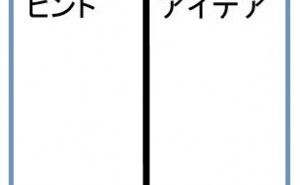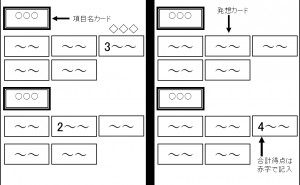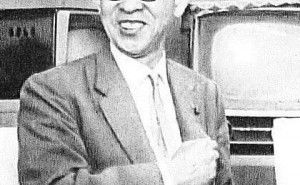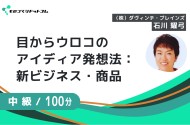1.暗い部屋の片隅で蛍光紙が発光しているのを見て、X線を発見した、ドイツの物理学者 ウィルヘルム・コンラッド・レントゲン
彼がX線を発見したのは1895年です。真空にしたガラス管内に電極を封じ込め、電圧を高めると陰極線が発生し、ガラスが蛍光を発する。その現象にレントゲンは興味を持ちました。
あるとき、暗い部屋の片隅で何かが緑色に光っていることに気きます。調べてみると、バリウムの合成物を塗ったボール紙が、ガラス管から1メートル近く離れているにもかかわらず、蛍光を発しています。そして、ガラス管と蛍光紙のあいだに厚い本を置いても、紙は蛍光を発し、レントゲンは陰極線から目に見えない放射線が発せられていると考えました。
ガラス管と蛍光紙のあいだに鍵、猟銃、本、ペンや自分の手を置いてみると、くっきりその形が写し出され、手の骨の影が現れます。妻の手で試すと、やはり手の骨と指輪が写ります。彼はこの放射線にX線という名をつけましたが、これは数学で未知数を表すときに使うXにちなんだものです。
レントゲンはこの発見によってノーベル賞を受賞しました。彼は、X線に関してどんな特許も取ろうとせず、金銭的な利益を得ることはありませんでした。また、個人の名をつけるべきではないといって、X線をレントゲンと呼ぶことにも反対しました。
2.手分けして牛を解体している光景を見て、流れ作業による自動車組み立て方を思いついた、アメリカのフォード自動車社長 ヘンリー・フォード