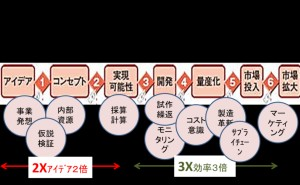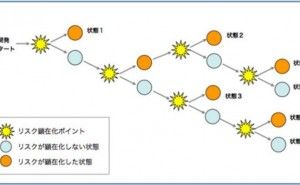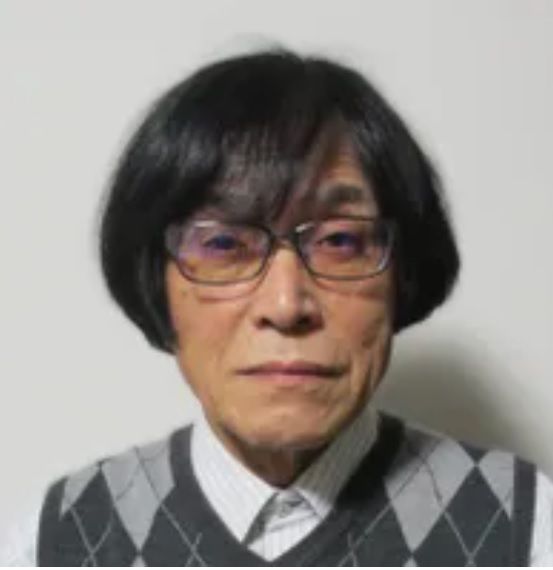製造現場や製品使用の場面で発生する事故や不具合。その原因をたどっていくと、多くは「人のミス」、つまりヒューマンエラーに行き着きます。しかし、単純に「作業者が注意不足だった」と結論づけてしまうのは危険です。現実には、そのミスが起こる環境や仕組みを作ったのは設計側であるケースが少なくありません。設計者の仕事は、図面やCADデータを作るだけではありません。「人が安全・確実・効率的に作業できる状態をデザインする」ことが重要です。今回は、ヒューマンエラーの基本と、設計によって防げるエラー予防の考え方、そして現場で役立つ具体例をご紹介します。
1. ヒューマンエラーとは何か
ヒューマンエラーは、単なる「うっかり」から深刻な事故まで幅広く、発生の仕組みを理解することが対策の第一歩です。
【ヒューマンエラーの主な分類】
- スリップ(Slip)・・・・・意図は正しいが、動作や操作が間違う。例:似た形のボタンを押し間違える
- ラプス(Lapse)・・・・・記憶や注意が抜け落ちる。例:ネジの締め付けを一箇所忘れる
- ミステイク(Mistake)・・判断や計画自体が誤っている。例:安全装置を無効化する操作が正しいと思い込む
発生要因は、疲労、時間的プレッシャー、習慣化による油断、情報不足、過剰な情報などです。例えば、組立ラインで左右対称の部品を反対に取り付けてしまった事例は、まさに設計段階での「区別しやすさ」への配慮不足から生じたエラーです。