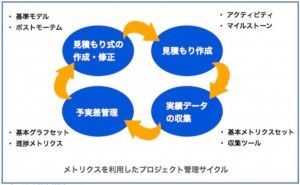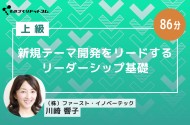【この連載の前回、新規事業×しんどいを乗り越える鉄則:マネージメント層、新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その102)へのリンク】
◆ 新規事業テーマ活動における人的リソースの考え方
日々、新規事業テーマの創出の支援をしていると、こんな話があがります。
新規事業はもちろん取り組む必要があるけれど、人をかけることができません。
当然ながら現在の利益の源である既存事業は最優先で取り組みたい業務であり、否定しません。目標とする事業売上を達成するべく活動に邁進する現場においては、当然ともいえる判断です。しかしながら経営層が同じ考え方では、どのような結果におちいるでしょうか。
経営層が直近の利益ばかりを追求する傾向の場合、現場も同じ意識で業務を行うことになりますので、最悪、製品ライフサイクルの終焉とともに事業が縮小してしまう可能性が高ま...