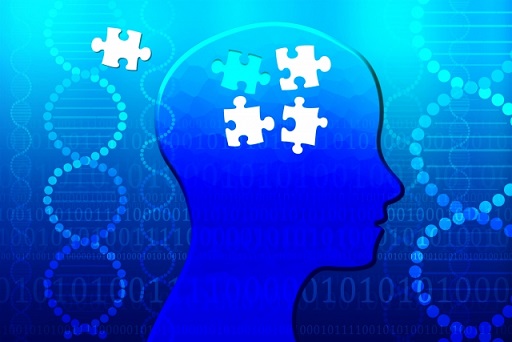弊社では、業務報告書の作成を依頼されることがあります。これは、依頼者が行なった業務(仕事)の報告書を弊社が書くことです。もちろん、弊社の専門分野での業務が対象です。依頼された業務報告書を書くとき気になることがあります。それは、「依頼者の頭の中から業務の方針が抜けていることがある」ということです。そこで、今回の記事ではこのことについて書きます。
1. 業務の枠組みを確認する
業務報告書を書く場合には、“わかりやすい業務報告書(読み手に内容が明確に伝わる業務報告書)”を以下の手順で書きます。
手順1:依頼者が行なった業務内容を確認する(業務内容を掘り下げて理解する)。
手順2:業務報告書の構成を考える。
手順3:手順2の結果に基づき業務報告書を書く。
これまでの記事で何度も書いていることですが、伝えるべき内容を書き手が掘り下げて理解していることで“わかりやすい文書”を書くことができます。したがって、依頼者が行なった業務内容を確認すること(業務内容を掘り下げて理解すること)でわかりやすい業務報告書を書くことができます。そのため、手順1は重要な作業です。
手順1の中では“業務の枠組み”を必ず確認します。業務の枠組みの確認とは以下のことを確認することです。
*業務の目的を確認する。
*業務の方針を確認する。
*業務の手順を確認する。
この業務の枠組み(業務の目的・方針・手順)を頭の中に入れたうえで依頼者が行なったことを確認すると業務の内容が理解しやすくなります。
2. 業務の方針が抜けている
業務の枠組みの中で“業務の方針”は重要な内容ですが、依頼者の頭の中からこれが抜けていることがあります。
業務報告書を書くための資料(依頼者から渡された資料)を読んでも業務の方針がわからない場合には、依頼者に「業務の方針は何ですか?」と聞きます。しかし、依頼者がすぐに回答できないことがあります。しばらく考えてから「◯◯です」と答えます。
これは、依頼者の頭の中から業務の方針が抜けていたからです。業務の方針が頭の中にあればすぐに「◯◯です」と答えることができます。
業務の目的とは業務のゴールと考えることができます。それに対して、業務の方針とは、「業務の目的(ゴール)に至るまでの道」と考えることができます。ゴールがあれば、スタートからそこに至るまでの道があります。すなわち、業務の目的があれば業務の方針もあります。
例えば、「業務の目的は、△△地区の復興計画を立案すること」という業務があったとします。この業務のゴールは「△△地区の復興計画を考えること」です。この目的に対する方針として、例えば、「△△地区に住む住民も参加する委員会を立ち上げその中で復興計画を検討する」を考えたとします。
この場合、業務の目的と業務の方針との関係は、「『委員会で復興計画を検討する』という道を進んで『△△地区の復興計画を考えること』というゴールに至る」という関係になります。
業務報告書に、「今回の業務では、『△△地区に住む住民も参加する委員会を立ち上げその中で復興計画を検討すること』を業務の方針とする」と書くことで復興計画を立案するための道がわかります。
これまでに書いたように、業務の目的があれば業務の方針もあります。依頼者も、業務の方針に基づき業務を行っていると思います。しかし、「今回の業務を進める場合には◯◯を方針とすることが当たり前だ」と思ってしまったた...