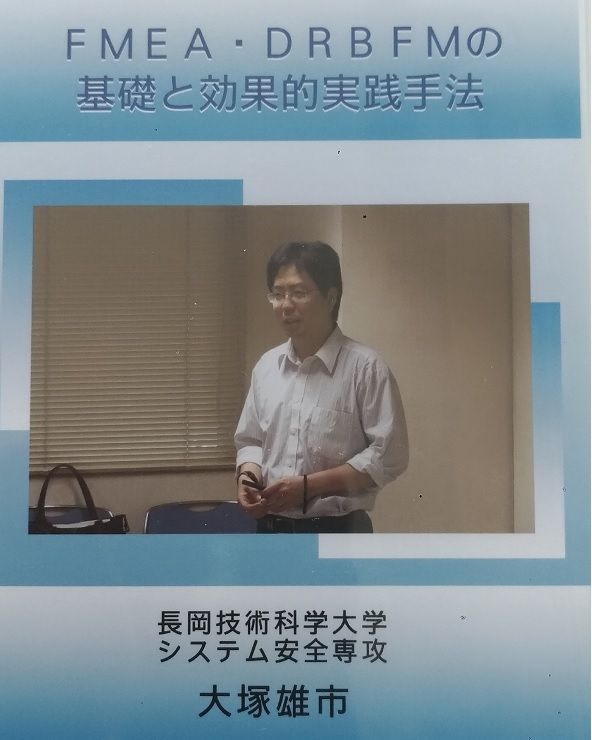・初めて化学分析に携わる方を対象とした、入門セミナー
・代表的な分析機器の基礎知識とその使い分け
・「分析ミスあるある」:起こりがちなミスを学び取ろう
・受講後すぐ活用できるチェックリストや、Q&A集も進呈
セミナー趣旨
「分析事始め」は、企業において初めて化学分析に携わる方を対象とした、入門セミナーです。本セミナーでは、「分析で何がわかるのか?」という根本的な問いからスタートし、分析の進め方や判断のための視点、サンプリングの重要性、代表的な分析機器とその使い分け、さらには現場で起こりがちなミスに至るまで、体系的に学びます。
分析の基本的な考え方を身につけるとともに、現場ですぐに活かせる実践的な視点を提供することが、本セミナーの目的です。
話の途中でいくつかの「分析ミスあるある」話を挿入することで、実際の現場でありがちな落とし穴やトラブル例を紹介し、ミスの原因を具体的に捉え、未然に防ぐための着眼点を身につけていただきます。また、実務に直結した事例をもとに参加者とディスカッションを行うことで、分析をより身近なものとして感じていただける構成となっています。さらに、受講後すぐに活用できるチェックリストやQ&A集などの補足資料もご用意しています。
これから現場力を高めていきたい分析初心者の方にとって、学びの機会にご利用下さい。
セミナープログラム
1.分析でわかること
1.1 分析とは何をすることか
1.2 分析が果たす役割と、現場での活用例
2.分析とはどんなことをするのか?
2.1 分析でわかること
2.2 目的と手法のつながり
・分析ミスあるある(1):目的があいまい
3.分析する際に考慮すべきこと
3.1 何を知りたいか?
定性分析/定量分析/構造解析/物性測定
3.2 何を測るのか?
分析対象(成分、異物、添加剤など)
3.3 どのように測定するのか?
分析手法の選択肢と判断基準
3.4 どのような状態を測定するのか?
固体/液体/気体、前処理の必要性
3.5 結果の使い道(目的と連動)
判定・報告・対策など
・分析ミスあるある(2):手法選択ミス
4.分析で最初にやるべき事
4.1 試料の確認と取り扱い
4.2 サンプリングと均質性の重要性
・分析ミスあるある(3):サンプリングの失敗
5.分析で使用される測定機器の基礎知識(よく耳にする分析機器、どんな装置?)
5.1 観察を行う装置:実体顕微鏡・光学顕微鏡
5.2 観察+元素分析を行う装置:走査型電子顕微鏡(SEM)+エネルギー分散型X線分析装置(EDS)
5.3 元素の定性・定量を行う装置:
蛍光X線分析装置(XRF)、誘導結合プラズマ発光分光分析装置(ICP-OES)・質量分析装置(ICP-MS)
5.4 官能基の定性・定量を行う装置:フーリエ変換赤外分光光度計(FT-IR)
5.5 色や吸光特性を測定する装置:紫外可視分光光度計(UV/Vis)
5.6 成分を分離・定量する装置(有機化合物・添加物など):
高速液体クロマトグラフ(HPLC)、ガスクロマトグラフ(GC)、ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS)
5.7 物質の結晶構造を測定する装置:X線回折装置(XRD)
5.8 物質の熱的性質を測定する装置:熱重量測定装置(TGA)、示差走査熱量計(DSC)
・分析ミスあるある(4):原理を知らずに使用
・分析ミスあるある(5):バラつきを機器のせいにする
6.事例(ディスカッションを含む)
6.1 重量分析の例:ポリマーの重量分析、充填剤の定量、含水率・揮発分の測定
6.2 定性分析の例:樹脂の種類
6.3 混合物分析の例:定性と定量、添加剤
6.4 異物分析の例:異物の正体
7.おわりに:楽しく語らう、フリートークセクション
~分析業務を巡る講師の経験談を交えて~
・分析の部署に配属されてどう思ったか
・どうやって分析技術を覚えていったか
・自分は分析に向いていないと思っていたこと
・失敗談
・コミュニケーションの取り方
・報告書で先輩に言われたこと
・分析に長く関わって今思うこと など
*折角の対面型セミナーです。受講者の皆さんのことも教えて頂ければ嬉しいです。
8.質疑応答
<補足資料>
・チェックリスト(分析前の確認、機器分析前の確認、分析簡易フローチャート;各1ページ)
・トラブル事例Q&A集(10項目質問程度;2-3ページ)
・測定機器早見表(本日講演機器のまとめ;分析目的と使用機器、試料状態、定量性、注意点などの概略;1ページ)
*途中、お昼休みや小休憩を挟みます。
セミナー講師
あなりす 代表 工学博士 岡田 きよみ 氏
■ご略歴
1984-2005 王子ホールディングス株式会社
<神埼製紙合併→新王子製紙合併→王子ホールディング、上級研究員>
(主に、画像用感熱フィルムの開発および分析業務担当)
2006-2016 株式会社パーキンエルマージャパン(分子分光シニアスペシャリスト)
2016-2019 京都大学 工学研究科(セルロースナノファイバー関係 特定研究員)
2018- あなりす(分析コンサルタント、受託分析会社)
セミナー受講料
1名50,600円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき39,600円
*学校法人割引:学生、教員のご参加は受講料50%割引。
受講について
- 感染拡大防止対策にご協力下さい。
- セミナー会場での現金支払いを休止しております。
- 新型コロナウイルスの感染防止の一環として当面の間、昼食の提供サービスは中止させて頂きます。
- 配布資料は、当日セミナー会場でのお渡しとなります。
- 希望者は講師との名刺交換が可能です。
- 録音・録画行為は固くお断り致します。
- 講義中の携帯電話の使用はご遠慮下さい。
- 講義中のパソコン使用は、講義の支障や他の方の迷惑となる場合がありますので、極力お控え下さい。
場合により、使用をお断りすることがございますので、予めご了承下さい。(*PC実習講座を除きます。)
受講料
50,600円(税込)/人
※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です
開催日時
10:30 ~
受講料
50,600円(税込)/人
※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます
※銀行振込、コンビニ払い
開催場所
東京都
【大田区】大田区産業プラザ(PiO)
【京急】京急蒲田駅
主催者
キーワード
分析化学前に見たセミナー
※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です
開催日時
10:30 ~
受講料
50,600円(税込)/人
※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます
※銀行振込、コンビニ払い
開催場所
東京都
【大田区】大田区産業プラザ(PiO)
【京急】京急蒲田駅
主催者
キーワード
分析化学関連セミナー
もっと見る関連教材
もっと見る関連記事
もっと見る-
なぜ「作りやすさ」は利益を生むのか?DFMAとフロントローディングの真価
【目次】 製品開発において、市場投入までのスピードとコストは企業の競争力を左右する重要な要素です。多くの企業は、製品の機... -
AIの無断学習とは?クリエイターの著作権は守られるのか【日米欧の法規制を比較解説】
【目次】 近年、目覚ましい発展を遂げているAI技術は、私たちの生活や働き方を根底から変えつつあります。中でも、テキストや画像を生成す... -
地中熱とは?知られざる再生可能エネルギー「地中熱」の可能性を解説
【目次】 再生可能エネルギーと聞いて、太陽光や風力を思い浮かべる方は多いでしょう。しかし、私たちの足元、大地にもクリーンで安定したエ... -
デジタルサービス法(DSA)とは?情報プラットフォームの責任と違法情報対策を徹底解説
【目次】 現代社会において、インターネット上の情報流通プラットフォームは、私たちの生活、経済、文化を支える不可欠なインフラとなってい...