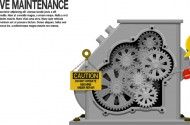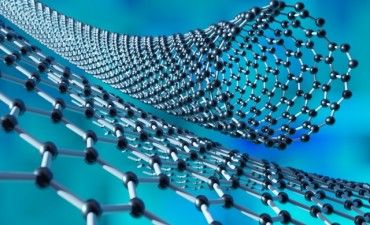混ざりやすさ、溶けやすさ、濡れやすさ、
くっつきやすさの正しい判断!
混合、溶解、塗布プロセスの制御、トラブル対策に!
セミナー趣旨
化学物質の製造現場では、混合・溶解・塗布などの操作が頻繁に行われる。これらの現象の良否はSPや表面張力を用いて考えることで制御が可能である。本講ではSPと表面張力を分子間力の観点から平易に解説し、コーティング分野への応用例をできるだけ多く紹介する。
習得できる知識
溶解性パラメーター・表面張力に関する基本的な知識、溶解・混合の良・不良とSP値との関係、ぬれ・ハジキ(接触角)と表面張力との関係
セミナープログラム
1.溶解性パラメーター(SP)
1.1 溶解性パラメーター(SP)とは
1.2 SPと溶ける・混じる
1.3 三次元SP(ハンセンパラメーター)
1.4 様々な溶剤や高分子のSP値
1.5 濁度滴定法による高分子のSP値の決定
1.6 粉体のSP値について(沈降安定性の支配因子)
1.7 化学構造式から計算によりSP値を求める
1.8 コーティング材料設計におけるSPの応用例
(1)相分離型塗料におけるSP値を用いた相分離制御
(2)被塗物への密着性とSP値
(3)SP値を用いた粒子表面の評価
2.表面張力(表面自由エネルギー)
2.1 表面張力とSP値(どちらも由来は分子間力)
2.2 表面張力とぬれる・ハジく(親和性とぬれ性は関係ない)
2.3 拡張ぬれと付着ぬれ
2.4 ヤング式とデュプレ式、付着仕事
(1)接触角を表面張力から予測する
(2)接触角から固体の表面張力を決定する
2.5 表面張力の成分分け
2.6 表面張力・界面張力の測定方法
(1)液体の表面張力の測定方法(ウイルへルミ法、白金リング法)
(2)固体粉体の表面張力の測定方法(毛管浸透法)
2.7 コーティング材料設計における表面張力の影響
(1)ぬれ障害型ハジキ
(2)異物ハジキ
(3)被塗物への密着性と表面張力
3.強い相互作用を表すパラメーター
3.1 発熱的相互作用と吸熱的相互作用
3.2 n-メチルピロリドン(NMP)がポリフッ化ビニリデン(PVdF)を良く溶かすのは何故?
3.3 表面張力の酸塩基成分分けと塗料の密着性
【質疑応答】
セミナー講師
小林分散技研 代表、東京理科大学 理工学部 客員教授 博士(工学) 小林 敏勝 氏
【略歴】日本ペイント(株)を経て現職。色材協会名誉会員(元副会長)
【専門】粒子分散・界面化学
セミナー受講料
1名につき 50,000円(消費税抜、昼食・資料付)
〔1社2名以上同時申込の場合のみ1名につき45,000円〕
主催者
開催場所
東京都
※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です
開催日時
10:00 ~
受講料
55,000円(税込)/人
※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます
※銀行振込、会場での支払い
※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です
開催日時
10:00 ~
受講料
55,000円(税込)/人
※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます
※銀行振込、会場での支払い
類似セミナー
-
 2026/02/05(木)
10:00 ~ 16:00
2026/02/05(木)
10:00 ~ 16:00シランカップリング剤の効果的活用のための基礎と機能材料への応用~種類と機能、選択法と効果的使用法、反応と作用機構、処理効果、ナノ粒子の調製・粒径制御、無機材料への表面処理法・処理表面の分析・解析法、具体的応用例~【会場/WEB選択可】WEB受講の場合のみ,ライブ配信+アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可)
 TH企画セミナールーム or WEB受講
TH企画セミナールーム or WEB受講
関連セミナー
もっと見る関連記事
もっと見る-
【真空不要】大気圧プラズマ(AP)とは?接着不良を解決しコストを激減させる「魔法の風」の仕組み
【目次】 製造業の現場では、製品の品質と耐久性を決定づける「表面処理」が極めて重要な工程です。これまで、高機能な表面処理を行うために... -
【液体を一瞬で粉末に】スプレードライ(噴霧乾燥)とは?原理・メリットから「粉ミルク」等の応用例まで
【目次】 現代の製造業、特に食品、医薬、化学の分野において、「乾燥」工程は最終製品の品質を決定する極めて重要なプロセスです。原料に含... -
驚異の多孔質構造が変える社会環境、MOF(金属有機構造体)の構造・機能、その市場とは
【目次】 現代社会は、地球温暖化対策のための二酸化炭素(CO₂)回収、クリーンエネルギーとしての水素貯蔵、医薬品の高効率な運搬、そして環... -
静電粉体塗装とは?常識を覆す塗装技術!静電粉体塗装の可能性
【目次】 今日の製造業において、製品の表面処理は品質と機能性を左右する重要な工程です。その中でも、環境負荷の低減と高性能化を両立する...