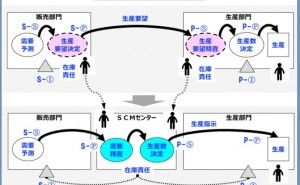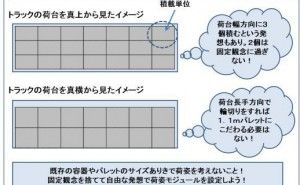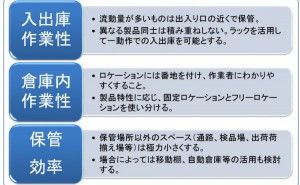1.物流業務の考え方
物流業務はアウトソースするという傾向があります。一方で自社自ら物流業務を行う内製化パターンを取っている会社もあります。この2つのパターン、どちらの方がメリットはあるのでしょうか。この判断は難しいところです。必ずしも一方がベストということは言えません。
(1)物流業務の内製化
主として内製で行う業務にはどのようなものがあるのかについて考えていきましょう。
筆頭に挙げられるのが物流企画業務でしょう。自社の物流をどのように組み立てていくのか、サプライチェーン全体効率との絡みで検討を行います。やはり自社の物流は自社の業務をよく知っていないと設計できないため、内製で行うことにメリットがあります。
(2)アウトソース化
アウトソース化のパターンについて考えてみましょう。まず多くの会社が外部に委託している物流業務の筆頭が輸送業務です。輸送を本業としている会社に任せることで、コスト的にも安全的にもメリットがあると考えられます。もちろん社員でも輸送は可能ですが、皆さんが一番心配されることが安全面です。ここはプロドライバーに依頼することは大きなメリットだと思われます。
次に梱包作業が挙げられます。これも社内で行うことは可能です。しかし意外とアウトソースしている会社が多いようです。そのメリットは、梱包設計を行う必要が無く、そのための人材を社内で抱えなくて済むことが挙げられます。また、専業者に任せることで、梱包資材を安く調達することがでることもメリットと言えるでしょう。
一方で梱包価格はアウトソースした場合、それを精査しづらいという課題があります。なぜなら、自社で実施したことが無い場合、梱包にかかわるコストを知らないからです。
アウトソースの三つ目が保管業務です。工場など自社物件で十分な保管スペースが無い場合、外部倉庫に保管と入出庫を委託する場合があります。このメリットは自社で倉庫を用意しなくて済むということが挙げられます。ただし、常に在庫を見ているわけではないため、余分な在庫がたまっても気づきにくいというデメリットもあります。

2.管理改善
メーカーでは製造や生産管理に詳しい人はいるものの、物流管理に詳しい人は少ないと思います。そもそも物流人財を育成していないのです。このような状況下、物流管理業務をアウトソースしたいと考える会社もあることと思います。
しかし、自社の物流を一番知っているのは自社の社員であることは間違いありません。そのため、物流企画業務を物流事業者に丸投げしても、満足いく回答はまず100%来ないと考えた方がよいでしょう。
物流企画業務は社内で行うか、コンサルタントを入れて一緒に進めるかのどちらかになるでしょう。では物流管理業務はどうでしょうか。物流管理はある程度物流事業者に委託しても可能な業務です。たとえば毎月の物流のパフォーマンスを見ていく業務などはアウトソースが可能です。
皆さんもお聞きになったことがあるかもしれませんが、「3PL(サード・パーティ・ロジスティクス)」という業種があります。この意味するところは、荷主でも物流事業者でもない第三者(サード・パーティ)が、荷主の物流業務を包括的に請け負うとともに、荷主に物流改革を提案する業務ということになります。
もしこの定義に当てはめたとしたら、我が国には3PL事業者は存在しないことになります。物流作業を請け負うことができても、物流改革を提案できる業者はいないからです。一方で物流作業を請け負いつつ、その結果について報告を行うぐらいの業務ならできる業者は存在します。
そこで、物流作業の結果を認識し、課題などを抽出してその改善を一緒に行うタイプのアウトソースはお勧めです。物流人財がいない会社では人が育つまでの間、この方式をとることはよいと思います。実はこのタイプのアウトソースは受注側にもメリットがあるのです。それは荷主から依頼される物流管理を実際に行いつつ、それをパッケージ化して商品にできるからです。それと同時に物流事業者側の人財育成にもつながるのです。一緒に改善を実施していくことで、改善力も磨かれます。
今まであまり物流改善に取り組んでこなかった物流事業者にとって、お金をもらいながら人財育成と物流商品開発ができるのですから、こんなにおいしいアイテムはありません。

3.業務の中長期計画
大手通販事業者が受注後2時間半で商品を顧客に届けるということが話題になっています。通販の差別化は商品ラインナップだけでなく、物流も大きなファクターに間違いありません。では物流では何が差別化アイテムになるでしょうか。それはずばり、リードタイムとコストです。顧客は買ったものはすぐに欲しい。しかも配送料が無料となれば顧客は喜ぶわけです。
そこでこの大手通販事業者も、このリードタイムとコストを武器に、シェア拡大を狙っているのです。しかしここで一つ大きな決断がありました。それは配送を物流事業者に任せるのではなく、自社の社員で行うということです。今まで輸配送は専業者にアウトソースすることが半ば常識のようなものでした。
しかし昨今のトラックドライバー不足や運賃の値上げもあり、必ずしも物流事業者を使うことが常にメリットが出ることではなくなったのです。たしかに労働力不足でものを顧客に届けられないようでは話になりません。それよりも確実に配送ができ、顧客対...