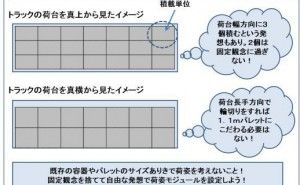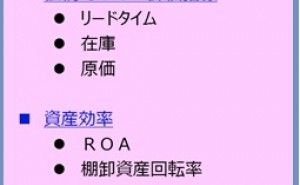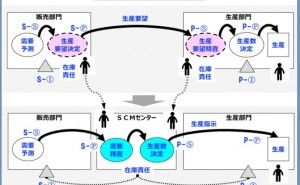◆トヨタ生産方式とは
トヨタ生産方式とは、トヨタが自社の生産を最適化するために考案した仕組みの総称で、7つのムダ(つくりすぎ、手待ち、運搬、加工、在庫、動作、不良)を最小化するためにJIT(Just in Time)、カンバン、平準化、アンドン、なぜなぜ5回、ニンベンの付く自働化、一個流しなどなど多くの方法論が徹底されます。 しかしながら、その本質は「意識革命」であり、問題を「見える化」し、それを全員で日々改善しつづけるところにあると言われます。今回は、物流改善にトヨタ生産方式の本質である「意識革命」をどう取り入れるかを事例解説します。
◆ 物流勉強会での気づきとは
1. 個人のノウハウが水平展開されない問題
物流改善スキルを学ぶためにどのような取り組みをされていますか。スキル向上に、外部講習を受けたり社内勉強会を開催したりすることが一般的だと思います。社内の先輩社員が新入社員や部署間異動者に対して改善事例を教えるといったこともよくあることだと思います。
会社の中で物流改善スキル向上のためのカリキュラムを組んでいるところもありますが、これはかなり上級レベルと言えるのではないでしょうか。会社でよくあるパターンが個人の中にノウハウが蓄積されることです。蓄積されること自体は非常に良いことなのですが、それが水平展開されないことに問題がありそうです。
輸送に関する知識であればAさんに聞けばわかる、荷役に関する知識であればBさんに聞けばよい、というようなことになっていませんか。会社として物流改善の総合力を向上していくのであれば、皆でスキルを共有していくことが望ましいと思われます。
2. 学びの場で、会話を通して物流改善スキル向上
定期的に勉強会の活動を実施して、その分野でのスペシャリストが先生になって教えていくといったしかけを作って管理してみてはいかがでしょう。教えられる方も勉強になりますがそれ以上に教える側にとっても学びの場となること請け合いです。教える人は受講者からいろいろな質問を受けることになります。そうなると今まで自分が気づかなかったような点に気づかされるケースが出てくるのです。
「ああ、こういった見方や考え方もあるのだ」という気づきです。これは相手の意見を受け入れてこそ身につくものです。物流に関するノウハウに限らずすべてについて言えることです。
このケースでは輸送や荷役、保管など物流に関する知識、そしてそれらを改善するための着眼点などを教える人が受講者と会話をする中で出てくることです。つまりお互い会話を通して物流改善スキルが磨かれていくということなのです。
◆ 物流現場見学と意見交換
1. 会話を通して見える自分と違った視点
例えば物流現場を見学に行ったとしましょう。複数名で見学した場合、見学後にぜひ感想を述べ合うことを実施しましょう。この会話を通して見えることは「自分と違った視点」でしょう。
ある人はトラックの積み込み状況に注目している一方で、別の人は積荷の荷姿に注目しているかもしれません。
人間誰しも得意分野や興味のある分野があります。物流現場に行くとその分野を中心に見ることになると思われます。そうなると物流のすべてについて見ることにはならず、必ずと言っていいほど情報に偏りが出ることが考えられるのです。そこで見学後の情報交換が生きてくるのです。
2. 情報交換で自分の物差しを知る
同じ分野を見ていても感じ方が違います。そこそこのレベルだと感じた人もいれば、まだまだだと感じる人もいます。したがって別の人と情報交換すれば、「自分の位置と物差し」について意識することにつながるのです。そうなれば少し自分の見方は甘すぎた、というような意識の変化が生まれます。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
以上のように「見る分野の拡大」と「物差しの修正」といったことが各人に起こります。それによって何よりもその人のレベル向上につながっていくのです。いかがでしょうか。物流現場見学後の会話だけでもかなりの物流改善スキルレベルの向上が図られることがお分かりいただけたのではないでしょうか。
特に若い人たちにはこのような見学とディスカッションの機会を提供してあげると良いと思います。若い人たちはまだ現場を見る際に固定観念が少ないと従来から思われています。そこでまだ頭の中が真っ白な状態、柔軟性の高い状態の内にいろいろな現場の見方をを教え込んでいくのです。若い人たちが現場見学に行ってきた時にはぜひ感想を聞いてみましょう。中堅以上の人たちにも新鮮な情報がもたらされて大変役立ちます。
◆ 荷姿の課題からの会話
物流の問題を知りたい場合、物流をもっぱら仕事にしている人以外にも話を聞いてみると良いのではないかと思います。たとえば小売りの最前線にいる人とか、製造工程にいる人たちと話をしてみるのです。そうするとそういった人たちの話の中から物流として対応すべきヒントが見つかってくる可能性があるのです。
1. 小売りや製造の人たちとの会話
その話題の一つにパッケージングがあります。皆さんはパッケージングについてどれくらい意識されて仕事をされていますでしょうか。小売りが商品を陳列する際に段ボールから取り出しますが、この段ボールを開けにくい場合があります。理由としてお客様思考のパッケージングになっていないということが考えられます。
製造現場からも同様に、資材や部品を取り出しにくいパッケージングだという声が上がってきます。物流と言うと真っ先に「輸送」をイメージしがちですが意外とこのパッケージング、す...