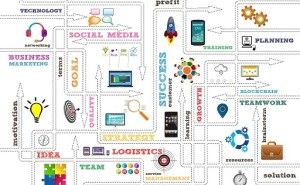STPマーケティング、STP分析、STP戦略とは、効果的な使い方をわかりやすく解説
1. STPマーケティングとは
STPマーケティングとは、セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングの頭文字を取ったもの。 市場を分割して狙いどころを絞り、競合とかぶらない自社製品の立ち位置を明確にすることが重要。フィリップ・コトラー博士が提唱したフレームワークでSTP戦略、STPマーケティングともいわれます。事業開発に使うか、商品開発に使うかと問われれば、後者のフレームワークです。ターゲットとポジションを具体的に考えると、どうしても商品単位に考えざるを得ないものです。
2. STPマーケティング、STP戦略を使うパターン
(1)アイデアを出そうとする場合
最初に市場・競合をセグメント化し、次にターゲットを決め、最後にターゲットに対する優位なポジションを取ろうします。アイデア=仮説を出そうとする場合に、STPの順番通り行かない事も多く、セグメントに分ける時にある程度ターゲットやポジションが見えていないと、良い分け方ができないこともあります。
(2)アイデアを評価する場合
アイデアを評価する時は検証のためのツールとしてSTP分析を使います。
3. セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングとは
(1)セグメンテーション
セグメンテーションがうまく出来たら、STPは終わったも同然です。なぜなら、市場を意味のある形で分解できるように、顧客が価値を感じる何かを特定する必要があるからです。特定するにはかなりの知見が必要です。この知見と結びついたセグメンテーションにこそ価値があり、簡単に分割しても意味のある結論は見いだせません。
(2)ターゲティング
セグメント化された図を見ると、ついつい空白の場所に市場がありそうな気がします。しかし実際にそうなのかは、実市場に聞いてみないと分かりません。
(3)ポジショニング
競合他社と違う価値を提供するのが差別化です。ポジショニングとは、他社と異なる価値を提供する差別化に他なりません。ポジショニングを決めようとすれば、ユーザーがどんな価値を感じて購買に向けて行動するかを知る必要がありますし、これに対して競合がどんな価値を提供しているのかを知る必要もあります。
4. STPマーケティング、STP分析、STP戦略の効果的な使い方
STPマーケティングでは、顧客の価値を感じる軸でセグメント分割し、空いているターゲットを見つけ、それに対するポジションを決定するという順番通りに行かない事が多く、いいセグメンテーションをするためには、顧客ごとにどんな購買基準で買っているかを知っている必要もあります、それを知ることができればSTP戦略が出来、STP分析として合理的に説明が出来ます。
5. STP戦略を成功に導くための実践的アプローチ
STP戦略は単なる分析ツールではなく、継続的な実践を通じて価値を生み出すためのプロセスです。成功のためには、いくつかの重要なアプローチを意識する必要があります。
(1)顧客理解の深化
セグメンテーションを精緻にするためには、顧客像をより深く理解することが不可欠です。デモグラフィック情報(年齢、性別、居住地)だけでなく、サイコグラフィック情報(価値観、ライフスタイル、購買動機)や行動データ(オンラインでの閲覧履歴、購買パターン)を活用することで、より意味のあるセグメントを抽出できます。顧客インタビューやアンケートを通じて生の声を聞くことも有効です。
(2)絶え間ない検証と修正
市場や競合の状況は常に変化します。一度設定したSTP戦略も、時間が経てば陳腐化する可能性があります。常に市場の動向をモニタリングし、設定したターゲットやポジショニングが現状に合っているかを定期的に検証することが重要です。必要に応じて、戦略を柔軟に修正する勇気を持つべきです。
(3)社内での共通認識の構築
STP戦略は、マーケティング部門だけでなく、製品開発、営業、カスタマーサポートなど、企業全体で共有されるべき共通言語です。全社員が同じ顧客像と価値提供の方向性を理解することで、一貫性のある顧客体験を提供でき、戦略の実効性が高まります。
6. デジタル時代におけるSTPの進化
デジタル技術の発展は、STP戦略のあり方を大きく変えています。膨大なデータを活用したより精緻なセグメンテーションが可能になり、デジタルチャネルを通じて特定のターゲットに合わせたメッセージを届けやすくなりました。
特に、オンラインでの顧客行動データは、従来の市場調査では得られなかったインサイトを提供します。例えば、どのウェブページを閲覧し、どの広告をクリックし、どのSNSで情報を共有したかといったデータを分析することで、顧客の潜在的なニーズや関心をより正確に把握できます。これにより、顧客の行動フェーズ(認知、検討、購買)に応じた、よりパーソナライズされたマーケティング施策を展開することが可能になります。
ポジショニングにおいても、デジタル空間でのブランドイメージ管理が重要です。顧客がオンラインでどのようにブランドを認識し、競合と比べてどのような立ち位置にあるのかを常に把握し、必要に応じてコミュニケーション戦略を調整する必要があります。
7. まとめ
成長社会において市場が伸びている時代は、供給者の論理でマーケティングを行うことができました。どんな製品を作り、価格を決め、流通チャネルを選択し、販売促進をするかはすべて製品供給側に委ねられていたのです。しかし、成熟社会を迎えて市場が飽和している現在は、買い手のニーズに寄り添わなくてなりません。これからの企業は、製品を提供するのではなく、顧客が抱える課題の解決が求められ、販売価格ではなく導入費用の適正化が求められます。流通は顧客の導入利便性に応えなくてはならず、Promotionよりも関係維持に向けた顧客とのCommunicationを重視したマーケティングを心掛けなくてはならないのです。成熟社会を意識したマーケティング戦略、市場を分割して狙いどころを絞り、競合とかぶらない自社製品の立ち位置を明確にするSTP戦略を立てることができるかどうかが、企業経営に求められるのです。