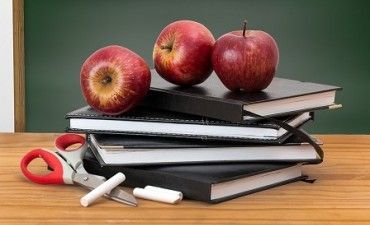品質表(QFD)とは、キーワードからわかりやすく解説
1. 品質表(QFD)とは
品質表(QFD)とは、まず顧客要求を徹底して洗い出して顧客表現のままに整理し、別途整理した品質特性との関連性をマトリクスで明確にする事で、要求品質重要度を品質要素重要度に転換して、要求に対応した機能、性能を設計します。 企画やテーマ設定の担当者は、分かっていながら目前の事実や自分の思い込みに引っ張られたコンセプトを設定しがちです。 そこで、このように作成した「品質表」を、必要に応じて「部品展開」「技術展開」「コスト展開」「FMEA」からQC工程表等に展開する方法が品質機能展開です。 製品仕様が顧客の声から設定される事と、その過程が明確に残る点で、極めて優れた製品仕様設定法です。
2. QFDの目的
QFDの目的は、QFDガイドブック(日本規格協会)の中で詳細に述べられています。実務的な視点で整理すると、要点は次のようになります。品質機能展開を実施するということは、要求品質展開表、品質表、業務機能展開表などの諸表を全て作成することではありません。その考え方やプロセスから対応策を探ることが狙いになります。
3. 製品開発活動とQFD
製品開発活動の中で課題は「コミュニケーション」と「モチベーション」の不足といわれます。QFDは新製品開発の品質保証を源流から行うために、企画・開発、製造、営業、そして品質保証のメンバーがチーム一体で進めていきます。したがって1つの表を中心に、部署をまたいだ意思疎通が可能になります。
また、それぞれの専門分野で意見を交わし、議論し、開発製品や技術についての理解を深めていく。これこそメンバーひとりひとりの「モチベーション」を、暗黙のうちに高めていたのです。 現在の開発では、部署をまたいでのワイガヤや技術に対しての議論が非常に少ないように見受けられます。ITを活用した上で、迅速な議論を行うことはけっして不可能ではないはずです。さらには、その過程を含めた結論を技術情報として蓄積していくことが、この時代には必要不可欠です。
4. QFDが生み出すチームの「集合知」
現代の複雑な製品開発においては、一人の天才がすべての課題を解決することは稀です。むしろ、多様な専門性を持つメンバーが協働し、互いの知識と知見を組み合わせることで、より高い次元の解にたどり着くことができます。QFDは、まさにこの「集合知」を効果的に引き出すためのフレームワークとして機能します。
顧客の要求を起点に、品質表という一つの共通言語を用いることで、開発、製造、営業、品質保証といった異なる部門のメンバーが、それぞれの視点から意見を出し合います。例えば、営業担当者は顧客の漠然とした「使いやすさ」という声を、エンジニアはそれを実現するための「ボタン配置」や「ソフトウェアのレスポンス速度」といった具体的な技術要素に落とし込んで議論します。製造担当者は、その技術要素が生産ラインでどのように実現可能かを検討し、品質保証担当者は潜在的な不具合リスクを洗い出します。
このように、QFDのプロセスは、単なる情報の伝達ではなく、知識の「交換」と「統合」を促進します。各メンバーが、これまで自身の専門領域に閉じていた情報を他部門と共有し、異なる視点から製品全体を俯瞰できるようになります。この相互作用を通じて、チームの誰もが「なぜこの仕様が必要なのか」という根本的な理由を深く理解することが可能になります。これは、単に与えられた仕様をこなすだけの作業から、自律的に課題を発見・解決する創造的な活動へとメンバーの意識を変えるきっかけにもなります。
5. QFDによる暗黙知の可視化と継承
製品開発において、経験豊富なベテランが持つ「暗黙知」は、しばしば重要な成功要因となります。しかし、その知識は言葉にしづらく、個人に属するものとして埋もれてしまいがちです。QFDは、この暗黙知を可視化し、組織の共有財産へと昇華させる効果的な手段でもあります。
例えば、過去の失敗事例や、顧客からのクレーム対応で得られた教訓は、通常、個人の記憶や部署内の非公式な文書に留まります。しかし、QFDのプロセスの中で、そうした経験から導き出された「顧客が本当に求めていること」や「リスクの高い技術要素」は、品質表の評価項目や関連性マトリクスの中に明示的に反映されていきます。
一度可視化された知識は、特定の個人が異動したり退職したりしても失われることなく、組織に蓄積され、次世代の開発チームへと継承されます。これは、製品開発のサイクルを短縮し、過去の成功と失敗から学ぶ「組織的な学習能力」を高める上で極めて重要な意味を持ちます。QFDが提供する体系的な記録は、単なる仕様書ではなく、未来の開発者たちへの貴重な「知のバトン」となるのです。
さらに、この過程で可視化された情報は、新人教育やOJT(On-the-Job Training)にも活用できます。新人は、品質表を通じて、顧客の声から製品仕様がどのように導き出されたかという思考プロセスを追体験し、体系的に学ぶことができます。これにより、ベテランのノウハウが個人の勘や経験則にとどまらず、組織全体に浸透する文化として根付いていくのです。
6. QFDの導入を成功させるために
QFDは強力なツールですが、ただ単にマトリクスを作成するだけでは、その真価を発揮することはできません。成功の鍵は、ツールそのものよりも、それを使う「チームの姿勢」と「組織の文化」にあります。
まず、経営層や管理職は、QFDの導入を単なる業務効率化の取り組みではなく「顧客中心主義」の文化を醸成するための戦略的な投資として位置づける必要があります。そして、その目的と意義をチームメンバーに明確に伝え、自由闊達な議論を促す環境を整えることが不可欠です。
また、QFDは一朝一夕で習得できるものではありません。初期段階では、ベテランのファシリテーターを立てたり、外部の専門家を招いてワークショップを開催したりするなど、継続的な学習の機会を設けることが重要です。小さな成功体験を積み重ね、その効果をチーム全体で共有することで、QFDに対する抵抗感を減らし、自律的な運用へと繋げることができます。
最後に、QFDのプロセスから得られた知見は、単に紙やデータとして保存するだけでなく、定期的にレビューし、生きた知識として活用し続けることが大切です。品質表に記載された顧客の声が、その後の製品改善や新製品のコンセプト立案にどう活かされたかをチーム全体で振り返ることで、QFDの価値が再認識され、次なる開発へのモチベーションへと繋がります。
QFDは、単に高品質な製品を作るための技術的な手段ではありません。それは、人と人、知識と知識を結びつけ、組織全体を成長させるための「対話の場」なのです。この本質を理解し、実践することで、私たちは、変化の激しい現代社会において、顧客の心に響く、真に価値ある製品を生み出し続けることができるでしょう。
「品質機能展開(品質表)」のキーワード解説記事
もっと見るQFD(品質機能展開)を深く知る 【連載記事紹介】
QFD(品質機能展開)を深く知る、連載記事が無料でお読みいただけます! ◆QFD(品質機能展開)とは 1960年代...
QFD(品質機能展開)を深く知る、連載記事が無料でお読みいただけます! ◆QFD(品質機能展開)とは 1960年代...
QFD-TRIZ-TMの連携適用による開発事例【連載記事紹介】
QFD-TRIZ-TMの連携適用による開発事例が無料でお読みいただけます! ◆QFD-TRIZ-TMの連携適用による...
QFD-TRIZ-TMの連携適用による開発事例が無料でお読みいただけます! ◆QFD-TRIZ-TMの連携適用による...
QFD(品質機能展開)とは 【連載記事紹介】DVD教材もご紹介
QFD(品質機能展開)の連載記事が、無料でお読みいただけます! 【特集】連載記事紹介の一覧へ戻る ◆QFD(品質機能展開)とは QFD(Qual...
QFD(品質機能展開)の連載記事が、無料でお読みいただけます! 【特集】連載記事紹介の一覧へ戻る ◆QFD(品質機能展開)とは QFD(Qual...
「品質機能展開(品質表)」の活用事例
もっと見るQFDが目指している理想、デザイナーと技術者が融合して、共通の価値を目指して創造活動を実現
▼さらに深く学ぶなら!「QFD」に関するセミナーはこちら! ▼さらに幅広く学ぶなら!「分野別のカリキュラム」に関するオンデマンドセミ...
▼さらに深く学ぶなら!「QFD」に関するセミナーはこちら! ▼さらに幅広く学ぶなら!「分野別のカリキュラム」に関するオンデマンドセミ...
QFD(品質機能展開)、TRIZ、タグチメソッドの融合について
▼さらに深く学ぶなら!「品質工学」に関するセミナーはこちら! ▼さらに幅広く学ぶなら!「分野別のカリキュラム」に関するオンデ...
▼さらに深く学ぶなら!「品質工学」に関するセミナーはこちら! ▼さらに幅広く学ぶなら!「分野別のカリキュラム」に関するオンデ...
QFD の難しいところとは
グリーンベルト認定のプロジェクトを指導していると、皆、たいてい同じところ(ツール)で躓く傾向...
グリーンベルト認定のプロジェクトを指導していると、皆、たいてい同じところ(ツール)で躓く傾向...
「品質機能展開(品質表)」に関するセミナー
もっと見るわかりやすいQFD(品質機能展開)の進め方〜効率的な展開手順・方法をお伝えします〜
要求品質の整理,重要度判定,開発活動のムダを省く着眼のしかたなど,具体例を交えてQFDの考え方・手順,要求品質展開表をやさしく作成する手順を解説します!
開催日: 2026-05-22
実務に役立つQFD(Quality Function Deployment:品質機能展開)の基礎と活用に向けた具体的ポイント
品質トラブル未然防止を効率的に実現する! 品質機能展開(QFD)の本質,課題の視える化(共有化),DR活用による開発業務効率可,QFDと他の技法(FMEA・FTA・TRIZ...
開催日: 2026-03-10
QFDセミナー(基礎編)-その原点を考える
QFD(品質機能展開)は、顧客要求を徹底して書き出して整理し、別途整理した品質特性との関連性をマトリクス状に明確化する事で、顧客要求の重要度を品質要素の重要度に転換して、要...
開催日: オンデマンド
QFDセミナー(応用編)-守・破・離ー
QFD(品質機能展開)は、顧客要求を徹底して書き出して整理し、別途整理した品質特性との関連性をマトリクス状に明確化する事で、顧客要求の重要度を品質要素の重要度に転換して、要...
開催日: オンデマンド
「品質機能展開(品質表)」の専門家
もっと見る「感動製品=TRIZ*潜在ニーズ*想い」実現のため差別化技術、自律人財を創出。 特に神奈川県中小企業には、企業の未病改善(KIP)活用で4回無料コンサルを...
お客様の期待を超える感動品質を備えた製品を継続して提供するために、創造性と効率性を両立した新しい品質工学を一緒に活用しましょう。