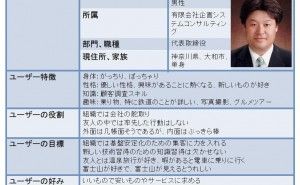コンジョイント分析とは、キーワードからわかりやすく解説
1. コンジョイント分析とは
コンジョイント分析とは、コンセプトが絞り込まれてきた時に、多くの組合せを試してみるのは非現実的なため、項目と水準を直交表に当てはめて一部の組合せを抜粋してユーザーの反応を分析し、最終的な仕様を決定してゆく方法です。商品企画の際、要求仕様を決定する場面で、計画的に仕様の要素を動かして種々の組み合わせを作り、顧客調査や顧客アンケートによって、組み合わせ案を評価してもらい、最も良い要求仕様を決める方法です。
2. コンジョイント分析:種々の組み合わせの作り方
すべての組み合わせを評価するのが一番ですが、属性(仕様)が7つ、それぞれ水準が2つの場合は、2×2×2×2×2×2×2である128案にもなり、非常に膨大な評価となってしまいます。ここに直交表を活用すると、属性(仕様)が7つ、水準がすべて2つの場合、8案を評価するだけで、128案評価したのと同じ評価が得られます。顧客調査をする際、128案を評価するより8案の方が、設計する側も回答する側も手間が省けます。
3. コンジョイント分析:分析結果の考え方
各属性の水準値が、全平均に対して±効果を持つものです。これを効用値といいます。+の場合全平均に対して+の効果を及ぼします。このことから、+の値が大きいほど、+の効果をもたらします。逆は全平均から-の効果となります。
4. コンジョイント分析の具体的な進め方、段階的なアプローチ
コンジョイント分析は、単なるアンケート調査ではなく、戦略的な意思決定を支援するための体系的なプロセスです。その成功は、事前の準備と、結果の解釈・活用方法にかかっています。
ステップ1:分析目的と対象の明確化
まず、何を明らかにしたいのか、その目的を明確にします。「新しいコーヒーメーカーの最適な価格帯と機能の組み合わせは何か?」、「オンライン教育サービスのどの要素(価格、コンテンツ、サポート)が顧客の満足度を最大化するか?」など、具体的な問いを設定することが重要です。この段階で、分析の対象となる製品やサービス、そしてターゲットとなる顧客層を定義します。
ステップ2:属性と水準の設定
次に、評価対象となる製品やサービスを構成する「属性」と、それぞれの属性が取りうる「水準」を特定します。
属性:製品やサービスを特徴づける要素。例:コーヒーメーカーの「価格」、オンライン教育サービスの「コンテンツの種類」。
水準:各属性が持つ具体的な選択肢。例:価格の属性における水準として「5,000円」「10,000円」「15,000円」、コンテンツの属性における水準として「動画講義」「テキスト資料」「ライブセッション」など。
ここで重要なのは、属性と水準は、互いに独立していること、そして顧客が実際に意思決定に使う要素であることです。例えば、「高性能」という抽象的な属性ではなく、「高画質カメラ(2000万画素)」というように、具体的に測定可能な水準を設定します。
ステップ3:直交表の作成とプロファイルの生成
すべての組み合わせを調査することが非現実的であるため、統計学的な手法を用いて、調査対象の組み合わせを効率的に抽出します。このために「直交表」が活用されます。直交表は、属性と水準の組み合わせが偏りなく含まれるように設計されており、少数の組み合わせ(プロファイル)を評価するだけで、すべての組み合わせの効用値を推定することが可能になります。例えば、属性が5つ、それぞれ水準が3つある場合、理論上の組み合わせは3^5 = 243通りですが、直交表を用いることで、例えば18のプロファイルに絞り込むことができます。
ステップ4:アンケート調査の実施
直交表に基づいて生成されたプロファイルを、アンケート形式で顧客に提示し、評価を依頼します。評価方法には、いくつかの種類があります。
- レーティング法・・・各プロファイルに対し、「1(非常に不満)~7(非常に満足)」などのスケールで評価してもらう方法。
- 順位付け法・・・提示された複数のプロファイルを、好みの順に並べてもらう方法。
- 選択法・・・・・最も好きなプロファイルを一つだけ選んでもらう方法。これは最も実際の購買行動に近い評価方法とされ、近年主流になっています。
ステップ5:効用値の算出と分析
収集したデータを統計的に分析し、各属性の水準が全体に与える「効用値」を算出します。
- 効用値・・・各水準が顧客の選好にどれだけ寄与するかを示す数値。プラスの値が大きいほど、顧客の選好を高める効果が強いことを意味します。例えば、「価格:10,000円」の効用値が「価格:15,000円」よりも高い場合、顧客は10,000円の価格帯をより好むと解釈できます。
この効用値を用いることで、以下のことが可能になります。 - 各属性の重要度を把握・・・効用値の範囲(最大値と最小値の差)が大きい属性ほど、顧客の選択に与える影響力が大きい(重要度が高い)と判断できます。例えば、機能の効用値の範囲が価格のそれよりも大きい場合、この製品では価格よりも機能が顧客の選好を決定する上で重要であると結論付けられます。
- 最適な組み合わせをシミュレーション・・・算出した効用値を組み合わせて、まだ評価していないプロファイル(組み合わせ)の総合的な効用値を計算できます。これにより、理論上最も高い効用値を持つ、つまり最も顧客に選好されるであろう「最適な」製品仕様やサービス設計をシミュレーションできます。
5. コンジョイント分析の発展と応用
コンジョイント分析は、基本的な手法からさらに進化し、多様な分野で応用されています。
属性と水準の拡張・・・より複雑な意思決定の分析
従来のコンジョイント分析は、比較的シンプルな属性と水準を扱っていましたが、近年ではより複雑な意思決定に対応する手法が開発されています。例えば、「ブランドイメージ」や「デザイン性」といった定性的な属性も、画像や動画を提示することで水準として扱うことが可能になっています。
応用事例・・・マーケティングと政策決定
新製品開発・・・顧客が最も魅力を感じる機能、デザイン、価格の組み合わせを特定し、無駄な開発を避け、成功確率を高めます。
価格戦略・・・価格の変更が顧客の購買意欲にどのように影響するかをシミュレーションし、最適な価格設定を導き出します。
セグメンテーション・・・顧客の効用値のパターンを分析することで、好みや価値観が異なる顧客グループ(セグメント)を特定し、各セグメントに合わせたマーケティング戦略を策定します。
公共政策・・・環境規制、交通インフラ、公共サービスなど、政策オプションに対する市民の選好を分析し、より多くの人々に受け入れられる政策を立案するための根拠とします。
6. コンジョイント分析の限界と留意点
コンジョイント分析は強力なツールですが、その結果を過信してはなりません。いくつかの限界と留意点があります。
非現実的なプロファイル・・・アンケート調査で提示される組み合わせの中には、実際の市場では存在しない、あるいは物理的に不可能なプロファイルが含まれる場合があります。例えば、「超高性能で価格が非常に安い」といったプロファイルは、顧客の選好を歪める可能性があります。
回答者の意識と行動の乖離・・・アンケートでの回答が、必ずしも実際の購買行動と一致するとは限りません。特に、価格に対する選好は、実際の購買時には他の要因(ブランド、店舗の雰囲気、口コミなど)に影響されることがあります。
属性と水準の網羅性・・・分析に含まれない重要な属性や水準が存在する場合、結果の妥当性は低下します。例えば、スマートフォンを調査する際に「バッテリー寿命」という重要な属性を見落とすと、導き出された最適な組み合わせは現実の市場で失敗する可能性があります。
以上の点を考慮し、コンジョイント分析は、他の市場調査やデータ分析手法と組み合わせて用いることで、その真価を発揮します。単一のツールとしてではなく、包括的な意思決定プロセスの重要な一環として位置づけるべきです。