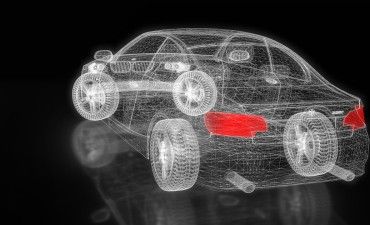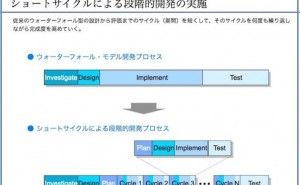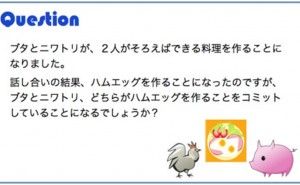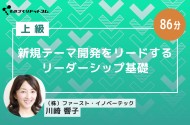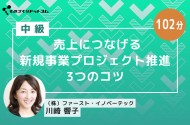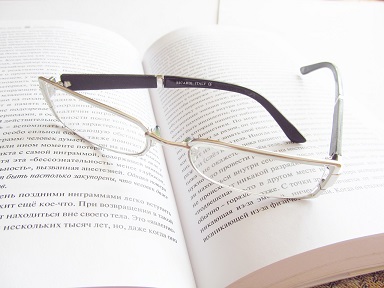
【この連載の前回、研究開発部門がとるべきリーダーシップの型、新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その97)へのリンク】
▼さらに深く学ぶなら!
「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら!
私のキャリアの出発点である半導体業界では、過去、3年周期で景気の良し悪しが変化すると言われたことがあります。この波に合わせて転職活動を繰り返す先輩方も多かったことを覚えています。そのうち3年周期説に陰りが生じ、半導体開発・製造に従事していると「まだ半導体やっているの?」と時代遅れと揶揄される時もあり、また大量生産品の減少が進み、コストで海外勢に勝てない状況が続き、日本の半導体業界は苦しい時期を過ごしました。
その後のコロナ渦を経て、現在はご承知のとおり、半導体産業に政府・民間企業による大規模投資が発表され、業界は再び盛り上がっています。以上は、私が従事してきた半導体業界における20年弱...