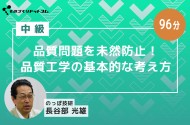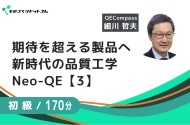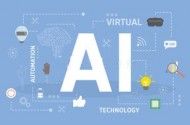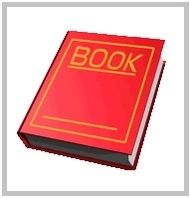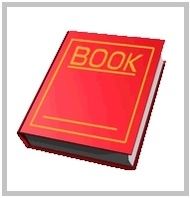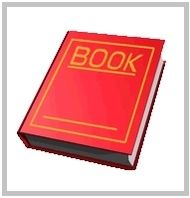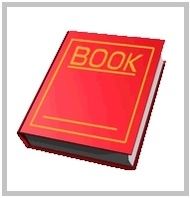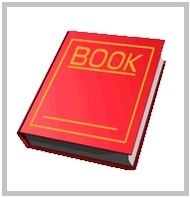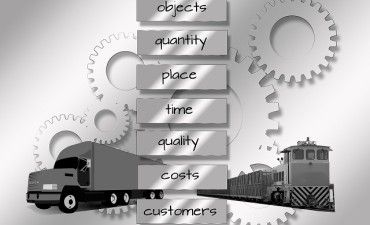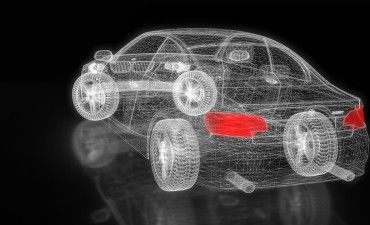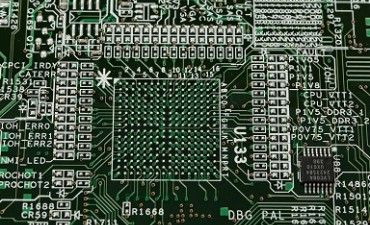このセミナーへの申し込みは終了しています。
類似セミナーを探す ↓
★ 有効な管理手法として感性価値の向上に貢献してきた感性品質手法(PQ)を学ぶ!
★ 時代の転換期を迎えている感性価値の管理手法としての発展性についても解説します。
講師
日本大学 芸術学部 講師 片岡 篤 氏
(元・日産自動車 デザイン本部 パーシブド・クオリティ部 マネージャー、PQアドバイザー・K 代表)
【経歴・活動・受賞など】
元 日産自動車(株) デザイン本部 パーシブド・クオリティ部 マネージャー、 PQアドバイザー・K 代表
1975年 日産自動車(株) 入社、デザイン本部にて多くの車種をデザインする。自身が手がけた二代目マーチは欧州カーオブザイヤーを受賞。2000年以降は感性品質部のマネージャーとして、新たな企業内デザインの仕組みを構築。現在、日本大学芸術学部デザイン学科講師、及びPQアドバイザーとして評価手法の普及と研究を進めている。
日本デザイン学会正会員、日本感性工学会正会員、自動車技術会正会員(デザイン部門委員会)
(元・日産自動車 デザイン本部 パーシブド・クオリティ部 マネージャー、PQアドバイザー・K 代表)
【経歴・活動・受賞など】
元 日産自動車(株) デザイン本部 パーシブド・クオリティ部 マネージャー、 PQアドバイザー・K 代表
1975年 日産自動車(株) 入社、デザイン本部にて多くの車種をデザインする。自身が手がけた二代目マーチは欧州カーオブザイヤーを受賞。2000年以降は感性品質部のマネージャーとして、新たな企業内デザインの仕組みを構築。現在、日本大学芸術学部デザイン学科講師、及びPQアドバイザーとして評価手法の普及と研究を進めている。
日本デザイン学会正会員、日本感性工学会正会員、自動車技術会正会員(デザイン部門委員会)
受講料
48,600円 ( S&T会員受講料 46,170円 )
(まだS&T会員未登録の方は、申込みフォームの通信欄に「会員登録情報希望」と記入してください。詳しい情報を送付します。ご登録いただくと、今回から会員受講料が適用可能です。)
S&T会員なら、2名同時申込みで1名分無料 1名分無料適用条件 1名分無料適用条件
※2名様ともS&T会員登録が必須です。
※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。
※3名様以上のお申込みの場合、1名あたり定価の半額で追加受講できます。
※受講券、請求書は、代表者に郵送いたします。
※請求書および領収証は1名様ごとに発行可能です。 (申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。) ※他の割引は併用できません。
セミナー趣旨
近年、自動車内外装の質感向上は、お客様の感性価値への要求を背景に重要度を増しています。そうした中で「感性品質手法(PQ)」は、有効な管理手法として感性価値の向上に貢献してきました。当手法は社内評価者による定性的な評価手法で、継続的な取り組みによって精度を向上させるヒューリスティックなアプローチですが、今回は身近な製品による演習を通して核となる評価手法を体験していただきます。加えてCASE等の時代変化の中で、転換期を迎えている感性価値の管理手法としての発展性についても、ご提案したいと思います。
セミナー講演内容
<得られる知識・技術>
・感性的な製品魅力の向上方法
・社内評価者の活用と育成
<プログラム>
1.はじめに
2.乗用車開発の概要
2.1 経緯
2.2 品質管理の視点
2.3 感性とは
2.4 日産PQの歴史
3.経営上の役割
3.1 組織的位置付
3.2 適用範囲の決定
3.3 戦略の重要性
3.4 事例
3.5 代用特性
4.評価体系
4.1 PQの定義とは
4.2 評価手法の特徴
4.3 評価スケール
4.4 ウエイト
4.5 検証プロセス
5.身近な製品を使った感性評価演習
5.1 ティーチング
5.2 個別評価
5.3 チーム評価
5.4 振り返り
6.導入へのご提案
6.1 今後の役割
6.2 導入方法
6.3 体制と人材
□質疑応答・名刺交換□
・感性的な製品魅力の向上方法
・社内評価者の活用と育成
<プログラム>
1.はじめに
2.乗用車開発の概要
2.1 経緯
2.2 品質管理の視点
2.3 感性とは
2.4 日産PQの歴史
3.経営上の役割
3.1 組織的位置付
3.2 適用範囲の決定
3.3 戦略の重要性
3.4 事例
3.5 代用特性
4.評価体系
4.1 PQの定義とは
4.2 評価手法の特徴
4.3 評価スケール
4.4 ウエイト
4.5 検証プロセス
5.身近な製品を使った感性評価演習
5.1 ティーチング
5.2 個別評価
5.3 チーム評価
5.4 振り返り
6.導入へのご提案
6.1 今後の役割
6.2 導入方法
6.3 体制と人材
□質疑応答・名刺交換□
受講料
48,600円(税込)/人
類似セミナー
関連セミナー
もっと見る関連教材
もっと見る関連記事
もっと見る-
電動建機のメリット・デメリットとは?普及を阻む課題と未来を徹底解説
【目次】 現代の建設業界は、技術革新と環境要件という二つの大きな波に直面しています。世界的なカーボンニュートラルへの... -
EVの未来を握る「eAxle」の衝撃とは?仕組み・メリット・課題をわかりやすく解説
【目次】 ※本記事を執筆した専門家「高原 忠良」が提供するセミナー一覧はこちら! 自動車の歴史は、内燃機関の進化とともに歩んできました... -
SDV に代表されるプロダクトの「ソフトウェア化」に対応するための基本方針
【目次】 前回の「SDV 時代における旧来のソフトウェア開発からの脱却と競争優位性確立のための戦略」は、「ソフトウェア定義型自動車... -
SDV(ソフトウェア定義型自動車)時代における旧来のソフトウェア開発からの脱却と競争優位性確立のための戦略
【目次】 自動車業界は電動化、ソフトウェア化、中国躍進、関税など、大きな変革期にあります。中でも「ソフトウェ...