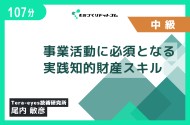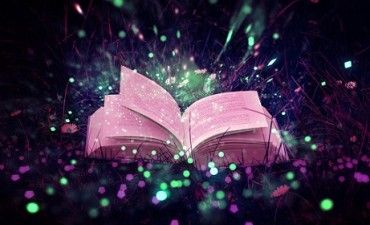他社特許をどのように打ち破り、自社に絶対優位な
特許網を構築するか? そのノウハウを伝授します!
セミナープログラム
<10:00〜11:30>
【第1部】 事業を強化する知財/特許戦略と特許網の形成
中澤経営知財パートナー 代表 中澤 俊彦 氏
【講演趣旨】
第4次産業革命など社会環境が大きく変化する中、企業 に求められる製品やサービスも大きく変化しており、その中で安定し て事業運営する為に知的財産の役割は益々大きくなっている。このよ うな時代の中で、事業の状況および周辺の環境に応じて、その企業 にとって有効な知的財産活動をどのような点に重点を置いてしていけ ば良いのかについて考察したいと考える。ビジネスモデルを活かすい くつかの特許網の事例についても紹介したい。
【講演項目】
1.事業活動と知財/特許戦略
1.1 三位一体の知財戦略の重要性
2.知的財産の経営上の役割
2.1 守りの特許
2.2 攻めの特許
2.3 ビジネスモデルを実現・維持・発展させる役割
3.群としての特許網形成
4.川上・川下を意識した特許網形成
5.商品、サービス形態を意識した特許網形成
6.特許マップ
7.知財ミックスの活用
8.ビジネスモデルを活かす特許網、知財ミックスの活用事例
9.その他
<12:15〜13:45>
【第2部】知財戦略と特許網構築の取り組み(ダイセルの事例)
元・(株)ダイセル 百瀬 隆氏
【講演趣旨】
企業においては、事業発展のために知的財産をどのように蓄積し、活用してくのか、その方向性を決めるための知財戦略が重要となっている。本講演においては、知財戦略の重要性について解説すると共に、その知財戦略に基づき、事業部門・研究開発部門・知財部門による三位一体の知財活動をどのよう進めていくのか、その具体的なプロセスについて説明する。そして、知財活動を通して、具体的に特許網構がどのように構築されるのかその実例を紹介すると共に、知的財産を蓄積する上での今後の課題について述べたい。
【講演項目】
1.はじめに
2.知財戦略の考え方について
3.三位一体の知財活動の重要性について
4.三位一体の知財活動の実例(ダイセルの事例)
5.特許網構築の実例(ダイセルの実例)
6.知的財産を蓄積する上での今後の課題について
<14:00〜15:30>
【第3部】シスメックスの知財戦略と特許網構築の取り組み
シスメックス(株) 井上 二三夫氏
【講演趣旨】
発明の実施形態に関する単一の特許のみではなく、第 三者が実施てくるであろう改良案(回避案)までも包含する複数の 特許(特許網)により、自社製品・事業を保護することがさまざま議 論され、また、紹介されている。特許網をうまく活用すれば、一定の 効果が期待できるかもしれないが、投資対効果の観点で考えると、 盲目的な特許網作成は、自社の競争力強化よりも、貴重な企業リ ソースの浪費につながる虞もある。特許件数をむやみに競う時代は 終わり、昨今は、最小の投資で最大の効果を得ることが企業の知財 マネジメントに要求される。この講演では、特許網の考え方を含む シスメックスの知財戦略を紹介する。
【講演項目】
1.特許出願の目的
2.特許網の有効性について
3.特許出願と出願コストについて
4.特許出願の効果について
<15:45〜17:15>
【第4部】オムロンの知財戦略と特許網構築の取り組み
オムロン(株) 金本 径卓氏
【講演趣旨】
社会課題解決のために長期的視点で特許を戦略的に出願、権利化し、その知的財産を活用して競争優位性を
構築することの重要性が益々大きくなってきている。当社では、企業理念に基づき、知的財産部門のミッション・ ビジョンを定め、三位一体の知財活動を行っている。本講演では、当社の知財戦略、ならびに、知財戦略を遂行する ための知財活動について述べる。特許網構築の考え方だけでなく、知財戦略実行上の課題に対する組織的な対応を 含め、企業内での知財戦略の実践のヒントとなるよう当社の活動事例を紹介する。
【講演項目】
1.会社紹介
2.知的財産センタの役割
3.知財戦略の位置づけ
4.特許網構築活動の事例
5.知財戦略実行に向けた体制構築
6.風土醸成
セミナー講師
1.中澤経営知財パートナー 代表 中澤 俊彦 氏
(元・キヤノン(株) 理事 知的財産法務本部 副本部長)
2. 元・(株)ダイセル 知的財産センター長 百瀬 隆氏
3. シスメックス(株) 知的財産本部 理事・本部長 井上 二三夫 氏
4. オムロン(株) 知的財産センタ 技術推進課 金本 径卓氏
セミナー受講料
1名につき60,000円(消費税抜き、昼食、資料付)
〔1社2名以上同時申込の場合1名につき55,000円(税抜)〕
主催者
開催場所
東京都
キーワード
※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です
開催日時
10:00 ~
受講料
66,000円(税込)/人
※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます
※銀行振込、会場での支払い
※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です
開催日時
10:00 ~
受講料
66,000円(税込)/人
※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます
※銀行振込、会場での支払い
類似セミナー
-
 2026/02/06(金)
10:30 ~ 16:30
2026/02/06(金)
10:30 ~ 16:30パテントマップを用いた知財戦略の策定方法-自社が勝つパテントマップ作成とそれを活用した開発戦略・知財戦略の実践方法--知的財産権業務にChatGPTを活用した事例紹介-<東京会場/オンライン受講選択可>
 会場受講の方:会場アクセス [東京・大井町]きゅりあん 4階研修室
会場受講の方:会場アクセス [東京・大井町]きゅりあん 4階研修室
-
 2026/02/17(火)
13:00 ~ 16:30
2026/02/17(火)
13:00 ~ 16:30成功する新規事業に欠かせない「尖った仮説」を立てるための特許情報の活用~特許調査の考え方・方法から、企業事例から学ぶ事業戦略への活かし方~<会場受講>
 [東京・大井町]きゅりあん 6階中会議室
[東京・大井町]きゅりあん 6階中会議室
関連セミナー
もっと見る-
 2026/02/06(金)
10:30 ~ 16:30
2026/02/06(金)
10:30 ~ 16:30パテントマップを用いた知財戦略の策定方法-自社が勝つパテントマップ作成とそれを活用した開発戦略・知財戦略の実践方法--知的財産権業務にChatGPTを活用した事例紹介-<東京会場/オンライン受講選択可>
 会場受講の方:会場アクセス [東京・大井町]きゅりあん 4階研修室
会場受講の方:会場アクセス [東京・大井町]きゅりあん 4階研修室
関連記事
もっと見る-
AIによる知財戦略はどこまで進化する?分析の高度化と未来像
【目次】 「競合他社の特許出願状況を、もっと早く正確に把握できないか?」 「膨大な技術文献から、自社の次の研究開発テーマのヒン... -
生成AIで知財が変わる!企業成長を加速する戦略的活用術とは
【目次】 近年、技術革新の波はかつてない速さで押し寄せ、ビジネス環境を大きく変容させています。その中でも特に注目を集めるのが、生成A... -
パーパス経営とは?社員を惹きつけ、顧客を繋ぐパーパス経営をわかりやすく解説
【目次】 現代のビジネス環境は、目まぐるしい変化の渦中にあります。テクノロジーの進化、社会課題の複雑化、そして人々の価値観の多様化は... -