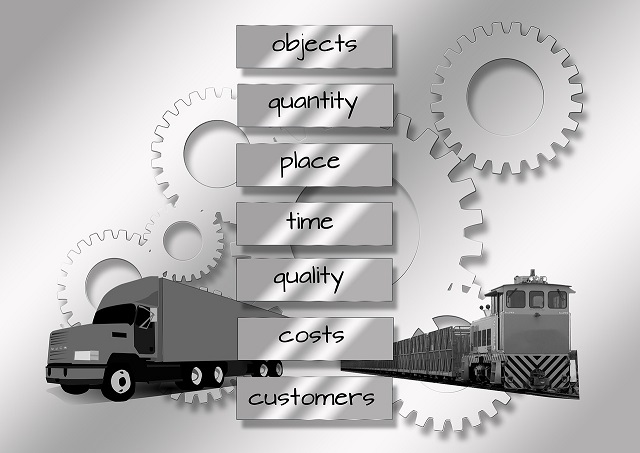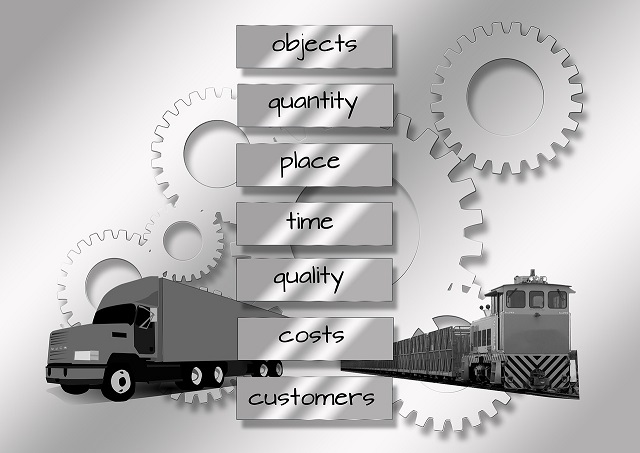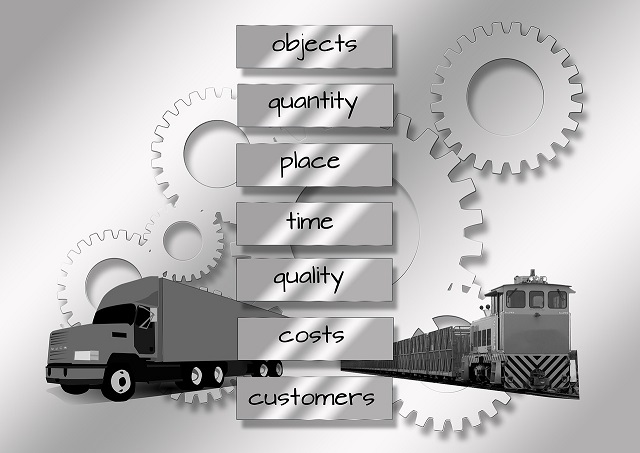1. サプライチェーンマネジメントのための組織論
誰しも長年生きていますと自分のライフスタイルというものが決まってきます。それと違うことをやろうとすると、何となく違和感を感じたり、場合によっては抵抗感すら感じたりすることがあると思います。これはビジネスにおいても同様ではないでしょうか。業界によって、あるいは会社によってビジネススタイルが確立されていて、それを変えることに大きな力が必要となります。
進化論でも時代の変化に対応できたものだけが生き残ると言われています。この言葉は、私たちが携わる物流の仕事にもそっくりそのまま当てはまると思います。ある製造会社に他業種から転職してきた人がいました。その人が就いたポジションは物流部の部長でした。今まで物流の仕事は全くやったことがなかったため、試行錯誤の連続でした。
その人とたまたま話をする機会があったのですが、その会社の物流戦略を聞いて驚きました。それはまさに今後のグローバル化を見据え、サプライチェーンマネジメントを行っていくための組織論と仕事のスタイルが網羅されていたのです。なぜ、物流の素人の方がここまで踏み込んだ考え方を確立できたのか、それは素人の素直な発想があったからだと考えました。
今まで会社はこういうやり方をしてきたからとか、物流とはこういったものだと言った、半ば誤った認識が会社の進化を阻みます。この物流部長さんにはこのような「余計な常識」と呼ばれる非常識が頭の中になかったのです。だからこそ、本当のサプライチェーンマネジメント論を頭の中で展開できたのでしょう。案の定、会社内の仲間からは素直に受け入れてもらえません。しかし、これからじっくりと時間をかけて説得していくとのことでした。
一つの例を挙げると、物流倉庫の仕事に波動があり、作業者に繁閑の差が出ていたそうです。それを解消するために作業者の技能向上を図り、徐々にできる仕事の幅を広げていく動きをしようとしたそうです。しかし昔からいる人たちにはそういった発想がないため、その説得に苦労したそうです。
2. 物流改革の要点
もう一つの例を挙げてみます。その物流部長さんの物流会社の活用方法は、
4PLを活用したいという発想でした。もちろん彼は4PLという言葉すら知りません。しかし、会社の物流マネジメント機能を外注化し、そこに実物流オペレーション会社もマネジメントさせようという考え方だったのです。
本来の効率的な物流を実施しようとすれば、こういった外部の知恵を借りて行っていくという考え方に行きつくことも十分理解できます。素直に考えれば、このような発想になると思います。しかし、大半の会社でそこまで発想が及ばず、とりあえず輸送改善だとか、物流支払費削減だとか言った、ミクロの領域にとらわれがちだと思います。つまりここでも今までの蓄積である固定観念が悪さをしていると考えられるのです。
改善を行っていく際に「今が最低だと思え」という教えがあります。この背景には改善は永遠であり、現状に満足するな、という思いが込められているのです。以前にも書かせていただきましたが、人は今いる位置がベストであり、そこから離れることに抵抗感を抱くものです。その組織に入ってしばらくたつと慣れが出てきます。しかし、世の中は常に変化していますから、自分たちがじっとしている間に周りが変化してしまうのです。
私たちはこの慣れの世界からは距離を置く必要があります。例の物流部長さんはその会社のよい所は是認しながらも、物流については改革していこうという姿勢があり、非常に好感が持てました。会社もそういった別の視点にも謙虚に耳を傾け、常に進化をしていくことが求められるのです。物流を物流という単なる点ではなく、サプライチェーンという線で見ていくことが必要なのです。
3. 物流倉庫の生産性
メーカーでは物流管理業務はノンコア業務という位置づけとなる可能性が高く、できればその仕事を外転化したいと考えています。自社の物流については自社で管理せよ、という理屈はあるかもしれませんが、これもまた固定観念と言えるかも知れません。顧客の本質をつかむことが大切です。これはむしろビジネスチャンスを考えるべきなのでしょう。顧客が物流管理業をやって欲しいと言うのであれば、それを受注して
4PL業務の一部と考えてみてはいかがでしょうか。
物流を本業としない会社では、物流スタッフを育てることに投資するよりも、その業務自体をアウトソースしてしまうことが早いのかもしれません。また、ある会社から物流倉庫...