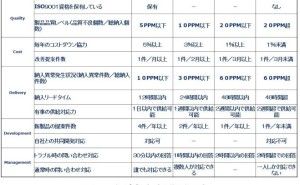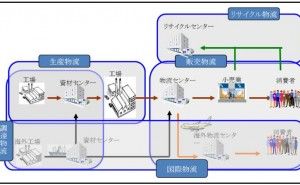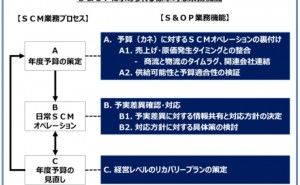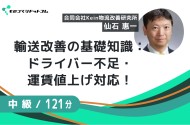◆低価格での物流取引
私たちがビジネスを実施していくうえで、協力会社の存在は欠かせないもです。協力会社とは常に連携を取り合って、効果的な取引をしていきたいものです。荷主会社であれば物流事業者は協力会社という位置づけになります。物流事業者にとって下請会社が協力会社ということになります。
今に始まったことではありませんが、物流事業者から出てくる声として、「荷主が適正価格を払ってくれない」というものがあります。
この適正価格ですが、価格は市場で決まりますので原則として今の価格が適正だということになります。しかし前記の「適正価格」とはそういう意味ではなく、事業を運営していくにあたり一定の利益が出る水準を意図していると思われます。そして従業員の給与向上など福利厚生面での改善要素も含んでいることが望まれます。
あくまで価格を決める際には相対で決めますので、納得できない価格であればビジネスが成立していないはずですが、そうは言っても、ということが実際のビジネスでは大いにありうるところです。一番多いのが荷主(実際の荷物の保有者と物流事業の親会社両方)からこの価格でないと発注しない、と言われた時の判断です。
つまり仕事を失うことを恐れ、利益が出ない水準で受注してしまうことです。荷主が強要することはないとは思いますが、それに近い行為が行われていたとしたら低価格での受注はありうることでしょう。特にどこでもできるような仕事であればあるほど、価格は低い水準で決定します。なぜならそういった類の仕事であれば、どこでもできるからです。
よく言われる「レッドオーシャン」です。下請法に抵触するような強要は論外ですが、少なくとも一定の付加価値が認められる、つまり荷主がお金を払ってでもや...