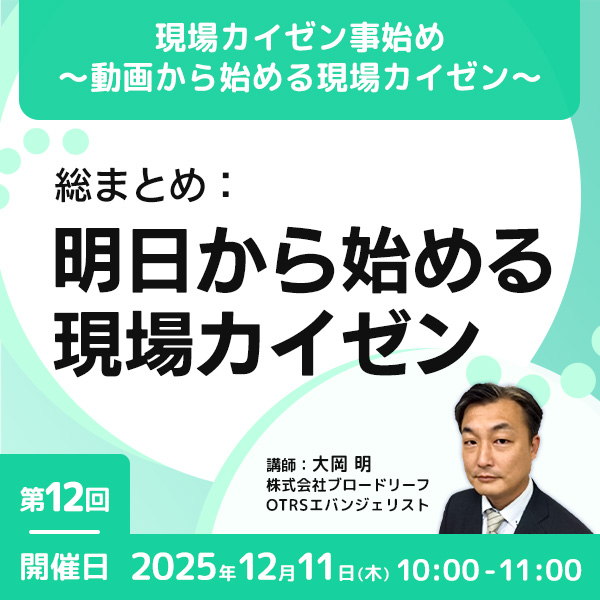生成AIの急速な進化や、あらゆるモノがネットに繋がるIoT社会の到来により、世界のデータ量は2年ごとに倍増するとも言われています。この「データ爆発」時代において、従来の電気配線は通信速度や消費電力の面で限界に達しつつあります。この深刻なボトルネックを解消する切り札として、今まさに「光インターコネクト」技術が注目を集めています。従来の電気信号による接続では、伝送距離や速度、消費電力において限界が見え始めています。そこで注目されているのが、光信号を利用した光インターコネクトです。光インターコネクトは、データセンターの巨大なサーバー群から、私たちの身近なPC内部のチップ間接続まで、あらゆるレベルでデータ伝送のボトルネックを解消し、情報社会のさらなる発展を支える基幹技術として期待されています。
1. 光インターコネクトとは何か?
光インターコネクトとは、情報伝送に電気信号ではなく光信号を用いる技術の総称です。従来の電気配線では、信号を伝送する際に抵抗による発熱や信号の減衰が発生し、特に長距離伝送や高速化においては大きな課題となっていました。また、信号間の干渉(クロストーク)も問題となり、密集した配線では安定した通信が困難でした。これに対し、光インターコネクトは光ファイバーや光導波路を介して光信号としてデータを伝送するため、これらの課題を克服できます。
光は電気信号に比べて伝送損失が極めて少なく、ギガビット/秒からテラビット/秒といった超高速なデータ転送が可能です。さらに、複数の波長の光を同時に利用する波長分割多重(WDM)技術を用いることで、1本の光ファイバーで大容量のデータを並列に送ることができ、大幅な伝送容量の拡大を実現します。これにより、データセンター内のサーバー間接続や、スーパーコンピューターにおけるプロセッサ間通信、さらにはCPUやメモリといったチップ内部の接続においても、飛躍的な性能向上が見込まれています。
【光インターコネクトと光通信の違い】
しばしば混同されがちですが「光インターコネクト」は比較的短距離(筐体内、ボード上、データセンター内など)の接続を主眼に置くのに対し「光通信」は主に長距離(都市間、国際間など)の通信を指す場合に用いられることが多いです。本記事で扱う光インターコネクトは、コンピューターの性能に直結する、より内部の接続に関する技術です。
2. 光インターコネクトの主要技術要素
光インターコネクトを実現するためには、いくつかの重要な技術要素が不可欠です。まず、電気信号を光信号に変換し、また光信号を電気信号に戻すための光電変換デバイスが挙げられます。具体的には、光を発するレーザーダイオードや発光ダイオード(LED)、そして光を電気信号に変換するフォトダイオードがその役割を担います。これらのデバイスは、高速な応答性と高い変換効率が求められます。
光信号を伝送するための媒体として、光ファイバーや光導波路があります。光ファイバーは長距離伝送に優れ、データセンター間の接続などに用いられます。一方、チップ内部やボードレベルの短距離接続には、シリコンなどの基板上に形成された光導波路が利用されます。これにより、電気配線では難しかった密集した配線パターンでも光信号を効率的に伝送できます。さらに、光信号のON/OFFを高速に切り替える光変調器も重要な要素です。電気信号の情報を光信号に乗せるためのデバイスであり、高速なデータ転送には欠かせません。これらの技術要素が高度に統合されることで、信頼性と効...

生成AIの急速な進化や、あらゆるモノがネットに繋がるIoT社会の到来により、世界のデータ量は2年ごとに倍増するとも言われています。この「データ爆発」時代において、従来の電気配線は通信速度や消費電力の面で限界に達しつつあります。この深刻なボトルネックを解消する切り札として、今まさに「光インターコネクト」技術が注目を集めています。従来の電気信号による接続では、伝送距離や速度、消費電力において限界が見え始めています。そこで注目されているのが、光信号を利用した光インターコネクトです。光インターコネクトは、データセンターの巨大なサーバー群から、私たちの身近なPC内部のチップ間接続まで、あらゆるレベルでデータ伝送のボトルネックを解消し、情報社会のさらなる発展を支える基幹技術として期待されています。
1. 光インターコネクトとは何か?
光インターコネクトとは、情報伝送に電気信号ではなく光信号を用いる技術の総称です。従来の電気配線では、信号を伝送する際に抵抗による発熱や信号の減衰が発生し、特に長距離伝送や高速化においては大きな課題となっていました。また、信号間の干渉(クロストーク)も問題となり、密集した配線では安定した通信が困難でした。これに対し、光インターコネクトは光ファイバーや光導波路を介して光信号としてデータを伝送するため、これらの課題を克服できます。
光は電気信号に比べて伝送損失が極めて少なく、ギガビット/秒からテラビット/秒といった超高速なデータ転送が可能です。さらに、複数の波長の光を同時に利用する波長分割多重(WDM)技術を用いることで、1本の光ファイバーで大容量のデータを並列に送ることができ、大幅な伝送容量の拡大を実現します。これにより、データセンター内のサーバー間接続や、スーパーコンピューターにおけるプロセッサ間通信、さらにはCPUやメモリといったチップ内部の接続においても、飛躍的な性能向上が見込まれています。
【光インターコネクトと光通信の違い】
しばしば混同されがちですが「光インターコネクト」は比較的短距離(筐体内、ボード上、データセンター内など)の接続を主眼に置くのに対し「光通信」は主に長距離(都市間、国際間など)の通信を指す場合に用いられることが多いです。本記事で扱う光インターコネクトは、コンピューターの性能に直結する、より内部の接続に関する技術です。
2. 光インターコネクトの主要技術要素
光インターコネクトを実現するためには、いくつかの重要な技術要素が不可欠です。まず、電気信号を光信号に変換し、また光信号を電気信号に戻すための光電変換デバイスが挙げられます。具体的には、光を発するレーザーダイオードや発光ダイオード(LED)、そして光を電気信号に変換するフォトダイオードがその役割を担います。これらのデバイスは、高速な応答性と高い変換効率が求められます。
光信号を伝送するための媒体として、光ファイバーや光導波路があります。光ファイバーは長距離伝送に優れ、データセンター間の接続などに用いられます。一方、チップ内部やボードレベルの短距離接続には、シリコンなどの基板上に形成された光導波路が利用されます。これにより、電気配線では難しかった密集した配線パターンでも光信号を効率的に伝送できます。さらに、光信号のON/OFFを高速に切り替える光変調器も重要な要素です。電気信号の情報を光信号に乗せるためのデバイスであり、高速なデータ転送には欠かせません。これらの技術要素が高度に統合されることで、信頼性と効率性の高い光インターコネクトシステムが構築されます。
3. データセンターにおける光インターコネクトの活用
データセンターは、クラウドサービスやWebアプリケーション、ビッグデータ分析など、現代のデジタル社会を支える心臓部です。ここには数多くのサーバー、ストレージ、ネットワーク機器が集積されており、その間を大量のデータが行き交います。従来のデータセンターでは、これらの機器間接続に銅線を用いた電気ケーブルが使用されていましたが、データ量の増加と高速化の要求に伴い、消費電力の増大、ケーブルの太さによるスペースの制約、そして伝送距離と速度の限界という問題が顕在化しました。
例えば、データセンター内でサーバーラック同士を繋ぐネットワークでは、400GbE(ギガビットイーサネット)や800GbEといった超高速な光トランシーバーが標準的に使用されています。これにより、膨大なデータを扱うAIの学習やビッグデータ解析の基盤が支えられています。将来的には、サーバー内のCPUやGPUと光I/Oチップを同一パッケージ上に実装するCPO(Co-Packaged Optics)技術の導入が進むことで、消費電力を劇的に削減しつつ、さらなる帯域幅の向上が期待されています。
4. スーパーコンピューターにおける光インターコネクトの活用
スーパーコンピューターは、科学技術計算、気象予測、シミュレーション、AI研究など、膨大な計算能力を必要とする分野で活用されています。その性能は、数千から数万に及ぶプロセッサ(CPUやGPU)がどれだけ高速に連携できるかに大きく依存します。プロセッサ間のデータ転送量が飛躍的に増加するにつれて、従来の電気配線によるインターコネクトでは、データ転送のボトルネックが深刻化し、スーパーコンピューター全体の性能を制限する要因となっていました。例えば、理化学研究所のスーパーコンピューター「富岳」においても、ノード間接続に光インターコネクト(毎秒25ギガバイト×2レーンの広帯域)が採用されており、その超高速な計算性能を支える根幹技術となっています。また、NVIDIAが開発したAIスーパーコンピューターでは、GPU間を高速に接続する「NVLink」にも光接続技術が応用されており、大規模言語モデル(LLM)などの並列計算処理を効率化しています。
そこで、光インターコネクトがスーパーコンピューターの性能を飛躍的に向上させる鍵として注目されています。プロセッサ同士を結ぶネットワークに光ファイバーや光導波路を用いることで、超高速かつ大容量のデータ転送が可能となり、計算ノード間の通信遅延を大幅に削減できます。これにより、並列処理の効率が向上し、より複雑で大規模な計算を高速に実行できるようになります。例えば、複数のノードを結合するネットワークインターフェースカード(NIC)に光トランシーバーが搭載されたり、さらにはプロセッサのパッケージ内に光電変換素子を組み込むことで、より短距離での光接続が実現され始めています。光インターコネクトは、次世代スーパーコンピューターの高性能化に不可欠な技術として、その進化を牽引しています。
5. チップ間接続における光インターコネクトの活用
データセンターやスーパーコンピューターだけでなく、より微細なレベル、つまりプリント基板上のチップ間や、さらにはチップ内部における接続においても、光インターコネクトの導入が進んでいます。現代のCPUやGPU、メモリといった半導体チップは、その性能向上のために、より多くのコアを搭載し、より高速なデータ処理が求められています。これに伴い、チップ間の電気配線は、信号の減衰、クロストーク、電力消費、そして配線密度の限界という課題に直面しています。特に、メモリとプロセッサ間の広帯域化は、システム全体の性能を決定する重要な要素です。光インターコネクトは、これらの課題を解決する強力な手段となります。
シリコンフォトニクスと呼ばれる技術は、Intel社やGlobalFoundries社などがこのシリコンフォトニクス技術の開発をリードしており、すでにデータセンター向けの光トランシーバーなどで実用化が進んでいます。これにより、チップとチップの間を光信号で直接接続したりさらにはチップ内部の異なるブロック間を光で結ぶことも検討されています。チップレベルでの光インターコネクトの実現は、データの高速移動を可能にし、消費電力を削減するとともに、これまで電気配線が物理的な制約となっていた設計の自由度を大幅に高めることで、次世代の高性能プロセッサやAIチップの登場を加速させると期待されています。
6. 光インターコネクトの課題と将来展望
光インターコネクトは非常に有望な技術ですが、実用化と普及に向けてはいくつかの課題も存在します。まず、コストが挙げられます。電気配線と比較して、光インターコネクトの部品や製造プロセスはまだ高価な傾向にあります。特に、チップレベルでの集積化を進めるためには、量産技術の確立とコスト削減が不可欠です。次に、集積化と小型化も重要な課題です。光電変換デバイスや光変調器などの光部品を、電気回路と同様に微細かつ高密度に集積する技術のさらなる発展が求められます。また、光と電気の変換効率や、光信号の損失をいかに低減させるかといった性能の最適化も継続的な研究開発が必要です。さらに、光信号は物理的な衝撃や曲げに弱いため、信頼性と堅牢性の確保も重要な検討事項となります。
しかし、これらの課題を克服するための研究開発が世界中で活発に進められています。シリコンフォトニクス技術の進化は、光インターコネクトの集積化と低コスト化を大きく推進します。加えて、NTTが提唱する「IOWN(アイオン)構想」のように、ネットワークから端末まで、あらゆる処理を光ベースで行う「オールフォトニクス・ネットワーク」の実現に向けた壮大なプロジェクトも始まっています。将来的には、データセンターから、スーパーコンピューター、さらには一般消費者向けのPCやスマートフォン内部に至るまで、あらゆるレベルで光インターコネクトが標準技術となる可能性がありますこれにより、現在のコンピューティングのボトルネックが解消され、より高速で、より低消費電力な情報処理環境が実現し、AI、IoT、VR/ARといった新たな技術の進化をさらに加速させるでしょう。
7. まとめ
【光インターコネクト市場の動向と主要プレイヤー】
光インターコネクトの市場は、データ通信量の爆発的な増加を背景に、急速な成長が見込まれています。この市場を牽引しているのは、以下のような企業です。
- 通信機器ベンダー・・・・・ Cisco, Broadcom, Marvell Technology
- 半導体メーカー・・・・・・ Intel, GlobalFoundries
- プラットフォーマー・・・・ NVIDIA, Google, Meta (各社が独自設計や導入を推進)
このように、業界の垣根を越えた多くの企業が研究開発にしのぎを削っており、技術革新とコスト競争が今後さらに加速していくと考えられます。
光インターコネクトは、現代のデジタル社会におけるデータ通信の進化を支える上で不可欠な技術です。従来の電気信号によるデータ伝送が抱える限界を、光信号の特性を活かすことで克服し、超高速、大容量、低消費電力な通信を実現します。データセンターにおける膨大なデータの処理から、スーパーコンピューターの計算能力の最大化、さらにはCPUやメモリといったチップ内部の接続に至るまで、その活用範囲は広がり続けています。シリコンフォトニクスに代表される技術革新により、光インターコネクトの集積化とコスト削減が進められており、将来的にはあらゆる情報機器に光が届く「光コンピューティング」の時代が到来するかもしれません。課題は残されているものの、その可能性は計り知れず、今後も私たちの情報社会の発展を強力に牽引していくことでしょう。
◆関連解説記事<シリコンフォトニクスとは?フォトニクス技術の特徴や市場動向について解説>