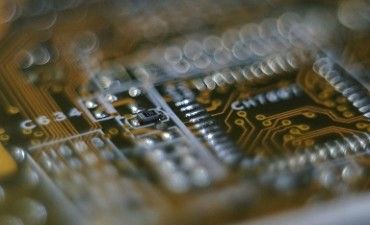![[入門者OK]<br/>この分野の初歩から説明します 初心者向けセミナーです](https://assets.monodukuri.com/img/beginner-mark.png?d=0x0) さらなる低コスト化を実現する銅微粒子・ナノ粒子の合成・高機能化と濃厚分散制御
さらなる低コスト化を実現する銅微粒子・ナノ粒子の合成・高機能化と濃厚分散制御
導電性材料によく使われる
銅微粒子・ナノ粒子の合成と応用について学びます!
両粒子の分散を制御、粒子径を揃え酸化させない!
表面吸着物をどう評価したらいい?etc…
セミナー趣旨
今回は、金属ナノ粒子・微粒子のうち、導電性材料によく使われようとされる銅微粒子・ナノ粒子の合成と応用について理解する1日コースです。これまでの研究成果を十分にわかりやすく皆様にご紹介します。化学法・凝集法を中心にその合成法、サイズや形状の制御に関する考え方と実践、さらに、得られたナノ粒子の表面、表面吸着物、酸化膜の微細構造の解析について紹介します。さらに、低温焼結用の銅微粒子とその低温焼結メカニズム、さらには低融点でこちらも低温焼結に優れた特性をもつスズについても今回は新しく触れたいと考えています。また、これらの濃厚分散系の構築が微粒子利用のために重要となると考えており、濃厚微粒子分散系の構築に関する当研究室の考え方をお話しします。当研究室独自のナノ粒子に対する考え方について一緒に議論しましょう。
セミナープログラム
1.金属微粒子・ナノ粒子の化学的合成の基本
1-1 化学的に金属イオンを還元する
1-2 原料・添加剤を選ぶ
1-3 保護構造を知る、設計する
2.金属微粒子・ナノ粒子のその他の合成法
3.銅微粒子・ナノ粒子の化学的合成
3-1 どのように粒子径を揃えるか
3-2 どのように形を整えるか
3-3 酸化させない手法はどうするか
3-4 表面吸着物を評価する手法を知る
3-5 実用性に耐えられる銅微粒子とは
4.銅微粒子の精密な評価法
4-1 電子顕微鏡(TEM、SEM)による構造、形状評価
4-2 銅微粒子・ナノ粒子の表面微細構造評価
4-3 受入材の評価はどうすべきか
4-4 表面吸着物(有機物)の評価
4-5 ゼータ電位の重要性と必要性
4-6 銅系合金微粒子・ナノ粒子
5.銅微粒子・ナノ粒子のペースト・インクへの再分散の基礎
5-1 金属微粒子・ナノ粒子を安定に分散させるということ
5-2 銅微粒子・ナノ粒子インク・ペーストを考える
5-3 微粒子・ナノ粒子分散手法の代表例
5-4 銅微粒子・ナノ粒子を分散の分散安定性評価
5-5 得られたインク・ペーストの性能および長期評価をどうする?
5-6 安定な銅微粒子システムを作り上げる
6.銅を用いた低温焼成導電材料
6-1 銅微粒子インク・ペーストをよく観察する
6-2 焼成プログラムを考える
6-3 焼成挙動を観察する
6-4 低温で焼成させるためには
6-5 得られた被膜を検証する
6-6 基材との相性はどうする
6-7 スズナノ粒子系の新規性を考える
7.大学と企業との連携、実用化に直結する大学との共同研究
8.応用と将来
【質疑応答 名刺交換】
セミナー講師
北海道大学 大学院工学研究院 材料科学部門 教授
北海道大学 産学・地域協働推進機構 教授
博士(工学)(東京大学)米澤 徹 氏【専門】
ナノ粒子科学・電子顕微鏡学
【活動】
イギリス王立化学会フェロー (2016~)
北京大学訪問教授(2014)
チュラロンコン大学訪問教授(2016)
日本化学会 コロイドおよび界面化学部会 役員
日本化学会 新領域研究グループ「分散凝集の学理構築への科学と技術戦略」メンバー
ナノ学会 幹事
セミナー受講料
【1名の場合】44,000円(税込、テキスト費用を含む)
2名以上は一人につき、11,000円が加算されます。
主催者
開催場所
東京都