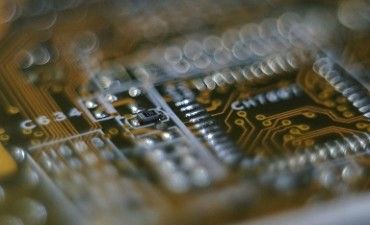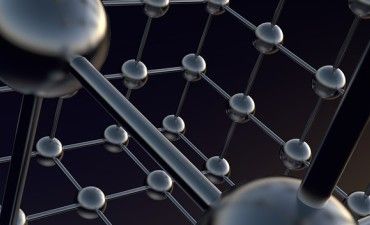自己修復性高分子材料の研究・開発動向および持続可能な社会の実現への期待【LIVE配信・WEBセミナー】
★2026年1月30日WEBでオンライン開講。大阪大学 原田氏、富山県立大学 納所氏、東京理科大学 古海氏、物質・材料研究機構 玉手氏が、【自己修復性高分子材料の研究・開発動向および持続可能な社会の実現への期待~マイクロカプセル・バイオマスを用いた自己修復材料、自己修復高分子ゲルの設計・開発~】について解説する講座です。
■注目ポイント
★自己修復研究の背景、歴史、経緯、原理にはじまり、マイクロカプセルを利用した自己修復メカニズムや炭素繊維強化高分子材料(CFRP)への適用事例、バイオマスを用いた自己修復材料の分子設計、イオンゲルに自己修復性・リサイクル性などの機能を付与する試みについて解説・紹介!
セミナー趣旨
【本セミナーの主題および状況・本講座の注目ポイント】
■本セミナーの主題および状況(講師より)
★近年、材料の自己修復に対して多大な関心が寄せられています。これはプラスチックス、セラミックス、ガラス、コンクリートなど、一度傷がついたらもとに戻らない、と考えられていた材料がもとに戻れば、材料の寿命が延び、環境への負担が軽減されるだけでなく、安全・安心につながるからであります。特にポリマー材料の自己修復に関しては、最近、多くの方法が考案され、実現されてきました。ポリマーを用いた自己修復に関しては水素結合やホストーゲスト相互作用、配位結合など可逆的な相互作用を利用した「化学的方法」が用いられており、切れてもつながる自己修復が可能になってきました。
★地球上の石油資源は残り約50年分の石油資源しか残されていないと試算されており、石油資源の枯渇問題は極めて深刻であります。今後、石油資源への依存から脱却して、バイオマスを有効活用して機能性材料を創り出すバイオマスリファイナリーの技術開発が急務であります。
★カチオンとアニオンのみから構成され、室温で液体となる常温溶融塩であるイオン液体は、高いイオン伝導性、不揮発性、不燃性、熱・電気化学的安定性など、従来の分子性液体にない優れた性質を示し、二次電池・キャパシタ・センサー・アクチュエータなどの電気化学デバイスへの応用が期待されます。
■注目ポイント
★マイクロカプセルを用いた自己修復CFRPの設計・評価事例を中心に数値シミュレーションによる材料設計や力学特性・自己修復効果改善の取り組みを紹介!
★バイオマスを用いた自己修復材料の分子設計、自己修復材料を用いたフォトニック材料の作製方法について解説!
★イオン液体およびイオン液体を溶媒とするゲル(イオンゲル)の基礎物性・応用事例、さらにイオンゲルに自己修復性・リサイクル性などの機能を付与する試みに関して概説・紹介!
習得できる知識
第1部
・自己修復研究の背景、歴史、経緯
・自己修復の原理(物理的自己修復、化学的自己修復)
・ポリマー材料の自己修復の方法
・自己修復材料の開発
・自己修復材料の応用
第2部
・マイクロカプセルを用いた自己修復高分子系複合材料の開発事例
・数値シミュレーションを活用した材料設計の考え方
第3部
バイオマスを用いた自己修復材料の分子設計、自己修復材料を用いたフォトニック材料の作製方法
第4部
イオン液体およびイオン液体と高分子からなるゲル材料(イオンゲル/イオノゲル)に関する基礎知識、自己修復高分子ゲルに関する最近の研究動向
セミナープログラム
【第1講】 ポリマーを用いた自己修復材料の研究開発動向とそのアプローチ【時間】 10:30-11:45
【講師】大阪大学 産業科学研究所 原田 明 氏
【講演主旨】
近年、材料の自己修復に対して多大な関心が寄せられている。これはプラスチックス、セラミックス、ガラス、コンクリートなど、一度傷がついたらもとに戻らない、と考えられていた材料がもとに戻れば、材料の寿命が延び、環境への負担が軽減されるだけでなく、安全・安心につながるからである。特にポリマー材料の自己修復に関しては、最近、多くの方法が考案され、実現されてきた。ポリマーを用いた自己修復に関しては水素結合やホストーゲスト相互作用、配位結合など可逆的な相互作用を利用した「化学的方法」が用いられており、切れてもつながる自己修復が可能になってきた。本講座では上記の自己修復の応用についても述べる。
【プログラム】
1. 自己修復とは
2. 生物の自己修復
3. 初期の自己修復に関する研究
4. 高分子材料の自己修復の方法
5. 非共有結合による自己修復
5-1 水素結合による自己修復
5-2 イオン結合による自己修復
5-3 ホストーゲスト相互作用による自己修復
5-4 配位結合を利用した自己修復
6. 動的共有結合による自己修復
6-1 Diels-Alder 反応による自己修復
6-2 動的ラジカル形成動的結合による自己修復
7. 外部刺激応答性自己修復
7-1 光応答性自己修復
7-2 酸化還元応答性自己修復
7-3 熱応答性自己修復
8.自己修復高分子材料の応用
【質疑応答】
【キーワード】
自己修復材料、プラスチックス、分子間相互作用、水素結合、ホストーゲスト相互作用、配位結合、物理的自己修復、化学的自己修復
【講演者のPRポイント】
講演者らは早くから高分子材料の自己修復について基礎研究から応用研究まで一貫した研究を行っており、世界で初めてホストーゲスト相互作用を用いた自己修復材料を発表し、社会実装まで実現した。
【第2講】 マイクロカプセルを用いた自己修復高分子系複合材料の開発事例
【時間】 12:45-14:00
【講師】富山県立大学 工学部機械システム工学科 / 助教 納所 泰華 氏
【講演主旨】
構造材料の信頼性向上を目指した、損傷を自ら修復する「自己修復高分子系複合材料」の研究事例をご紹介します。本講演では、マイクロカプセルを利用した自己修復メカニズムや炭素繊維強化高分子材料(CFRP)への適用事例を中心に、微視構造の最適化や損傷の可視化、数値シミュレーションを活用した材料設計についてお話しします。また、高熱伝導性高分子系複合材料への自己修復機能付与の取り組みについても取り上げ、マイクロカプセルを用いた自己修復高分子系複合材料の可能性を探ります。
【プログラム】
1.自己修復材料の背景
- 自己修復機能を付与する手法の紹介
- マイクロカプセルを利用した自己修復メカニズム
2.自己修復CFRPの課題と解決策の提案
- マイクロカプセル含有CFRPでの課題
- 開繊炭素繊維を活用した複合材料の提案
3.開繊炭素繊維を用いた自己修復CFRPの開発
- 微視構造の最適化
- 損傷の可視化
- 数値シミュレーションを用いた力学特性の予測
- 開繊炭素繊維と織物炭素繊維のハイブリッド化による特性改善
- 微小フィラー添加による特性改善
4.関連研究紹介と今後の展望
- 高熱伝導性高分子系複合材料への自己修復機能付与の試み
- 今後の展望
【質疑応答】
【キーワード】
高分子系複合材料、炭素繊維強化高分子材料(CFRP)、マイクロカプセル、自己修復
【講演のポイント】
マイクロカプセルを用いた自己修復CFRPの設計・評価事例を中心に、数値シミュレーションによる材料設計や力学特性・自己修復効果改善の取り組みを紹介します。また、高熱伝導性複合材料への自己修復機能付与の試みも取り上げます。
【第3講】 バイオマスを用いた自己修復材料の創製とフォトニクスへの応用
【時間】 14:10-15:25
【講師】東京理科大学 理学部第一部 応用化学科 / 教授 古海 誓一 氏
【講演主旨】
地球上の石油資源は残り約50年分の石油資源しか残されていないと試算されており、石油資源の枯渇問題は極めて深刻である。今後、石油資源への依存から脱却して、バイオマスを有効活用して機能性材料を創り出すバイオマスリファイナリーの技術開発が急務である。本講演では、地球上で最も多く存在するセルロースなどのバイオマスに着目して、新しいサステナブルな自己修復材料の創製とフォトニック材料への応用について解説する。これらバイオマスの自己修復材料は切断・損傷した状態から簡単に復元できるため、SDGsにおける”つくる責任 つかう責任”に貢献できる。
【プログラム】
1. はじめに
2. 動的共有結合を導入したバイオマス自己修復材料の創製
3. バイオマス自己修復材料のフォトニクスへの応用
4. まとめと将来展望
【質疑応答】
【キーワード】
バイオマス、セルロース、自己修復、動的共有結合、コレステリック液晶、ブラッグ反射、フォトニック材料
【講演のポイント】
本講演では、石油資源をなるべく使わずに、バイオマスの自己修復材料の創製と応用に関する研究であり、近年、クローズアップされている石油資源の枯渇問題と海洋マイクロプラスチックごみ問題の両方に貢献できる可能性があります。
【第4講】 自己修復性イオンゲルの設計とその自己修復挙動、特性
【時間】 15:35-16:50
【講師】物質・材料研究機構 高分子・バイオ材料研究センター / 主任研究員 玉手 亮多 氏
【講演主旨】
カチオンとアニオンのみから構成され、室温で液体となる常温溶融塩であるイオン液体は、高いイオン伝導性、不揮発性、不燃性、熱・電気化学的安定性など、従来の分子性液体にない優れた性質を示し、二次電池・キャパシタ・センサー・アクチュエータなどの電気化学デバイスへの応用が期待される。
本講演ではイオン液体の特性と応用、更に高分子とイオン液体の複合化により得られるソフトマテリアル「イオンゲル」に関して概説する。特に近年我々が開発した、化学的アプローチおよび物理的アプローチを利用した自己修復性を持った新しいイオンゲル材料を含めた、自己修復高分子材料、特に自己修復性イオンゲルの最新動向に関して詳細を解説する。
【プログラム】
1.イオン液体とは
1.1 イオン液体の性質
1.2 イオン液体の分類
1.3 イオン液体の応用
2.イオン液体と高分子の複合化によるソフトマテリアル創製
2.1 イオン液体中の高分子
2.2 イオンゲル
2.3 イオンゲルの高機能化
3.自己修復性イオンゲル
3.1 化学的アプローチを利用した自己修復性イオンゲル
3.2 物理的アプローチを利用した自己修復性イオンゲル
3.3 今後の展望
4.まとめ
【質疑応答】
【キーワード】
イオン液体、イオンゲル、イオノゲル、高分子ゲル、自己修復、高強度、フレキシブル、ウェアラブル
【講演のポイント】
イオン液体およびイオン液体を溶媒とするゲル(イオンゲル)の基礎物性・応用事例に関して概説する。さらに、イオンゲルに自己修復性・リサイクル性などの機能を付与する試みに関して紹介する。
セミナー講師
第1部 大阪大学 産業科学研究所 原田 明 氏
第2部 富山県立大学 工学部機械システム工学科 / 助教 納所 泰華 氏
第3部 東京理科大学 理学部第一部 応用化学科 / 教授 古海 誓一 氏
第4部 物質・材料研究機構 高分子・バイオ材料研究センター / 主任研究員 玉手 亮多 氏
セミナー受講料
【1名の場合】60,500円(税込、テキスト費用を含む)
2名以上は一人につき、16,500円が加算されます。
受講料
60,500円(税込)/人