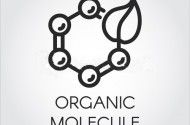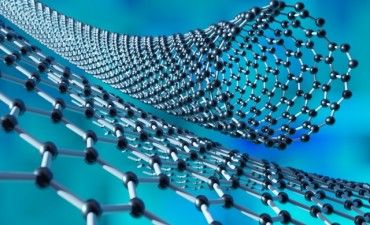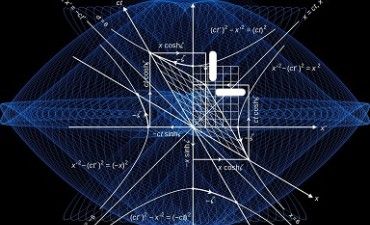製薬用水入門講座~水基礎から汚染防止と水質管理・査察対応までの実践情報【会場/WEB選択可】WEB受講の場合のみ:ライブ配信/アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可)
製薬用水はGMP対応や査察において最も重要な品質要素の一つです。純水と製薬用水の違い、精製水製造装置のしくみや汚染防止の最新知見、RMMを活用した水質管理、さらにNon distillation methodによるWFI製造の動向まで幅広く解説します。トラブル事例や査察対応の実践ノウハウも学べる特別セミナー!!
【会場/WEB選択可】WEB受講の場合のみ:ライブ配信/アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可)
セミナー趣旨
外部から来訪する第三者に対し、安全な製薬用水を製造現場へ連続給水していることを査察という機会に説明できる。この段階を講座聴講終了時の目標とします。
基礎編は製薬用水とは何?飲料水と純水はどこが異なるのか?製薬用水でのGMPは?不純物とは?
原水選択、導電率TOCは何を測定するのか?を学んで頂きます。
応用編は、精製水製造装置のしくみを理解して頂きます。第3章は、大事な精製水の微生物汚染防止の現状を点検し今なぜRMMによる水質可視化が求められるのか?へ進みます。第4章は、今なぜNon distillation methodがWFI製造に採用されるのか?この答えを注射用蒸留水と呼ばれた1980年代へ振り考察してゆきます。エンドキシンを使い蒸留器へチャレンジテストを行った結果についてもお話します。第5章は、外部査察の対応と自主管理、この一見相反する2つの視点の接点を探りつつ将来へ向けた査察対応へのヒントを幾つか提案します。
製造現場や品質管理現場での疑問をお持ち頂くか事前質問もお受けします。また、事後質問もお受けしています。
受講者の声
- 本日はありがとうございました。この度、製薬用水を用いる部署に新卒採用されました。その入門として、今回のセミナーに参加させていただきました。 わからないことが多く、戸惑うこともありましたが、セミナーを通して、注射用水やその基準、国内外での大きな違いがあることなどを学ぶことができ、注射用水製造の面白さを再確認することができました。また、査察対応では指摘があるより、ない方が取り組むべき目標がわからないとおっしゃっており、とても印象的でした。今後、査察時の状態を維持していくことや一般人=患者さん、わかりやすい結果を示していくということを心がけて業務を遂行していきたいと思います。
- 製薬用水関係の業務担当になってから半年で、まだまだ知識もない状況だったのですが、一から教えていただき少しずつですが理解を深めることができたと思います。教えていただいた知識を無駄にせず、日々の業務に取り組みたいと思いました。貴重な講演をありがとうございました。
- 自社の設備の用途の再確認や認識不足だった内容を補うことができ有意義な時間でした。各項目のポイントに加えて、講師の体験、意見を述べておられており、考え方やリスクに関する理解度が向上しました。
- セミナーありがとうございました。4月から新入社員として製薬用水設備に携わることになり自分の中であいまいだった原水からWFIを作る流れがよくわかりました。
- 私は約17年前にプラントにUF膜の設備を導入したことがあり、今回受講させて頂きました。いまは健康食品業界のなかで、蜂産品(プロポリスやローヤルゼリー等)を手掛けており、何かつながることはないかと考えながら受講させて頂きました。ありがとうございました。
受講対象・レベル
医薬品・医療機器・化粧品・健康食品を製造する業種
膜メーカー・蒸留器メーカー・測定器メーカー
製薬会社へ係わるゼネコン・エンジアリング会社・プラントメーカー など
必要な予備知識
特に必要ありません。
習得できる知識
1)製薬用水の一般基礎事項
2)製造装置のしくみと汚染箇所
3)用途に適した装置選択を考えるヒント集
4)近い将来に自主的な管理へ移行するヒント集
5)将来疑問が生じたときの相談相手が得られる など
セミナープログラム
Prologue
第1章 製薬用水の基礎編
1.純水と製薬用水
2.何が不純物なのか
3.パイロジェンとエンドトキシン
4.薬局方に定められる製薬用水
5.導電率・TOCを管理するねらいは何?
第2章 精製水をつくる 応用編
1.イオン交換塔のしくみ
2.ROのしくみ
3.EDIのしくみ
4.精製水貯槽と配管
第3章 微生物汚染について 応用編 ~今なぜRMMによる水質可視化が求められるのか?~
1.センセーショナルな異物混入事故から
2.デッドレグ基準制定とその背景
3.前処理装置・精製水装置内での汚染発生とその対処
第4章 WFI製造法新しい流れ 情報編~今なぜNon distillation methodなのか?~
1.蒸留法のしくみ
2.エンドトキシンチャレンジテスト結果
3.膜WFIのしくみ
4.蒸留水とUF水の水質比較
第5章 外部査察時へ対応 ヒント編 ~査察官が帰った後も現状維持を示す策は?~
1.同条件で1週間中POUに通水するには
2.装置が同条件で稼働しているか
3.検査方法が信頼できるか
4.データが信頼できるか
5.自主管理体制つくりがベースとなる
まとめ・質疑
まとめ
当日質問タイム
※なお事前質問も歓迎します。(できますれば開催の1週間前までに事務局へご提出ください)
なお、参加者はセミナー後1年間ご質問ご相談を受け付けます。
セミナー講師
布目技術士事務所 製薬用水コンサルタント 布目 温 先生
技術士(衛生工学部門:水質管理)
栗田工業,野村マイクロ・サイエンスを経て現在に至る
1972年に栗田工業入社
1992年に野村マイクロ・サイエンスに入社
2011年に布目技術士事務所を神奈川県大磯町に開き現在に至る。
PHARM TECH JAPAN誌・クリーンテクノロジー誌・レギュラトリーサイエンス誌・GMP Platformに、
1995年~2025年に渡り、WFI製造・精製水微生物汚染防止、製薬用水のTOC測定、膜WFI、
RMMについての執筆を継続している。また、日本PDA学会&膜分離技術振興協会へはOB会員として、
後進の指導にも当たっている。
セミナー受講料
(消費税率10%込)1名:49,500円 同一セミナー同一企業同時複数人数申込みの場合 1名:44,000円
※WEB受講の場合、別途テキストの送付先1件につき、配送料1,210円(内税)を頂戴します。
テキスト:製本資料(受講料に含む)
受講料
49,500円(税込)/人