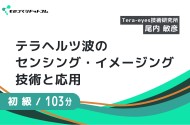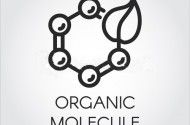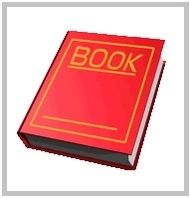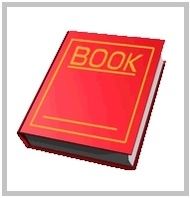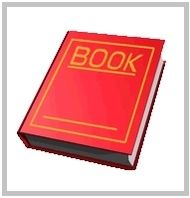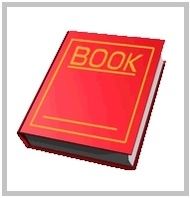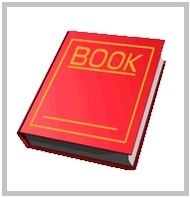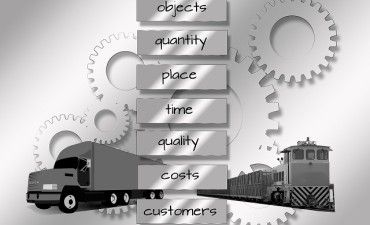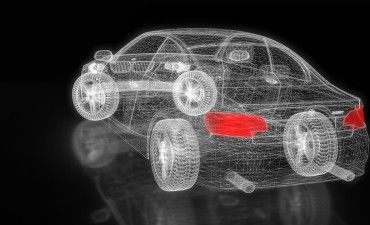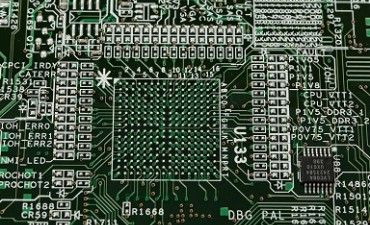★ 定期点検、目視点検では見えない内部の劣化状態!
天井落下、道路陥没など重大な事故を未然に防ぐための分析技術、対策を詳解!
セミナープログラム
【10:30-12:00】
1.近赤外分光を用いたコンクリートの非破壊診断
●講師 (国研)産業技術総合研究所 センシング技術研究部門 主任研究員 理学博士 渡部 愛理 氏
【習得できる知識】
・分光器基礎
・成分分析
・インフラモニタリングの必要性
・コンクリートの相組成分析
【講座の趣旨】
近赤外域の光を用いると、非破壊・非接触でコンクリート構造物の化学的な劣化を簡易診断することができます。分光はどんな技術で何に使えるのか、建設物のマネジメントの重要性などについて実験結果をもとに、分かりやすく説明します。
1.インフラモニタリング
1.1 インフラの長寿命化
1.2 劣化要因となる外来因子
1.2.1 塩害
1.2.2 炭酸化
1.2.3 硫酸劣化
1.2.4 アルカリ骨材反応
1.3 モニタリング技術について
2.分光による成分分析とは
2.1 特徴的な光吸収
2.2 光を分ける
2.3 分光器の種類
2.4 近赤外域について
2.4.1 原理
2.4.2 近赤外域での分光の特徴
3.高感度分光
3.1 分光器の種類
3.2 高感度な二光束干渉計とその利点
3.3 分解能向上の工夫
4.分光分析の事例
4.1 コンクリートの相組成分析について
4.2 近赤外域における解析の難しさ
4.3 確率論を用いた分析法
4.4 表面被覆剤の劣化
5.まとめ
【質疑応答】
【13:00-14:30】
2.誘導加熱技術を用いたIH式塗膜剥離装置の開発と適用事例
●講師 第一高周波工業(株) 新事業推進部 営業部 係長 田上 祥太 氏
【略歴】
2011年3月 九州工業大学大学院 生命体工学研究科 生体機能専攻 修了
2011年4月 第一高周波工業株式会社 入社
入社以来、誘導加熱技術を応用した研究開発及び誘導加熱装置の製造販売に従事
【習得できる知識】
誘導加熱を用いた塗膜剥離技術の概要とその展望
【講座の趣旨】
インフラの老朽化は人命にかわかる事故やライフラインの寸断といった深刻な問題を引き起こす。橋梁や送電鉄塔をはじめとした鋼構造物を安全に長期間使用する手段の一つとして、これらの構造物の金属腐食を抑制し、耐力を維持する事が非常に有効である。そのため定期的な塗装の塗り替えが簡便かつ効果的な手段であるが、この際の塗膜の剥離作業には多くの課題があり、具体的には工期短縮、環境および安全への配慮、廃棄物処理の煩雑さなどが挙げられる。
これらの課題を解決するために当社は誘導加熱(Induction Heating:IH)技術を使ったIH式塗膜剥離装置を開発し、実用化している。今回の講座ではその概要について詳しく解説する。
1.はじめに
2.インフラ老朽化問題と課題
3.塗膜剥離工法の種類と特長
4.誘導加熱式塗膜剥離工法の優位性
5.DHF製IH剥離装置の紹介
6.事例紹介
7.今後の展望とまとめ
8.おわりに
【質疑応答】
【14:45-16:15】
3.「四次元透視」が実現する未来のインフラ監視技術と陥没リスクの低減
●講師 東京大学 生産技術研究所 准教授 博士(工学) 水谷 司 氏
【略歴】
2007年東京大学工学部都市工学科卒業(首席),2009年東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻修士課程修了,2011年同専攻博士課程修了(短縮).博士(工学).2012年東京大学大学院工学系研究科助教,同年英国ケンブリッジ大学研究員を経て2019年より東京大学生産技術研究所准教授.東京大学工学部長賞,科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞,American Society of Civil Engineers(ASCE) Moisseiff Award, Elsevier “Engineering Structures Best paper of the Year 2024”
ほか多数受賞.2021年に東京大学卓越研究員,科学技術振興機構創発研究者に選出.
【習得できる知識】
地中レーダー(GPR)やLiDAR、AI解析を組み合わせて、道路や構造物の「内部」を非破壊で透視し、損傷の進行や空洞の形成といった陥没リスクをいかに早期に察知するかを理解できます。また、時系列データを重ねて劣化の進行を定量化する「四次元透視」技術の構造や、社会実装に向けた最新の取組(例:長野県千曲市での大規模計測)について学ぶことができます。
【講座の趣旨】
インフラ老朽化が進む中で、目視や打音による従来の点検手法には限界があり、内部劣化や空洞を可視化する新たな技術が求められています。本講演では、四次元透視技術を軸に、インフラの点検・保全をより予防的・効率的に進めるための技術的潮流を紹介します。AI解析や自動運転車との連携による国土規模での維持管理の未来像にも触れ、実践的かつ構想的な視点からその可能性を共有します。
1.社会インフラの老朽化と予防保全の重要性
1.1 全国で多発する陥没・崩落事故
1.2 目視点検の限界と新しい点検アプローチの需要
2.車載型センシングの最先端
2.1 可視空間センシング
2.2 非可視空間センシング
2.3 車載型地中レーダー(GPR)・LiDARの統合による路面・路面下の立体可視化
3.深層学習による自動解析
3.1 GPRデータに対するセグメンテーションおよび逆解析手法
4.自治体における社会実装の最前線
4.1 約128kmにおよぶ走行計測
4.2 大規模解析の例
5.今後の展望:無人化・標準化・輸出戦略
5.1 自動運転技術と連携した常時インフラ監視体制の構想
5.2 「四次元透視」の新たな概念・技術の創出・地中レーダー解析の最前線
【質疑応答】
セミナー講師
1.(国研)産業技術総合研究所 センシング技術研究部門 主任研究員 理学博士 渡部 愛理 氏
2. 第一高周波工業(株) 新事業推進部 営業部 係長 田上 祥太 氏
3. 東京大学 生産技術研究所 准教授 博士(工学) 水谷 司 氏
セミナー受講料
1名につき60,500円(消費税込、資料付)
〔1社2名以上同時申込の場合のみ1名につき55,000円〕
受講について
セミナーの接続確認・受講手順はこちらをご確認下さい。
受講料
60,500円(税込)/人
※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です
開催日時
10:30 ~
受講料
60,500円(税込)/人
※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます
※銀行振込
開催場所
全国
主催者
キーワード
土木技術 自動車技術 人体計測・センシング前に見たセミナー
※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です
開催日時
10:30 ~
受講料
60,500円(税込)/人
※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます
※銀行振込
開催場所
全国
主催者
キーワード
土木技術 自動車技術 人体計測・センシング関連セミナー
もっと見る関連教材
もっと見る関連記事
もっと見る-
電動建機のメリット・デメリットとは?普及を阻む課題と未来を徹底解説
【目次】 現代の建設業界は、技術革新と環境要件という二つの大きな波に直面しています。世界的なカーボンニュートラルへの... -
EVの未来を握る「eAxle」の衝撃とは?仕組み・メリット・課題をわかりやすく解説
【目次】 ※本記事を執筆した専門家「高原 忠良」が提供するセミナー一覧はこちら! 自動車の歴史は、内燃機関の進化とともに歩んできました... -
SDV に代表されるプロダクトの「ソフトウェア化」に対応するための基本方針
【目次】 前回の「SDV 時代における旧来のソフトウェア開発からの脱却と競争優位性確立のための戦略」は、「ソフトウェア定義型自動車... -
SDV(ソフトウェア定義型自動車)時代における旧来のソフトウェア開発からの脱却と競争優位性確立のための戦略
【目次】 自動車業界は電動化、ソフトウェア化、中国躍進、関税など、大きな変革期にあります。中でも「ソフトウェ...