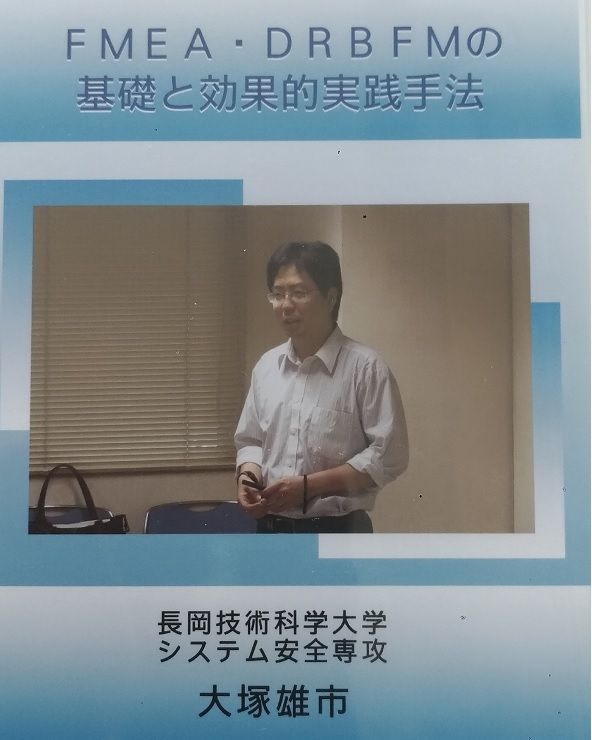類似セミナーへのお申込みはこちら
★粒子分散技術の基礎、分散性及び安定性評価、分散の実務、分散剤の選定・評価、分散機の選定・評価!
★理解度を深めるため、両日とも最後に、その日の最重要ポイントを確認・復習します!
【日時】 2017年5月30日(火) 11:00-17:00
2017年5月31日(水) 09:30-15:30
粒子分散系における粒子の分散状態は、分散液の流動性や沈降の有無、分散液から得られる被膜の表面平滑性や膜密度、種々の光学的性質などに、大きな影響を与える。良好な粒子分散系を得るためには、ソフトとハードの両面を理解し、最適な選択をする必要がある。
本講では、ソフト面として構成成分の組み合わせ方や材料選択に関する基本的な考え方を、有機溶剤系・水系それぞれについて、入門者向けに平易に解説するとともに、各種分散剤の特徴や使い方、高分子分散剤の合成方法や最近の開発動向を紹介する。
また、ハード面としては、分散機・分散プロセスの選定に関する基本的な情報を提供するとともに、最近話題のナノ分散のための分散機・分散プロセスについても取り上げる。
粒子分散の評価では、分散度の評価とフロック形成状態の評価が重要であり、濃厚粒子分散系への提供を念頭に、主な粒子径計測方法の原理と適用上の留意点、粘度測定によるフロック形成の評価法について解説する。
■受講後、習得できること
・粒子~高分子(分散剤・バインダー)~溶剤の親和性に関する基本的な考え方
・分散のための粒子表面評価法
・粒子分散安定化メカニズム
・各種粒子径測定装置の原理と使用上の留意点
・各種分散機・分散プロセスに関する基本的な情報
・分散剤の分子設計と製造法の実例
・分散剤の使い方と分散配合設計
【講師】
小林分散技研 博士(工学) 小林 敏勝 先生
東京理科大学 理工学部 客員教授 *元日本ペイント(株)
【セミナープログラム】
(1日目)
第1部(11:00-12:00)「粒子分散技術の基礎」
1. 粒子分散の基本的な考え方
1.1 一次粒子と二次粒子 ~分散とは二次粒子を一次粒子にほぐすことである~
1.2 分散の単位過程 ~三つの単位過程に分けて考えよう~
1.2.1 濡れ ~濡らす物と濡らされる物の表面張力の相対的大きさで決まる~
1.2.2 機械的解砕 ~分散機と分散プロセスの選択と設計~
1.2.3 分散安定化 ~実用的な系では高分子吸着で~
1.3 粒子~高分子~溶剤間の親和性はどうあるべきか
第2部(12:40-14:00)「粒子分散性及び安定性評価」
1. 粒子の分散状態を評価し、粒子分散液の性質との関係を考える
1.1 フロキュレートの形成と分散液の流動性
1.1.1 フロキュレート形成のメカニズム
1.1.2 フロキュレート形成の評価 (Casson式と降伏値、チキソトロピー係数)
1.1.3 擬塑性流動とチキソトロピー
1.1.4 ダイラタンシーと粒子の分散状態
1.2 粒子分散度が関係する性質
1.2.1 光の散乱 (隠ぺい、ヘイズ)
1.2.2 乾燥被膜の平滑性
1.2.2 沈降
1.3 粒子分散度の評価法
1.3.1 粒ゲージ法 ~分散度評価法としてのJISがあるのはこれだけ~
1.3.2 顕微鏡法
1.3.3 沈降速度法
1.3.4 光子相関法(動的光散乱法)
1.3.5 光回折法
1.3.6 超音波減衰分光法
1.3.7 乾燥被膜の光沢から間接的に分散度を評価する
1.4 分散安定性に関する諸現象
1.4.1 複数種類の粒子が共存する際に生じる不具合現象
1.4.2 粒子分散液に溶剤や高分子を加える際の留意点(溶解ショック)
1.4.3 粒子分散が安定であるとは
第3部(14:10-16:20)「分散の実務」
1. 有機溶剤系での分散の実務
1.1 粒子と高分子(樹脂や分散剤)の酸塩基性評価法
1.1.1 非水電位差滴定法 ~酸塩基の量と強度が求められる~
1.1.2 等電点と等酸点 ~粒子表面の酸塩基性の目安~
1.2 バインダー樹脂で分散する
1.2.1 酸塩基変性の効果
1.2.2 阻害効果
2. 水系での分散の実務
2.1 水系ではまず濡れを考える ~ウオッシュバーン式と濡れに影響する因子~
2.1.1 親水-疎水性度 ~これは誰でも考える~!
2.1.2 凝集の幾何学的因子 ~タイトに凝集した粒子は濡れにくい~
2.2 水系での分散安定化
2.2.1 界面電気化学(DLVO理論)の基本と適用上の留意点
2.2.2 水の構造と疎水性相互作用
2.2.3 疎水性相互作用による高分子吸着 ~実用系ではこれが主体~
2.3 粒子表面の最適親水性度 ~濡れと分散安定化の両立~
2.4 混合有機溶剤の影響
「確認・復習と全体質疑応答」(16:25-17:00)
(2日目)
第4部(09:30-11:50)「分散剤の選定・評価」
1. 界面活性剤概論
1.1 低分子量界面活性剤の種類と特徴
1.2 粒子分散に影響する因子
1.2.1 臨界ミセル濃度
1.2.2 曇点
1.2.3 HLB値
2. 高分子分散剤の基本構造 ~アンカー部と溶媒和部~
2.1 アンカー部の種類
2.2 アンカー部の分布と粒子分散性 ~分散剤の分子設計~
2.2.1 橋架け吸着による粒子凝集
2.2.2 ランダム型高分子
2.2.3 ホモポリマー型高分子分散剤
2.2.4 ブロック型高分子分散剤 ~直鎖型と多点吸着型分散剤(櫛形分散剤)~
3. 分散剤の合成
3.1 グラフト法による分散剤の合成
3.1.1 Grafting through法
3.1.2 Grafting onto法
3.1.3 いくつかの分散剤合成の実例
3.2 精密重合法
3.2.1 精密重合法とは
3.2.2 精密重合法により合成された分散剤の特徴
4. 分散剤の評価と使いこなし
4.1 分散剤の評価とマッピング例
4.2 分散配合の決定
第5部(12:30-14:50)「分散機・分散プロセスの選定・評価」
1. 粒子分散プロセス概論
1.1 粒子分散に用いられる一般的な分散機・撹拌機とその特徴
1.1.1 ロールミル
1.1.2 ニーダー(フラッシャー)
1.1.3 エクストルーダー
1.1.4 プラネタリーミキサー
1.1.5 ボールミル
1.1.6 アトライター
1.1.7 高速インペラー分散機
1.1.8 コロイドミル
1.1.9 ビーズミル
1.2 分散プロセス
1.2.1 分散方式 ~予備混合、パス分散、循環分散~
1.2.2 多品種少量生産に適した分散機
2. ナノサイズ分散機
2.1 ナノサイズ分散機の特徴
2.2 過分散 ~一次粒子の破砕とその影響~
2.3 異種分散方式の組み合わせによる高分散度化
3. 最近登場した分散機
4. ラボ用分散機
「確認・復習と全体質疑応答」(14:55-15:30)
受講料
61,560円(税込)/人
※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です
開催日時
11:00 ~
受講料
61,560円(税込)/人
※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます
※銀行振込
開催場所
東京都
【品川区】きゅりあん
【JR・東急・りんかい線】大井町駅
主催者
キーワード
化学技術
※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です
開催日時
11:00 ~
受講料
61,560円(税込)/人
※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます
※銀行振込
開催場所
東京都
【品川区】きゅりあん
【JR・東急・りんかい線】大井町駅
主催者
キーワード
化学技術類似セミナー
関連セミナー
もっと見る関連教材
もっと見る関連記事
もっと見る-
グリーン水素とは?なぜグリーン水素が注目されるのか、知っておきたいグリーン水素のすべて
【目次】 地球温暖化の進行と化石燃料への依存からの脱却は、現代社会が直面する最も喫緊の課題の一つです。世界各国が持続可能な社会の実現... -
ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)とは?ゼロエネビル、その驚きの効果と事例を解説
【目次】 近年、地球温暖化やエネルギー問題への意識が高まる中で「ゼロ・エネルギー・ビル」、略して「ZEB(ゼブ)」という言葉を耳にす... -
光インターコネクトが拓く未来、AI時代のデータ爆発を解決するCPO・シリコンフォトニクスとは
【目次】 生成AIの急速な進化や、あらゆるモノがネットに繋がるIoT社会の到来により、世界のデータ量は2年ごとに倍増するとも言われて... -
パーパス経営とは?社員を惹きつけ、顧客を繋ぐパーパス経営をわかりやすく解説
【目次】 現代のビジネス環境は、目まぐるしい変化の渦中にあります。テクノロジーの進化、社会課題の複雑化、そして人々の価値観の多様化は...