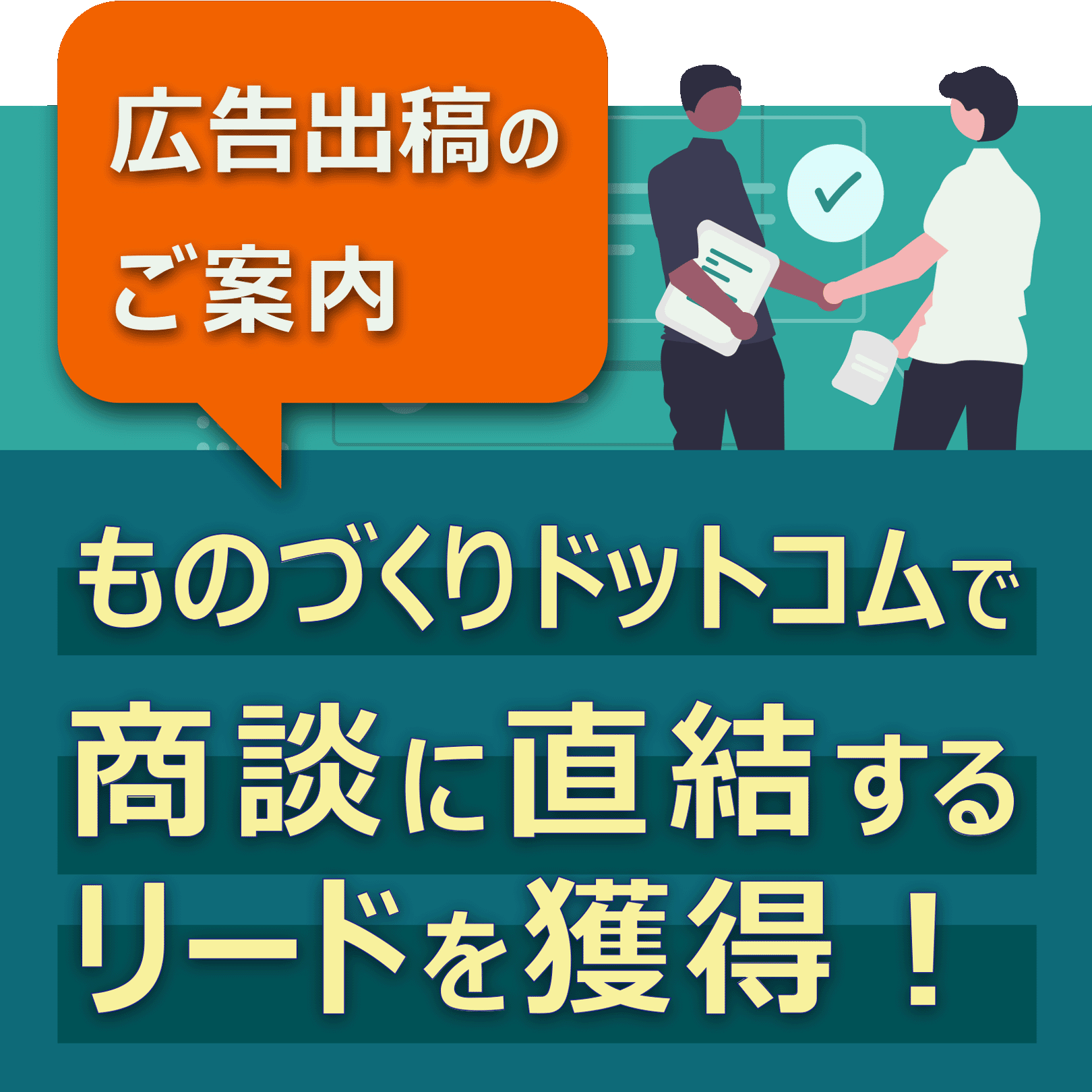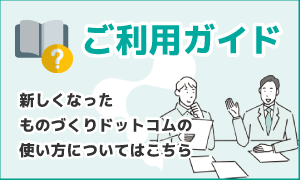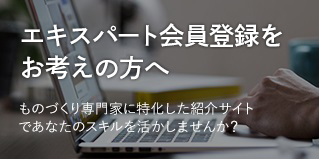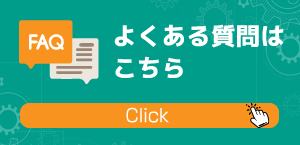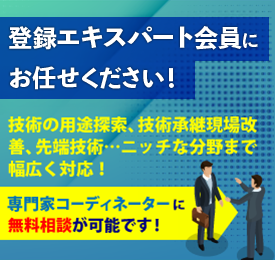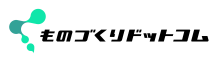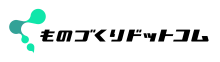
① L8直交表を用いた実験において、交互作用が無いと判断できるとき、7因子まで評価できますが、その場合誤差列がなくなるため、分散分析に進めないように思います。分散分析を行うためには、因子は6つまでということになりますでしょうか。
② 直交配列実験の繰り返しは、どのように考えれば良いのでしょうか。
1回の直交配列実験そのものを数回繰り返し、各因子の効果や交互作用ごとに1元配置実験の要領で分散分析を実施するということでしょうか。
③ 上記の理解が正しければ、①のように7因子全てを7列使って評価し、②のように繰り返すことで、分散分析を実施すればよい、ということでしょうか。
実験計画法を学んでいる最中のため、見当違いの質問がありましたら、ご容赦ください。
補足1 投稿日時:2023/02/09 8:14
直交配列の繰り返しについて、追加で質問させてください。
村島様の、直交配列実験の繰り返しは実験間誤差になるというご指摘は、乱塊法の考えということでしょうか。繰り返しごとの実験間のブロック因子を考えないといけないという。
考え方を変えますが、L8直交表で決めた8実験を繰り返し2回の計16回を無作為に実験するとした場合、各因子や交互作用の効果を調べるには、2回の平均を用いれば良いのでしょうか(誤差も同様に2回の平均値)。
自由度については、因子は2水準のままなので1と思いますが、誤差自由度も1のままでしょうか。総実験数が増えるので誤差の自由度は大きくなるように思われるのですが。
こういう場合の分散分析の手法についてアドバイス頂けると幸いです。
効果の小さい要因効果や交互作用を誤差として扱うという考えは理解できるのですが、実験の繰り返しではないと、実験そのものの誤差は汲み取れないのではないかと思っております。
登録専門家の村島です。実験計画法、品質工学、多変量解析等々のコンサルタントやセミナーを行っております。
かんたんに、ご質問に回答させていただきます。
①相対的に頑健性の高い因子と水準を求める場合には、7個の因子のうち、相対的に分散が小さいものをプールしていきます。3個か4個ぐらいでいいと思いますが、厳密な基準はありません。プールした平方和と自由度から分散を計算し、誤差分散とします。これで、検定するわけです。
通常の実験計画法であれば、6個の因子をわりつけて、1個を誤差列にとるということでも、もちろん間違いではありません。ただし、やればわかりますが、誤差の自由度が1で、その他6個の因子の自由度もそれぞれ1ですから、有意になる可能性は非常に小さくなります。又、誤差の自由度が5以下では、通常判定保留にします。結局、7個割付けと同じように、プーリングをしていくことになります。L8は、プールしていっても誤差の自由度がかなり小さいので、判定保留覚悟になります。
②直交配列実験の繰り返しは、実験間誤差となります。1因子ごとの一元配置実験と同じような処理をやってはいけません。実験場が2つあるので、その繰り返しは、あくまでも実験間誤差で検定します。もちろん、ひとつの実験場で繰り返し(サンプリングや測定)があれば、その繰り返し誤差と区分して、検定します。実験間誤差の計算方法は、下記セミナーを参考にしてください。
③前項にて、ご回答したとおり、実験間誤差を確保しているのであれば、7個の因子を検定することは可能です。
よく間違えるものに、サンプリングの繰り返しや測定の繰り返しと実験そのものの繰り返しです。質問者の方は、実験の繰り返しとされていますが、それでいいです。
具体的な説明は略しますが、サンプリングや測定の繰り返しよりも実験間誤差を優先するほうがいいので、実験繰り返しの工数が許されれば、そのほうがいいでしょう。
なお、私のオンデマンドセミナーでも詳細説明しています。そのものずばりの説明ではありませんが、下記参照にしてください。
ものづくり.com 村島⇒セミナー⇒実践的SQC習得オンデマンドセミナーー効率的品質管理のための統計的手法の基本と応用ーの第4回と第5回です。そのものずばりの説明でなくても、かなり基本から説明していますので、わかりやすいと思いますが、もしわからなければ、質問はメールでもZOOMでも受け付けます。(産業革新研を通してください)
以上です。よろしくお願いします。
|
|
QE Compassの細川と申します
寄与の小さい制御因子をプールし、実験誤差として扱いF検定を実施するアプローチが一般的ですが、このような方法では納得のある結果が得られないケースが多いのも事実です。効果があるはずの制御因子にも関わらず有意にならない、効果ないはずの制御因子が有意になるなど。空き列を設けて誤差列とする方法もありますが、交互作用がゼロということは現実的にはありませんので、多くの実験では空き列に交互作用が交絡します。よって、現実には正しく検定ができません。
検定によって制御因子の効果を判断するのであれば、ご提案のように繰り返し実験を実施することは上記の問題を回避できるので効果的です。ただし、繰り返し実験は実験回数が増えてしまいますので効率性を犠牲にすることになりますが。それと、もし手間でなければ、実験の順番をランダマイズして系統誤差を偶然誤差にすると良いかと思います。
ここからは品質工学的な側面からのアドバイスとなります。交互作用がないと判断できるとのことですが、それを実験的に確認された方が良いかと思います。取り上げた制御因子が目的特性と因果関係を持つとき、交互作用は必ず存在すると考えるのが現実的です。よって、直交表実験を実施する際には必ず確認実験を実施することをお勧めします。特に交互作用の空き列のない実験の場合は必須かと思います。確認実験の方法については品質工学の書籍に書かれていますので参照お願いします。
まったく異なる方法としては、交互作用が均等にばらまかれるL12などの混合型直交表を用いて実験し、要因効果図から各制御因子の寄与を判断する。さらに確認実験で交互作用の影響度を評価する。この方法が精度と効率の両立性の面で最も優れていると思います。
参考になれば幸いです
|
|
未完成な音色さん、
ご質問の趣旨は理解できますが、もっと本質的なことを教えてください。
そもそも目的は何なのでしょうか?
特性値に対する因子の影響が統計的に有意なのかを調べるだけでしたら、ご質問には意味があります。それは因果関係の追及の場合です。この場合はF検定などが意味をもちます。
特性値が品質工学で言う望小、望大、望目等であれば目的は最小化や最大化、バラツキの最小化と目標値の合わせこみという技術的目的がありますからアプローチは変わってきまし、統計的な有意度はあまり気にしないことを奨めます。基本的に各因子の影響があるとして、それが大きいのか微々たるものなのを判断するべきです。
その意味で因子の種類が制御因子なのか、ノイズ(誤差因子)なのかで解析法や、その解釈も変わってきます。
ブロック因子をお考えのようですが、因果関係の追及でしたらその意味があります。目的としてブロックの水準ごとでの最適化なのか、ブロック因子をノイズとしてロバストにするというのがあり得ます。
目的有りきですので、助言は難しいです。
答えになってなくて申し訳ありません。
|
|
村島です。補足質問へのご回答です。
実験間誤差は、わざわざ乱塊法に含める人はいないと思いますが、間違いでもありません。たとえば、実験の繰り返しを1回目と2回目で、実施日の違いにするなら、実験日をブロック因子と考えれば、これも立派な乱塊法です。解析は、同じです。
次の質問ですが、2回の平均をとってはいけません。そんなことをすると、実験間誤差を全く無視してしまうことになります。実験計画法は「平均をとらない」ことが原則です。平均をとると、個々のデータのばらつきを考慮できないし、自由度も減ってしまいます。自由度が、減るはずはないことからも平均をとってはいけない理由がわかると思います。
(L8を2回繰り返したのであれbば、全自由度は15です。平均とったら、8個の平均値のデータから1引いて、7です。これは、大きな間違いになります。)
最後のほうのご質問は、そのとおりなので、それでいいと思います。実験の繰り返しによってのみ、実験間誤差は計算されます。
ただし、
効果の小さい(変動の小さい、分散の小さい)ものを実験間誤差として処理するということが、なぜ、実験間誤差になるのか? という質問だと思いますが、(間違ってたらすいません)、これは、「単に、そう考える」というだけのことです。数理的な厳密な保証はありません。効果が小さいので、誤差に(実験間誤差の一種に)しておこう、ということです。実験計画法では、これをプーリングといっていますが、この厳密なやり方というのはないのです。いろいろなやり方、考え方があります。具体例によって異なります。
なお、くどいですが、そういう意味では、実験間誤差の前に、サンプリングや測定繰り返しの誤差(いわゆるデータ繰返しの誤差)を算出できる実験計画にしておくといいでしょう。1回目で、各実験Noごとに、2個のデータ繰返し、2回目でも同様に2個のデータ繰返し。そうすれば、データ繰返しと実験間誤差が区分できます。もし、実験間誤差が有意であれば、検定は実験間誤差で行います。有意でなければ、このふたつをプールします。いずれにせよ、こういった誤差の誤差分散と比べて、わりつけた因子の分散が、かなり小さければ、文句なしの実験間誤差(の一種)だし、ほぼ2倍程度までなら、実験間誤差にプールしますが、有意性から判断してもいいでしょう。
ご検討ください。
|
|
補足質問にコメントさせていただきます
先ほどは一般論的な内容で回答させていただきました。実験計画の詳細については,実験の目的,計測特性,因子の種類などを把握した上で,網羅性及び精度と効率性を考慮して決定する必要があります。仮に実験の目的が性能の向上であり,計測特性を大きくしたいのであれば,できるだけ沢山の制御因子を取り上げて混合系直交表にわりつけて最適化する方法がお勧めです。
ばらつきの低減が目的であれば,繰り返し1回では足りないでしょう。誤算因子の導入が現実的になります。
ばらつき要因を抽出するために,その候補となる誤差因子を抽出したいのであれば直交表実験以外のアプローチが有効かもしれません。
このような視点でもご検討いただければと思います
|
|

 コミュニティはこちら
コミュニティはこちら