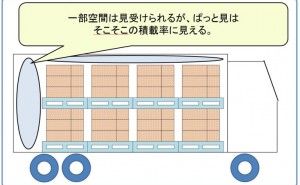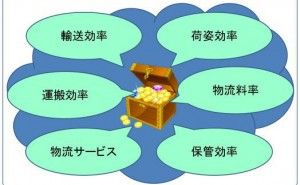前回の稼働分析とは:倉庫内物流作業の改善(その2)に続いて解説します。
1. 作業改善:倉庫内作業~通路幅の理想は1m未満
倉庫内作業で気を付けなければならないことがあります。それは効率的にエリアを使う手法です。エリアが十分にある事例は必要以上に「のびのびと」使うことが考えられます。
エリアが不足している事例も困りものですが、広すぎても効率を落としがちです。ちょっときつめかな、と感じるくらいの提案が丁度(ちょうど)良いと考えられます。
皆さんの会社でピッキング場の通路幅はどれくらいでしょうか。本当に効率を上げようと考えている会社では1m未満が大半です。
しかし効率を真剣に考えずに設計すると、1.5m~2mくらい取ってしまいます。よくある理由が「2台の台車がすれ違えるため」といわれますが、これは意味はないと思います。
まず、台車同士がすれ違う現象がどれくらいの頻度で起こるのか、ということを考えてみましょう。一般的にはそれほどないと思われますが、一日に何度もあるようでしたら「人が多いのではないか」と疑ってみる必要がありそうです。
むしろ通路幅を縮め、一方通行にするとともに作業編成を考え、人と人が干渉しないように業務指示を行うべきだと思います。
2. 作業改善:梱包作業場~作業者が動かない工程設計を
梱包作業場も一緒です。エリアがあるからといってのびのびと使うのではなく、極力「間締め(まじめ)」を行い、作業者の動く範囲を縮めなければなりません。
もし皆さんの会社がメーカーであれば一度、生産現場を見に行きましょう。多分そこでは「間締め」が行われていて、作業者の歩行は極小化されているものと思われます。
メーカーでない場合は、どこかの製造会社に見学に行きましょう。思想は同じですから、生産現場でも物流現場でも作業者が動き回らないような工程設計を実施していきたいものです。
このほか、作業者に万歩計をつけさせている会社もあります。これは、同じ作業をやらせても歩行に差が出る場合があります。その要因として業務指示が十分でないため、作業者の裁量が大きすぎる可能性が考えられます。
あるいは時間に余裕があるため、必要以上に歩き回っている可能性もあるでしょう。ここはどちらかというと現場管理の課題です。
会社として明確な作業ルールを設定し、それを守らせるような仕掛けづくりが必要です。これも倉庫の生産性向上に効いてくるアイテムですから、しっかりとした取り組みを心掛けましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
いかがでしょうか。倉庫内物流作業改善への取り組みの必要性について、ご理解いただけたのではないでしょうか。すでに十分な取り組みを継続している会社もあります。ぜひ、他社に負けないよう、積極的に作業改善を進めていきましょう。