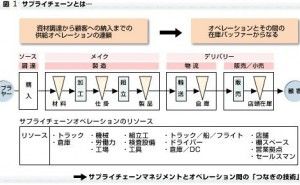◆ 倉庫容積率という考え方
日本は国土が狭い影響を受けてか、物流に関するスペースも不足する傾向にあるようです。一時期海外との取り引きが拡大するにつれて港湾地区に集中立地する傾向にあった倉庫は、最近ではBCPの取り組みの一環として内陸部に建設されるようになる一方、都市部では多層階型の倉庫が一般的になってきました。
高速道路のインターチェンジ付近は物流倉庫にとって一等地でもあります。なぜなら我が国にとって極力リードタイムを短縮して行う物流のニーズが高いため、トラック主体の輸送にならざるを得ないからです。
物流倉庫のみならず、工場併設倉庫や工場建屋内倉庫についてもエリアは貴重だといえるでしょう。工場では倉庫エリアは原則として付加価値を生んでいない場所とみなされるため、エリア効率は重要ファクターとなるのです。
先日、ある物流会社の方から相談がありました。「倉庫効率を向上させるためのKPIとして『倉庫容積率』はどれくらいが一般的か」という質問です。
まずこのような意識の高さに驚いた次第ですが、極めて常用な考え方であるとも思いました。そうです。物流倉庫や工場倉庫ともに面積に対する使用率は気にしますが、その二次元にとどまらず、高さ方向も加味した三次元評価をしている会社はほとんど見かけません。
倉庫の効率は「倉庫容積率」で評価することが妥当でしょう。この倉庫容積率は次の算式で求められます。
倉庫容積率 = 保管貨物総容積 ÷ 倉庫総有効容積
倉庫を水で満たした時の水の質量が倉庫総有効容積になります。保管貨物の容積は一つ一つの箱の容積をすべて足し合わせたものになります。この二つの比率を...