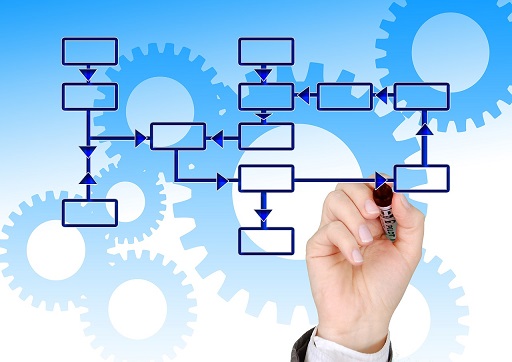近年、世界経済は歴史的なインフレ、地政学的なリスクによるサプライチェーンの分断、そして原材料価格の激しい高騰という未曾有の環境変化に直面しています。このような経営環境において、企業活動の根幹を支える「調達購買」部門が持つ戦略的な重要性は、かつてないほど高まっています。これまで調達購買は、単に「コストを抑えるための実務」として裏方的な役割を担うことが一般的でした。しかし、ひとたび原材料の供給が途絶えれば生産活動は停止し、価格高騰への対応が遅れれば企業の利益は一瞬にして消滅します。調達購買は、まさに企業の「血液循環」を司る心臓であり、その優劣が企業の競争力と存続を直接的に左右する時代へと突入したのです。今回は、この重要な機能が経営に与える具体的なインパクトと、日本企業が抱える「認識のギャップ」を克服し、調達購買を戦略的な経営の柱へと進化させるための方策について解説します。
◆関連解説記事:調達購買部門を「コスト部門」で終わらせないための経営戦略~戦略部門への進化が企業の成長を左右する~
1. 調達購買の存在感が問われる時代へ
これまで日本企業では、調達購買部門は「コストを抑えるための実務部門」として扱われる場合が多かったようです。しかし、世界的なインフレ、サプライチェーンの分断、原材料価格の高騰、急速な技術革新などの環境変化の中で、次のような理由から調達購買が企業経営に与える影響は、かつてないほど大きくなっています。
- 原材料が入らなければ生産は止まり、価格高騰に対応できなければ利益は消える。
- 品質トラブルや納期遅延が発生すれば、取引先との信頼関係にも直結する。
つまり調達購買は、企業の「血液」を循環させる心臓のような存在です。それにもかかわらず、多くの企業ではその重要性が十分に理解されていません。この「認識のギャップ」こそが、今、見直すべき最大の経営課題です。
2. 経営に直結する調達購買の3つの役割
調達購買部門が果たすべき役割は、単なるコスト削減ではあり...