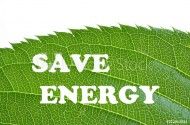多くの日本企業において、調達購買部門は「見積を取って発注するだけのコストセンター」という認識に留まりがちです。しかし、原材料費の高騰やサプライチェーンの複雑化が進む現代、調達の巧拙は企業の利益とリスクに直結し、経営力そのものを左右します。今回は、調達購買部門が単なるコスト部門の役割を超え、いかにして企業の成長を担う「戦略部門」へと進化すべきか、その具体的な道筋と重要性を解説します。
1. 調達購買部門のプレゼンスが低い現状
多くの日系企業では、依然として調達購買部門の存在感が薄いようです。「見積を取って発注するだけ」「コストを抑えることが仕事」という認識が根強く、社内でも「支出を管理 するコスト部門」として扱われているケースが少なくありませ。その結果、現場では次のような姿が見られます。
- 関係部門からの見積依頼をそのまま処理
- 決まったサプライヤーへの見積・発注の繰り返し
- 納期調整や品質トラブルの対応に追われ、改善に時間を割けない
こうした状況では、調達購買部門は「誰でもできる仕事」に見えてしまい、スキルが評価されにくいのです。 しかし本来、調達購買業務は企業の利益に直結する「戦略業務」であり、設計・生産・営業のいずれとも 密接に関わる経営中枢機能のひとつです。
2. 外資企業に見る「戦略調達」の考え方
一方で、外資系企業では古くから、調達購買部門を企業収益に貢献する戦略部門として明確に位置づけているケースが多いのです。
組織構造としても「ソーシング(調達戦略)」と「パーチェシング(購買実務)」の役割を明確に分け、担当者が単なるオペレーションに終始しない...