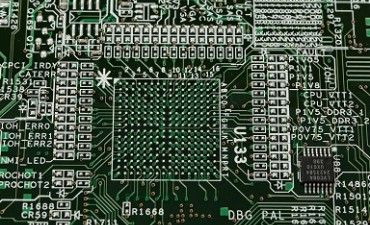自動車の駆動システムはガソリンエンジンなどの内燃機関から、モーターとエンジンを組み合わせたハイブリッド、そして電気のみで走行するEVへと、進化の歴史を歩んできました。しかしその進化は駆動源の変更に留まらず、配置そのものに革新をもたらす技術が注目されています。それが「インホイールモーター」です。従来の自動車ではエンジンやモーターが、ほとんどの場合車体中心線上に配置され、プロペラシャフトやドライブシャフトを介して車輪を駆動していましたが、インホイールモーターは文字通り車輪の中にモーターを組み込みます。この発想の転換が自動車の設計自由度を飛躍的に高め、EVの性能をこれまでにないレベルへと引き上げる可能性を秘めているのです。まさに常識を覆すこの駆動技術は、モビリティの未来を大きく変える鍵となるでしょう。
1. モビリティの未来を担うインホイールモーター
自動車産業は今、歴史的な転換期にあります。地球環境問題への意識の高まりや、自動運転技術の進化、そしてMaaS(Mobility as a Service)といった新たなサービスの登場により、自動車に求められる役割や価値は大きく変化しています。この変革期において、特にEVは環境性能の高さや静粛性、そして電気駆動ならではの制御性の良さから、次世代モビリティの中心的存在として期待されています。そのEVの性能をさらに引き出し、モビリティの未来を拓く可能性を秘めているのがインホイールモーターです。
インホイールモーターは、従来の複雑な駆動系部品、例えばトランスミッションやプロペラシャフト、デファレンシャルギア、ドライブシャフトといったものをごっそり削減し、各車輪に独立したモーターを配置するものです。これにより車両設計の自由度が格段に向上します。例えば広大な室内空間の確保や、これまでにない車両レイアウトの実現が可能となり、乗員の快適性や積載能力を大幅に向上させることができます。またモーターが直接車輪を駆動するため、エネルギー伝達ロスが最小限に抑えられ、効率的な電力利用が可能となります。
さらに、各車輪を個別に制御できるという特性は車両の運動性能に革命をもたらします。トラクションコントロールやアンチロックブレーキシステムといった従来の電子制御では難しかった、よりきめ細やかなトルク配分が可能となり、あらゆる路面状況において車両の安定性を高め、ドライバーに安心感を提供します。雪道や凍結路といった滑りやすい状況でも、路面状況に応じた最適な駆動力を各車輪に独立して供給することでスリップを抑制し、安全な走行を実現します。インホイールモーターは、CASE、MaaS(Mobility as a Service)に代表されるモビリティ革命を支える重要な技術と言えるでしょう。
◆関連解説記事<モビリティ革命とは?モビリティ革命が描く未来の移動と新しい社会システムの探求>
2. インホイールモーターの仕組み、車輪に宿る駆動の心臓
(1)インホイールモーターの仕組み
インホイールモーターは、文字通り車輪の内部に組み込まれたモーターが、その車輪を直接駆動する仕組みです。従来の自動車では、エンジンやメインモーターといった単一の動力源から、プロペラシャフトやドライブシャフト、デファレンシャルギアといった複雑な機械部品を介して各車輪に動力が伝達されていました。これに対しインホイールモーターでは、各車輪に独立したモーターが備わるためこれらの伝達機構が不要になります。
具体的には、モーターは車輪のハブ部分に直接、あるいは非常に近い位置に内蔵されます。このモーターは通常、DCブラシレスモーターや永久磁石同期モーターといった高効率で小型化に適したタイプが用いられます。モーターの回転軸が車輪の回転軸と一致するように設計されており、モーターが発生させた回転力がギアを介して直接車輪を回す、あるいはダイレクトドライブ方式で直接車輪に伝達される形となります。
(2)インホイールモーターの特徴
インホイールモーターの大きな特徴は、そのシンプルな構造にあります。駆動力を発生させるモーターが車輪のすぐそばにあるため、動力伝達経路が極めて短く、従来の複雑な機械部品に伴うエネルギーロスを大幅に削減できます。これにより、バッテリーから供給される電力をより効率的に走行に利用できるため、EVの航続距離の延伸に貢献します。
また各車輪に独立したモーターが配置されるため、それぞれのモーターを個別に制御することが可能です。例えば、右カーブでは右側の車輪のトルクをわずかに減らし、左側の車輪のトルクを増やすことで、車両をスムーズに旋回させることができます。これは「トルクベクタリング」と呼ばれる技術で、従来の車両...

自動車の駆動システムはガソリンエンジンなどの内燃機関から、モーターとエンジンを組み合わせたハイブリッド、そして電気のみで走行するEVへと、進化の歴史を歩んできました。しかしその進化は駆動源の変更に留まらず、配置そのものに革新をもたらす技術が注目されています。それが「インホイールモーター」です。従来の自動車ではエンジンやモーターが、ほとんどの場合車体中心線上に配置され、プロペラシャフトやドライブシャフトを介して車輪を駆動していましたが、インホイールモーターは文字通り車輪の中にモーターを組み込みます。この発想の転換が自動車の設計自由度を飛躍的に高め、EVの性能をこれまでにないレベルへと引き上げる可能性を秘めているのです。まさに常識を覆すこの駆動技術は、モビリティの未来を大きく変える鍵となるでしょう。
1. モビリティの未来を担うインホイールモーター
自動車産業は今、歴史的な転換期にあります。地球環境問題への意識の高まりや、自動運転技術の進化、そしてMaaS(Mobility as a Service)といった新たなサービスの登場により、自動車に求められる役割や価値は大きく変化しています。この変革期において、特にEVは環境性能の高さや静粛性、そして電気駆動ならではの制御性の良さから、次世代モビリティの中心的存在として期待されています。そのEVの性能をさらに引き出し、モビリティの未来を拓く可能性を秘めているのがインホイールモーターです。
インホイールモーターは、従来の複雑な駆動系部品、例えばトランスミッションやプロペラシャフト、デファレンシャルギア、ドライブシャフトといったものをごっそり削減し、各車輪に独立したモーターを配置するものです。これにより車両設計の自由度が格段に向上します。例えば広大な室内空間の確保や、これまでにない車両レイアウトの実現が可能となり、乗員の快適性や積載能力を大幅に向上させることができます。またモーターが直接車輪を駆動するため、エネルギー伝達ロスが最小限に抑えられ、効率的な電力利用が可能となります。
さらに、各車輪を個別に制御できるという特性は車両の運動性能に革命をもたらします。トラクションコントロールやアンチロックブレーキシステムといった従来の電子制御では難しかった、よりきめ細やかなトルク配分が可能となり、あらゆる路面状況において車両の安定性を高め、ドライバーに安心感を提供します。雪道や凍結路といった滑りやすい状況でも、路面状況に応じた最適な駆動力を各車輪に独立して供給することでスリップを抑制し、安全な走行を実現します。インホイールモーターは、CASE、MaaS(Mobility as a Service)に代表されるモビリティ革命を支える重要な技術と言えるでしょう。
◆関連解説記事<モビリティ革命とは?モビリティ革命が描く未来の移動と新しい社会システムの探求>
2. インホイールモーターの仕組み、車輪に宿る駆動の心臓
(1)インホイールモーターの仕組み
インホイールモーターは、文字通り車輪の内部に組み込まれたモーターが、その車輪を直接駆動する仕組みです。従来の自動車では、エンジンやメインモーターといった単一の動力源から、プロペラシャフトやドライブシャフト、デファレンシャルギアといった複雑な機械部品を介して各車輪に動力が伝達されていました。これに対しインホイールモーターでは、各車輪に独立したモーターが備わるためこれらの伝達機構が不要になります。
具体的には、モーターは車輪のハブ部分に直接、あるいは非常に近い位置に内蔵されます。このモーターは通常、DCブラシレスモーターや永久磁石同期モーターといった高効率で小型化に適したタイプが用いられます。モーターの回転軸が車輪の回転軸と一致するように設計されており、モーターが発生させた回転力がギアを介して直接車輪を回す、あるいはダイレクトドライブ方式で直接車輪に伝達される形となります。
(2)インホイールモーターの特徴
インホイールモーターの大きな特徴は、そのシンプルな構造にあります。駆動力を発生させるモーターが車輪のすぐそばにあるため、動力伝達経路が極めて短く、従来の複雑な機械部品に伴うエネルギーロスを大幅に削減できます。これにより、バッテリーから供給される電力をより効率的に走行に利用できるため、EVの航続距離の延伸に貢献します。
また各車輪に独立したモーターが配置されるため、それぞれのモーターを個別に制御することが可能です。例えば、右カーブでは右側の車輪のトルクをわずかに減らし、左側の車輪のトルクを増やすことで、車両をスムーズに旋回させることができます。これは「トルクベクタリング」と呼ばれる技術で、従来の車両では複雑なメカニズムや高度な電子制御が必要でしたが、インホイールモーターであれば各モーターの出力を微調整するだけで容易に実現できます。これにより車両の旋回性能、安定性、そして雪道や悪路での走破性が飛躍的に向上します。まさに車輪の中に駆動の心臓が宿ることで、自動車の運動性能に新たな次元をもたらす技術がインホイールモーターなのです。
3. インホイールモーターのメリットとデメリット
インホイールモーターは、その革新的な構造から多くのメリットをもたらしますが、同時に克服すべき課題も存在します。
(1)インホイールモーターのメリット
主なメリットとしては、まず車両設計の自由度向上が挙げられます。従来の駆動系部品が不要になるため、エンジンルームやトランスミッションスペースの制約がなくなり、広々としたキャビンや多様なボディデザインが可能になります。次に駆動効率の向上です。動力伝達経路が短くなることでエネルギーロスが最小限に抑えられ、バッテリーの電力をより効率的に利用できます。これはEVの航続距離延伸に直結します。さらに優れた運動性能も大きな利点です。各車輪を独立して制御できるため、緻密なトルクベクタリングが可能となり、旋回性能、安定性、トラクションコントロール性能が飛躍的に向上します。回生ブレーキの効率も高まり、エネルギー回収もより効果的に行えます。
(2)インホイールモーターのデメリット
一方でデメリットも無視できません。最も大きな、そして長年の課題が「バネ下重量の増加」です。インホイールモーターは車輪の内部にモーターや減速機が組み込まれるため、タイヤやホイールと共に路面からの衝撃を直接受ける「バネ下」の重量が増加します。バネ下重量が増えるとサスペンションの追従性が悪化し、路面の凹凸を乗り越える際にゴツゴツとした不快な突き上げを感じたり、タイヤの接地性が損なわれ、コーナリング性能やグリップ力が低下したりするなど、乗り心地と操縦安定性に深刻な影響を与えます。この課題の克服は容易ではありませんが、NTN、ニデック(旧日本電産)、シェフラーといった大手部品メーカーは、モーター自体の小型軽量化や応答性の高いサスペンションとの統合制御技術によって、この問題の解決に取り組んでいます。インホイールモーターがもたらす圧倒的なメリットは、この困難な技術課題に挑む十分な価値があるのです。
例えば軽量素材の使用や、モーターの配置を工夫することで重心を最適化する試みが行われています。インホイールモーターがもたらす圧倒的な設計自由度、高効率なエネルギー利用、そして卓越した運動制御性は、バネ下重量増加のデメリットを上回るほどの大きな変革を自動車にもたらす可能性を秘めているからです。特に、自動運転化が進む未来においては、車両の運動性能を極限まで引き出し、乗員の安全性と快適性を両立させる上で、インホイールモーターの果たす役割は大きいものがあります。この課題を克服することで、インホイールモーターはEVの真のポテンシャルを解き放つ鍵となるでしょう。前述のようにインホイールモーターは、日本ではNTNやニデック、海外ではシェフラーやプロティアン・エレクトリックなどが開発をリードしています。バスなどの商用車ではすでに実用化が始まっていますが、乗用車でもオランダのLightyear社が開発したソーラーカー『Lightyear 0』に搭載され、ルノーは2026年から生産する「5ターボ3E」への採用を発表するなど、実用化の動きが進んでいます。
4. インホイールモーターの用途、広がる可能性
インホイールモーターはその特性から様々なモビリティへの応用が期待され、その用途は多岐にわたります。最も直接的なのは、やはり乗用EVへの搭載です。モーターが車輪内に収まることで、従来のEVでデッドスペースとなっていた部分を居住空間や荷室として活用でき、より広々とした快適な室内空間を実現できます。また各車輪独立制御による高い運動性能は、ドライビングプレジャーを向上させるだけでなく、自動運転における安全性と快適性を高める上でも重要な要素となります。特に悪天候時や滑りやすい路面での安定した走行は、乗員にとって大きな安心材料となるでしょう。
商用車や特殊車両への応用も非常に期待されています。バスやトラック、バンなどの商用車では、客室・荷室のアクセス性や広さ、積載効率が重要視されますが、インホイールモーターであれば車体下部のスペースを有効活用し、これらを最大化できます。特に床面を極限まで低くできる「超低床化」が可能になるため、高齢者・車椅子利用者をはじめとする乗客の乗降性と車内の流動性、荷物の積み下ろし作業の効率を、劇的に改善できます。また工場内を走行する無人搬送車(AGV)や建設現場で用いられる特殊な作業車両、さらには農業機械など、複雑な地形や限られたスペースでの走行が求められる用途においても、各車輪を独立制御できるインホイールモーターは優れた操縦性と走破性を提供します。例えば全方向移動が可能な車両の実現も夢ではありません。
パーソナルモビリティの分野でもインホイールモーターの可能性は広がっています。高齢者向けの電動カートやシェアリングサービスで利用される小型モビリティなど、小型で取り回しやすく、かつ安定した走行が求められるシーンでは、インホイールモーターのコンパクトさと制御性の高さが大きな強みとなります。デザインの自由度も高まるため、これまでにない斬新なモビリティの登場も期待されます。
極めつけは、ロボットやドローン、そして宇宙探査機といった、一般的な車両とは異なる分野への応用です。複雑な地形を移動する必要がある探査ロボットや、精密な姿勢制御が求められるドローンなど、インホイールモーターの精密なトルク制御とコンパクトさは、その性能を飛躍的に向上させることができます。このように、インホイールモーターは自動車という枠を超え、陸上から宇宙まで幅広い分野でモビリティの常識を覆し、新たな価値を創造する可能性を秘めているのです。
◆関連解説記事<電動化で変わる自動車の動力伝達システムとカタチ・機能>
5. インホイールモーターの未来展望
インホイールモーターは自動車産業が直面する多くの課題を解決し、未来のモビリティを形作る上で不可欠な技術となる可能性を秘めています。その未来展望は、大きく分けて技術革新、システム統合、そして新たなモビリティサービスへの貢献という3つの柱で語ることができます。
(1)技術革新
技術革新の面では、インホイールモーター自体の小型軽量化と高出力化がさらに進むでしょう。モーター内部の磁性材料や導電材料の進化、冷却技術の高度化、そして高効率なパワーエレクトロニクスの開発により、より高性能でありながら、バネ下重量の課題を克服するレベルでの軽量化が実現されます。またノイズや振動の低減も重要なテーマであり、これらを最小限に抑えるための設計や制御技術が発展するでしょう。耐久性や信頼性の向上も不可欠であり、過酷な使用環境にも耐えうる堅牢な構造と、長寿命化のための技術開発が進められます。
(2)システム統合
システム統合の観点では、インホイールモーターは車両全体の制御システムとより密接に連携するようになります。現在の車両におけるESC(横滑り防止装置)やABS(アンチロックブレーキシステム)といった個別の制御機能が、インホイールモーターの独立制御と統合されることで、車両の運動性能を包括的かつ瞬時に最適化する「統合シャシー制御」へと進化します。これにより自動運転システムとの親和性が極めて高まり、車両の安全性が飛躍的に向上するだけでなく、よりスムーズで快適な移動体験を提供できるようになります。バッテリーマネジメントシステムとの連携も深まり、回生エネルギーの最大化や電力消費の最適化が図られ、航続距離のさらなる延伸に貢献します。
(3)モビリティサービスへの貢献
インホイールモーターは新たなモビリティサービスの実現に大きく貢献します。前述したような車両設計の自由度の高さは、未来の都市に求められる多様なMaaS車両の開発を促進します。例えば乗車人数や用途に応じて車体を柔軟に変化させられるモジュール式の車両や、オフィスやリビングのような空間を提供する移動体など、これまでの自動車の概念を超えたパーソナルモビリティや公共交通機関が登場するでしょう。また各車輪の独立制御は、自動バレーパーキングや狭い場所での精密な移動を可能にし、都市部の交通効率向上にも寄与します。インホイールモーターは単なる部品としてではなく、EVの進化、自動運転の普及、そしてMaaSの発展を加速させる、まさに未来のモビリティを駆動する中核技術となるでしょう。
6. まとめ
インホイールモーターは、その名の通り車輪の中にモーターを内蔵するという、これまでの自動車の常識を覆す駆動技術です。この革新的なアプローチは、駆動系部品の削減による車両設計の自由度向上、エネルギー効率の飛躍的な改善、そして各車輪独立制御による比類なき運動性能の実現という、EVにとって画期的なメリットをもたらします。バネ下重量の増加という課題は存在するものの、技術の進化によりその影響は克服されつつあり、インホイールモーターがもたらす価値はそれを上回るものです。乗用車から商用車、パーソナルモビリティ、さらにはロボットまでその応用範囲は広がり、未来の多様なモビリティを形作る基盤となるでしょう。インホイールモーターは単なる部品の進化に留まらず、EVの真のポテンシャルを引き出し、自動運転やMaaS時代における新たな移動体験を創出する、「EV進化の鍵」となる技術なのです。
7. よくある質問
Q1: なぜインホイールモーターはまだ市販の乗用車に広く採用されないのですか?
A1: 主な理由は3つあります。①本記事でも解説した「バネ下重量の増加」による乗り心地の課題、②モーターや制御装置を4つ搭載することによる「コスト高」、③車輪という過酷な環境(衝撃・水・熱)に置かれることによる「耐久性・信頼性の確保」です。これらの課題を解決するための技術開発が現在も進められています。
Q2: インホイールモーターが壊れたらどうなりますか?
A2: 1つのモーターが故障した場合でも、残りの3つのモーターで走行を継続できる可能性があります。これは、4輪を独立して制御できるインホイールモーターならではのフェイルセーフ機能(安全機能)であり、従来の駆動方式にはないメリットとも言えます。
Q3: 有名なメーカーはどこですか?
A3: 日本ではベアリング大手のNTNや、モーター大手のニデック(旧日本電産)が研究開発をリードしています。海外ではドイツのシェフラーなどが有名です。