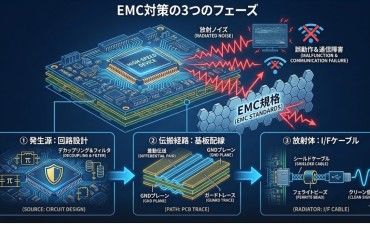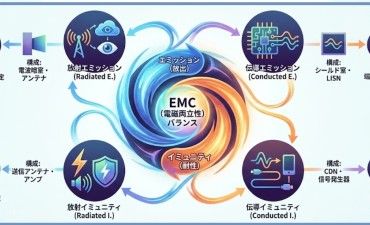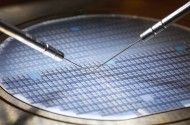
半導体・回路素子における劣化寿命の故障モード・構造因子とその予測法~半導体・回路素子の寿命を考える~
実務で役立つ実践知識習得
寿命をもつ電子部品の故障モード、電子部品に欠陥を内在した場合の寿命故障モード、寿命予測の考え方、部品ごとの寿命予測法について、様々なやり方を実務的・実践的に解説します。テキストには、事例・データを交えて数百ページにおよぶ内容となっており、事典のような活用が可能です。
※事前質問を受付ます。
【会場/WEB選択可】WEB受講の場合のみライブ配信(アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可)付き)
セミナー趣旨
この講座は電子部品、なかでも「半導体には寿命がない」そう思われている方々、あるいは形あるものいずれは壊れるのだらか寿命はあるとおもいながらもどう考えていいかわからない方々に対する講座である。半導体から回路素子、電子部品に広げて寿命のある部品ごとに故障モード、メカニズム並びに寿命予測と対策について解説する。寿命とは工場出荷から機能が果たせなくなるまでの時間、回数で、これに統計的要素を加えると50%の累積故障の点が平均寿命で、業界ごとに10%、5%,1%などといった累積故障の割合の点を保証寿命として決めている。専門的にいえば、故障率が増加に転ずる変曲点の時間、回数が寿命である。
寿命対策で最も良いのは耐久限度といわれる、いくら使っても寿命のこないストレス以下で使うこと、次いで負荷軽減設計といわれる故障の起こるストレス限界点より余裕をとったところで使うようにして寿命を延命して商品ライフの中では寿命が来ないようにすること、致命故障、重大故障の故障モードは起きないようにフールプルーフ、フェイルセーフ、フェイルソフトなどといった安全設計をすること、最後の打ち手は寿命を知って交換時期を決め、メンテナンス計画に生かすことである。寿命予測に用いる加速係数は相対値であるからまだ容易に求まるが、寿命は絶対値であるので材料、構造によって変わり、これを求めるのは容易なことではない。その予測法はアレニウス則やラーソンミラー則に限ることなく多様な手法があり、実務的で簡便な手法もある。テキストには寿命予測事例50を取り込んであり、部品ごとの寿命因子の解説もある。これらを知って自社、自分に一番あったやり方をこの講座から見出だしてほしい。
テキストに関して
本セミナーのテキストは、PDFテキストの配布となりますが、製本版のテキストを購入いただくことも可能です。
写真付きで、豊富な事例がリストアップされています。
製本テキスト資料:11,000円(税込)(別途テキスト送付先1件につき、配送料 1,100円(税別) / 1,210円(税込) を頂戴します)
※購入希望の方は、お申込み時に備考欄に「製本テキスト購入希望」と記載してください。
受講者の声
- 講師の貴重な経験、資料を伝えていただきました。テキストもしっかりしており、内容も充実しているのでありがたいです。
- 難しいテーマをわかり易く説明いただいたと思っている。自分に理論的な知識がなく、難易度は高かったが大変有意義なセミナーだった。
- 本セミナを通して電子部品の調達や現場の監査で気をつけなければいけない点を学べた
- テキストが充実しており驚きました。セミナー内でおっしゃったようにさらに読み直して理解を深めたい。
- 聞きたかった内容(電子部品毎の故障モード)がわかり満足している。個別の質問もできたので有意義でした。
受講対象・レベル
設計、試験、品質保証、クレーム処理に従事する技術者
必要な予備知識
とくに必要はありませんが、ワイブル解析の基本的なことを知っているとより理解が深まります。
習得できる知識
1)寿命をもつ電子部品とその故障モード
2)電子部品に一定の欠陥を内在した場合の寿命故障モード
3)寿命予測の考え方
4)部品ごとの寿命予測法 など
講師の長年の経験・技術データ・事例を1080頁余にわたって製本したテキスト本が残り、辞書のような形で活用できる。同一な故障モードでもアレニウス則、ラーソン・ミラー則・アイリング則・コフィンマンソン則、ノートン則、累積損傷則、水蒸気圧則などの古典的な故障モデル式だけでなく、ワイブル解析、極値解析、重回帰分析などの統計手法を活用したやりかたもあり、対数直線化、べき乗則、時間重ね合わせ則、内挿法、外挿法などの実務的なやりかたなどをいれて実に多様な予測法を習得できる。
セミナープログラム
1.基本的な考え方
(1)寿命故障率増加型故障モードと故障率一定型故障モード
(2)耐久限度・疲労限度・
(3)平均寿命・特性寿命・最低保証寿命
(4)特性保証(スペック保証)・機能保証(動作保証)・極値保証(故障モード保証)
2.代表的な寿命故障モードとその寿命の因子となる構造因子の関係
(1)IC・トランジスタ(湿度劣化寿命、ワイヤ接合劣化寿命)
(2)ダイオード(回復動作サージ劣化寿命)
(3)パワーMOSFET(ワイヤ接合破壊寿命・酸化膜劣化寿命・ダイボンド接合破壊寿命)
(4)IGBT(ダイボンド接合破壊寿命・酸化膜劣化寿命)
(5)LED(ワイヤ断線寿命・光劣化寿命・硫化劣化寿命)
(6)炭素皮膜抵抗(電食寿命、パルスサージ破壊寿命)
(7)アルミ電解コンデンサ(ドライアップ寿命、温度・電圧・リップル複合劣化寿命)
(8)フィルムコンデンサ(熱劣化寿命、湿度劣化寿命)
(9)バリスタ(サージ劣化寿命)
(10)積層セラミックコンデンサ(電極間リーク劣化寿命、高電界耐圧劣化寿命)
(11)セラミック振動子(熱応力配向劣化寿命)
(12)リレー・スイッチ(接点開閉寿命、トラッキング寿命、応力腐食寿命)
(13)コネクタ(摺動摩耗寿命)
(14)トランス、ソレノイド、コイル(加水分解劣化寿命、溶剤劣化寿命)
(12)EE-PROM(書き込み消去寿命)
(13)はんだ接続・基板(熱疲労寿命、リーク劣化寿命、クリープ劣化寿命)
3.基本的な寿命予測法
(1)ファーストフェイラーポイントにおけるワイブルパラメータmの当てはめ法
(2)対数直線化法
(3)べき乗則法
(4)極値確率紙法
(5)アレニウス則法
(6)ラーソンミラー則法
(7)ウイリアム・ランデル・フェリー則法
(8)重回帰分析による複数因子が絡む寿命の推定法
(9)材料S-Nデータをつかった寿命推定法
(10)市場回収品ないしは市場実験品からの劣化度測定データからの寿命推定法
(11)故障メカニズムに着目した損傷度比較による寿命推定法
4.部品ごとの寿命予測の主要な事例
(1)IC、トランジスタ
①湿度劣化寿命
ワイブル解析による予測法
水蒸気圧則による予測法
べき乗則による予測法(アイリング則)
②酸化膜劣化寿命
(2)整流ダイオード
①回復動作サージ劣化寿命
ワイブル解析による予測法
対数直線化による予測法
べき乗則による予測法(アイリング則)
②湿度劣化寿命
(3)パワーMOS-FE、パワートランジスタ
①ワイヤ接合破壊寿命(パワーサイクル寿命)
対数直線化による予測法
アレニウス則による予測法
べき乗則による予測法(アイリング則)
②酸化膜劣化
③ダイボンド接合劣化寿命
(3)IGBT
ダイボンド接合劣化
対数直線化による予測法(アレニウス則)
べき乗則による予測法(アイリング則)
②酸化膜劣化
(4)LED
①ワイヤ接合劣化寿命
対数直酸化による予測法
べき乗則による予測法
②熱劣化寿命
アレニウス則による予測法
べき乗則による予測法
時間重ね合わせ則による予測法(ウイリアムズ・ランデル・フェリー則)
ラーソンミラー則による予測法
②硫化劣化寿命
市場硫化腐食量からの比較解析法
(5)アルミ電解コンデンサ
①ドライアップ寿命
形状パラメータm当てはめによる予測法
アレニウス則による予測法
温度・電圧・リップル電流の組み合わせによる予測法
②封止ゴム劣化による電解液漏れ寿命
(6)バリスタ
①サージ劣化寿命
②熱劣化寿命
(7)炭素皮膜抵抗
①電食寿命
②パルスサージ寿命
(8)フィルムコンデンサ
①熱劣化寿命
時間重ね合わせ則による予測法(ウイリアムズ・ランデル・フェリー則)
②圧縮割れ劣化寿命
水蒸気圧則による予測法
(9)積層セラミックコンデンサ
①電極間リーク劣化寿命
ワイブル解析からの予測法
べき乗則からの予測法
②高電界短絡現象によるリーク寿命
ワイブル解析からの予測法
対数直線化による予測法
(10)セラミック振動子
①熱疲労寿命
インピーダンス特性と位相特性の関係
熱疲労の逆n乗則による予測法
(11)トランス、ソレノイド、コイル
①加水分解劣化寿命
ワイブル解析による予測法
べき乗分布のあてはめによる予測法
水蒸気圧則による予測法
②溶剤劣化寿命
(12)コネクタ
①摺動摩耗寿命
べき乗則による予測法
②局部電池腐食寿命
(13)リレー、スイッチ
①接点開閉寿命(接点消耗、接点転移、接点溶着)
ワイブル解析による予測法
べき乗分布のあてはめによる予測法
累積損傷則による予測法(S-N則)
重回帰分析による予測法
②酸化劣化寿命
アレニウス則からの予測法
べき乗則からの予測法
市場データ比較解析法による予測法
③応力腐食割れ寿命
(14)はんだ接続並びに基板
①はんだ熱疲労寿命
コフィン・マンソン修正則による予測法
はんだ合金材S-N曲線からの予測法
②はんだクリープ寿命
ラーソンミラー則による予測法
アレニウス則からの予測法
質疑・応答
セミナー講師
技術コンサルタント 伊藤 千秋 先生
オムロン株式会社 品質保証部長,部品技術部長等歴任後現職
制御機構部品の品質保証を15年,自動車電装部品の品質保証23年経験,品質・信頼性一筋のプロフェッショナル
この間,日本科学技術連盟 信頼性開発技術研究会 委員長などを歴任
セミナー受講料
(消費税率10%込)1名:49,500円 同一セミナー同一企業同時複数人数申込みの場合 1名:44,000円
テキスト:PDF資料(受講料に含む)
主催者
開催場所
東京都