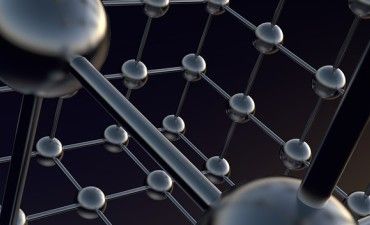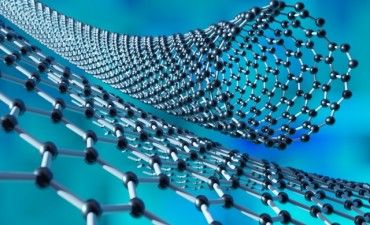MLCCの基礎構造と電極設計・信頼性評価【アーカイブ視聴対応】 ~内部電極(Ni)と外部電極の特性とBaTiO3の絶縁性 絶縁劣化メカニズム~
★2025年10月27日開講。【防衛大学・名誉教授:山本氏】に、MLCCの構造から電極材料の設計・製造方法と、信頼性評価について解説していただきます。
■本講座の注目ポイント
講演日以降でもアーカイブ視聴可能です(11/1~11/14の期間)
「積層セラミックコンデンサの基礎」「電極材料(内部電極/外部電極)」「積層セラミックコンデンサの高信頼性」について解説します。Ni内部電極と外部電極、BaTiO3の絶縁性 絶縁劣化メカニズムなど、MLCCの全容を学べる講座です。
セミナー趣旨
生成〖AI〗(人工知能)が空前のブームである。条件付き自動運転の「レベル3」、特定条件下の完全自動運転の「レベル4」といった高度な自動運転技術の普及が〖AI〗技術と相まって、自動車の自動運転はサイバー空間と現実世界(フィジカル空間)との融合を目指している。
これらの世界を実現するために、まず第一に高集積・大容量の〖CPU〗が必須であり,安定に動かす受動部品の代表である積層セラミックスコンデンサ-〖MLCC〗は小型・大容量・高性能・省電力・高信頼化が進んできた。特に、Ni内電MLCCはNi金属の低コスト化を特徴にして大容量・小型化が急激に進んだ。チップサイズは年々小型化し0201タイプ(0.2×0.1mm)10μFの実用化も始まっている。
一方、生成〖AI〗(人工知能)サーバー向けに1608タイプ(1.6x0.8mm)の100μFの大容量MLCCの量産も発表された。Ni内電MLCCの内部電極切れ(Line coverage)が信頼性・製造プロセスと絡んで、コンデンサ容量(C)を増減させることが認識され、Sn-Ni MLCC,AI―Ni MLCC等内部電極の検討されてきた。
当講座では、「積層セラミックコンデンサの基礎」「電極材料(内部電極/外部電極)」「積層セラミックコンデンサの高信頼性」に大別し、特に電極材料(内部電極/外部電極)の製造技術と、積層セラミックコンデンサの高信頼性を詳細に解説する。
習得できる知識
①積層コンデンサ (MLCC) 材料の基礎から応用まで
②MLCCの高積層・高容量の技術
③MLCCの内部電極・外部電極の全て
セミナープログラム
【講演のポイント】
MLCCの高積層化技術と、それに伴って生じるトラブル、解決方法を歴史から始まって最新情報まで解説する。
【講演キーワード】
積層コンデンサ (MLCC) 材料の基礎から応用まで
MLCC原料から完成体まで
MLCCの高積層・高容量の技術
積層の技術、その問題点
MLCCに用いられる電極,内部電極・外部電極
【プログラム】
1. 積層セラミックスコンデンサ―(MLCC)とは
1.1 移動通信システムの進化
1.2 自動運転のレベル分け,AIとの結合
1.3 MLCCの応用例(民生用,車載用)
1.4 MLCCの温度特性:車載用/生成AIには
1.5 Class I vs Class II MLCC の温度特性/DC特性/温度特性
1.6 スマートホンに搭載される電子部品の個数MLCCの自動車搭載個数, MLCCの世界ランキング
1.7 主要なコンポーネント供給プレーヤー,グラビア印刷法の採用でMLCCの世界ランキング変わる?
1.8 コンデンサなのに,等価回路ではLCR, 低ESL化の試み,ノイズ除去に重要
2. 積層セラミックコンデンサの基礎
2.1 積層セラミックスコンデンサの構造
2.2 材料から見たBaTiO3+希土類+アクセプタ+固溶制御材
2.3 信頼性向上/希土類添加BaTiO3系誘電体の開発
2.4 希土類を使わないMLCCの開発
2.5 MLCCの小型化、容量密度の進化、誘電体層薄層化の進化
2.6 積層セラミックスコンデンサの進展方向
2.7 大容量MLCCの(100μF)の実現 誘電体層・電極厚みの変遷
2.8 Ni-MLCCの製造プロセス、グリーンシートの技術動向
2.9 高信頼性MLCCに必要なこと、コア・シェル構造の重要性
2.10 コア・シェル構造とプロセスの関係 コア・シェルの構造制御
2.11 薄膜用MLCCのBaTiO3に求められる特性(水熱合成法)
2.12 固相法によるBaTiO3の微細化, 粉砕技術,ビーズミル (解粒),分散,分級
2.13 水蒸気固相反応法、BaTiO3の低温反応、水で加速する室温固相反応 (BaTiO3),Cold Sintering
2.14 粉砕と分散とは、メデイアのサイズ、メデイアの材質
3. 電極材料(内部電極/外部電極)
3.1 積層デバイスに用いられる電極,Ni内部電極
3.2 Ni内部電極向上のために,
3.3 高積層・高容量MLCCのためのNi内部電極用Ni微粒子、供材
3.4 2段焼成法のNi内部電極の効果,カバーレッジの向上
3.5 Ni内部電極の成形メカニズム (膜断面の観察), Ni内部電極の連続性 (カバーレッジ) 向上のメカニズム
3.6 Ni電極向上のために (Ni微粒子径、粒度分布、供材添加), Ni微粒子への添加効果 (Ni-Cr, Ni-Sn)
3.7 MLCC内部電極のプラズマ法によるNi微粒子作製
3.8 Ni内部電極の連続性の向上
3.9 MLCCの内部電極/低焼成収縮率 (Delaying Low Temperature Shrinkage)
3.10 Ni電極の酸化/Ni層とBaTiO3層の界面輸送
3.11 Sn添加Ni電極の低焼成収縮率
3.12 Al添加,Zr添加,Ni電極の低焼成収縮率
3.13 プラズマ法によるNi粒子の作成,特性評価
3.14 MLCC法の内部電極/グラビア印刷法
3.15 MLCC外部電極, Cu/Ni/Sn. Cu/Resin/Ni/Sn, Cu/Ni/Sn
3.16 MLCCのCu外部電極用ガラス
4.積層セラミックコンデンサの高信頼性
4.1 BaTiO3の絶縁性 絶縁劣化メカニズム
4.2 MLCCの信頼性評価
4.3 導電体の導電メカニズム
4.4 リーク電流―時間依存性
4.5 ショットキー電流とプールフランケル電流
4.6 Cu-MLCCとNi-MLCCのリーク電流特性の違い
4.7 劣化時の電流の変化について
4.8 熱刺激電流/酸素欠陥の評価法
4.9 交流インピーダンス・等価回路法による評価
4.10 圧電応答顕微鏡による表面電位測定(KFM)
4.11 MLCC素子断面のKFM評価(抵抗値の可視化,電位分布,酸素欠陥の移動)
4.12 高信頼性MLCCの材料設計に向けて(電極界面,粒内,粒界)
5.まとめ
5.1 付記1) 最新のMLCC研究
5.2 付記2)現象論的熱力学を用いたBaTiO3の特性シミユレーション
5.3 各社のMLCC発表
【質疑応答】
セミナー講師
防衛大学校 名誉教授、大阪公立大学 客員教授 工学博士 山本 孝 氏
研究・業務
1. 日韓セラミックスセミナ-日本側委員(2009~)
2. 強誘電体応用会議実行委員会委員顧問(2008~)
3. ファインセラミックス標準化EC2委員長(1989~)
4. ISO/TC206 委員(2015~)
5. 加藤科学振興会評議委員(1990~)
6. 電子セラミックス・プロセス研究会評議委員長(2007~)
その他 所属・役職
大阪府立大学 客員教授/研究員
略歴
1980年京都大学大学院博士課程修了
1981年防衛大学校助手(電気工学教室)
1984年9月カルフォルニア大学・バ-クレ-校
ロ-レンツ・バ-クレ-研究所客員研究員
1987年防衛大学校講師(電気工学教室)
1988年防衛大学校助教授(電子工学科)
1994年防衛大学校教授(電気工学科)
1999年防衛大学校教授(通信工学科)
2014年防衛大学校定年退職、
2014年大阪府大客員研究員(2014年~)
2014年防衛大学校名誉教授
2014年大阪府大客員教授(2014年~)
2017年同志社大学非常勤講師(2017年~2019年)
2022年大阪公立大客員教授(2022年~)
セミナー受講料
●1名様 :49,500円(税込、資料作成費用を含む)
●2名様以上:16,500円(お一人につき)
※受講料の振り込みは、開催翌月の月末までで問題ありません
受講料
49,500円(税込)/人