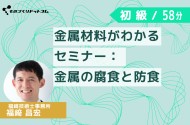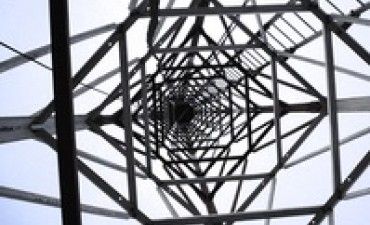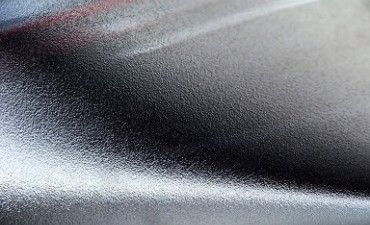金属材料の腐食は、設計・製造・保守のあらゆる現場に潜むリスクです。
本セミナーでは、腐食現象を支配する電気化学の本質を基礎から丁寧に解説し、鉄・ステンレスからチタン・銅まで幅広い金属の腐食と防食技術を体系的に学習できます。現場で役立つ確かな理論と実務対応力を養える、腐食対策の決定版セミナー!!
【会場/WEB選択可】WEB受講の場合のみ,ライブ配信/アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可)
セミナー趣旨
金属材料の腐食は、機器設計における構造設計,材料選定は言うに及ばず操業時の腐食トラブルに対する対応方針決定まで広範囲で非常に重要な課題となっています。しかし、これらに関わる腐食科学を理解するには材料の知識のみならず溶液化学の知識,さらには腐食過程そのものが電気的要素を含んでおりこれらの総合的な知識が必要となってきます。また、相互の関連性が複雑に見えることが腐食現象理解の妨げとなっているものと思われます。
本セミナーにおいては、金属の腐食科学を理解する上で最も重要な電気化学を基礎から平易に説明することによりその本質を学んでもらいたいと考えております。その上で,金属材料の耐食機構を明確にし腐食がなぜ起こるのかを金属材料の種類を問わず理解することを目指します。説明には鉄系金属(ステンレス鋼を含む)を主体に行いますが,後半ではアルミニウム,チタン,銅などの他金属との比較も行い得られた知識の拡大と理解の深化を目指します。また、防食技術についても会得した腐食理論と関連付けながら述べたい考えております。
腐食の一般的な教科書では記載されていないような基礎的なことから出発し腐食科学の本質に迫るセミナーです。個別材料の腐食課題の解決セミナーではありませんが、業務上金属材料の腐食問題を扱う必要のある方あるいはさらに深い知識を得て応用範囲を広げたいと考えておられる方には、基盤的な考えが身につく最適なセミナーとなると考えております。
受講対象・レベル
金属材料の腐食が課題となる設備設計,機器設計に携わる設計者
工場の製造エンジニア,工場保守業務に携わってる方
顧客との技術的な会話が必要な技術営業職の方
研究職であっても腐食の知識を深めたいと考えておられる方
必要な予備知識
腐食の基礎から説明しますので,腐食の専門的予備知識は必要ありません。
ただ、腐食の基本的理論を理解するには高校での化学や物理の知識があれば理解しやすいと考えます。
習得できる知識
1)腐食科学のベースとなる電気化学の知識
2)電位,pH,など腐食に関わる最も重要な因子の理解
3)腐食形態とその腐食理論
4)防食方法の考え方 など
セミナープログラム
1.腐食・防食技術への取組み
1−1 実務で直面する腐食問題
1−2 金属の安定性とは(熱力学での自由エネルギーの大小)
2.元素とイオン化 (酸化して溶液中に溶け出すとは)
2−1 元素周期表とイオンの価数
2−2 化学溶解と腐食
2−3 腐食に関わる自由エネルギー変化(電位と電位差)
2−4 イオン化傾向
3.電気化学の基礎
3−1 電位-pH図
3−2 アノードとカソード(酸化還元電位との関係)
3−3 分極曲線と電位ーpH図
4.金属腐食の基礎
4−1 腐食の考え方(局部腐食と混成電位)
4−2 金属/溶液の界面反応と不働態化
4−3 加水分解
4−4 不働態皮膜破壊(Cl-,H+)
4−5 カソード反応の重要性
4−6 自然水の電位分布と酸素が関与する腐食
4−7 微生物が関与する腐食
4−8 材料側の課題(ステンレスの溶接部)
5.各種金属の腐食
5−1 鉄
5−2 ステンレス鋼
5−3 アルミニウム,チタン,銅
6.防食技術
6−1 耐食材料選定と防食
6−2 防食設計
6−3 環境制御
7.まとめ
質疑・応答
セミナー講師
元 日鉄ステンレス株式会社 シニアフェロー 梶村 治彦 先生
博士(工学),腐食防食専門士(腐食防食学会認定)
1981年 大阪大学大学院工学研究科金属材料工学専攻博士課程前期 修了
1981年 住友金属工業(株)入社
1992年 博士(工学):大阪大学
2003年 新日鐡住金ステンレス(株)に転籍
2014年 腐食防食専門士(腐食防食学会認定)
2021年 日鉄ステンレス(株)退職
受賞歴
1990年 腐食防食学会,論文賞
2004年 スガウェザリング技術振興財団,特別技術功労賞
2012年 日本金属学会,技術賞
2017年 腐食防食学会,論文賞
2018年 腐食防食学会,論文賞
2023年 腐食防食学会,論文
著作
論文,解説記事 121編(原著論文41編)
書籍
「ステンレス鋼の科学と最新技術」-ステンレス鋼100年の歩み-,ステンレス協会(細井祐三監修)(2011)
“Environmental Degradation of Advanced and Traditional Engineering” Edited by L.H.Hihara, R.P.I.Adler and R.M.Latanision, CRC Press(2014)
所属学会
腐食防食学会
セミナー受講料
(消費税率10%込)1名:49,500円 同一セミナー同一企業同時複数人数申込みの場合 1名:44,000円
※WEB受講の場合、別途テキストの送付先1件につき、配送料1,210円(内税)を頂戴します。
テキスト:製本資料(受講料に含む)
受講料
49,500円(税込)/人
前に見たセミナー
関連セミナー
もっと見る関連教材
もっと見る関連記事
もっと見る-
レアアースレス・モーターとは?レアアースフリーの衝撃、環境と経済を変えるモーターの進化論
【目次】 現代社会はモーターなしには成り立ちません。スマートフォンから電気自動車、産業用ロボットに至るまで、私たちの生活のあらゆる側... -
DEHPとは?危険性や健康への影響、身近な製品例と安全な代替品まで解説
【目次】 DEHP(フタル酸ジエチルヘキシル)、この耳慣れない化学物質が、私たちの日常生活に深く根ざしていることをご... -
HVDC(高圧直流送電)とは?HVDCが描く未来、再エネ社会を繋ぐ革新送電
【目次】 現代社会において、電力は私たちの生活を支える不可欠なインフラです。しかし、その電力供給のあり方は、気候変動問題への対応やエ... -
撓鉄(ぎょうてつ)とは?1200年の歴史が生んだ日本の鍛鉄技術、その美学と技能継承の課題を解説
【目次】 日本には、1200年以上の時を超えて受け継がれる「撓鉄(ぎょうてつ)」という独自の伝統技術が存在します。この技術は、熱した...