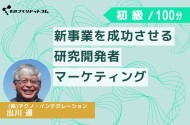【中止】顧客経験価値を創造する商品開発入門
※オンライン会議アプリZoomを使ったWEBセミナーです。ご自宅や職場のノートPCで受講できます。
セミナー趣旨
最終消費者であれ法人であれ、レンタルリース、サブスクリプション、シェアリングエコノミーなどの普及で、モノを「買う」という行為が少なくなり、サービスを通じてモノの価値を利用することに変化してきています。
商品企画もかつて技術開発による物理的、機能的なモノやのサービスの企画が主体で、顧客が購入してくれること、つまり売上・利益に重点が置かれていましたが、これからは、顧客がどのような場面で、どう利用し、ベネフィットを感じるかといった顧客側の利用に重点を置かなければなりません。
顧客が商品を利用し続けるには、顧客経験価値が常に高くなくてはならず、顧客との継続した接点と、必要な状況で必要なモノやサービスを提供するビジネスモデルが必須となります。またAI、IoTなどのDXの発展でその環境は成熟してきています。
以上のような点から、これまでの技術開発に起点をおいた商品開発のあり方は大きく変革しなければならず、独自の顧客経験価値を生み出す商品開発でなければなりません。
本セミナーは、日本企業が得意とする技術を重視しつつも、その強みを、顧客経験価値をベースにした新たな商品開発手法に変革するためのものです。
受講対象・レベル
・研究開発部門
・商品企画開発部門、マーケティング戦略部門、設計開発部門
・新製品・新事業開発部門、M&A/アライアンス部門、市場調査部門
・製造技術部門、技術営業部門
・知的財産部門、技術調査部門
・大学の研究者、産学協同部門
経験に関係なくどなたでも受講できます。
習得できる知識
(1) 顧客経験価値の基本構造と仕組みが理解できます
(2) 自社の商品開発を前提とした効果的な顧客経験価値の創造ステップが学べます
(3) 顧客経験価値創造のための商品開発が、これまでの技術を起点とした商品開発と大きく異なることが理解できます
(4) 顧客経験価値開発を進めていく上での個人と組織の能力開発の方法が理解できます
セミナープログラム
1.顧客は何を購入しているのか
1-1. サブスクリプション、シェアリングエコノミーで顧客が購入しているのは何か?
1-2. 売れる商品が変化している「なりたい自分になれるもの」「自分の好きな空間」
1-3. 予測技術が進みライフステージを意識する消費が成長している
1-4. 顧客の価値観変化についていけていない既存業界
1-5. AI、IoTなど、サイバー空間が普及し刻々と変化する商品の形態とその開発方法
1-6. 個人の主観で考えたものが顧客の欲しいものになることが多い
1-7. 顧客は何を購入しているのか
1-7-1. ユーザーエクスペリエンス“顧客経験価値”とは
1-7-2. 経験価値の入り口はSense(感じる)とFeel(思う)、そしてThink(考える)、Act(行動する)、Relate(繋がる)へ
1-7-3.「商品を開発する」から「顧客と共創する」へ
2.コトづくりのための「顧客経験価値」の理解
2-1. まず「商品」の定義を変えろ
2-2. コトづくりのための「顧客経験価値」の理解
2-2-1. 「顧客経験価値」とは顧客の個人の価値観や感情、感性に働きかける
2-2-2. 「顧客経験価値」ワンウェイではなく双方向コミュニケーションである
2-2-3. シュミットの経験価値モジュールとは
2-2-4. 売手の視点の「顧客提供価値」「商品価値」と顧客個人視点の「顧客経験価値」
2-3. 「顧客経験価値」の詳細構造と仕組みを理解する
2-3-1. 事業活動と顧客経験価値の生成・変化
2-3-2. そもそも顧客価値とは何か?
2-3-3. 顧客経験価値と直接的商品価値に分ける
2-3-4. 時間的視点でみた顧客経験価値
2-3-5. 優れた顧客経験価値とは「夢にあふれた顧客の経験ストーリー」である
2-4. インパクトある顧客経験価値とは
2-4-1. 新しい独自の意味を与えてくれるもの
2-4-2. 従来のやり方、発想を破壊するもの
2-4-3. 物語としての面白さ、独自性があるもの
2-4-4. 人や社会、地球環境視点での普遍性
3.顧客経験価値のための商品開発の7つのコンセプト
3-1. これまでの商品開発と顧客経験価値のための商品開発の違い
3-1-1. コンセプト1:商品の開発ではなく意味の開発を目指す
3-1-2. コンセプト2:新しい意味を作り出せそうな異業種でプロジェクトを組む
3-1-3. コンセプト3:調査分析からではなく、個人の主観からスタートさせる
3-1-4. コンセプト4:世の中の変化の本質をつかむ
3-1-5. コンセプト5:計画よりも身近なことで実証を繰り返す
3-1-6. コンセプト6:アイデアで終わらずにコンセプト化する
3-1-7. コンセプト7:ストーリーとしての面白さを妥協しない
4.顧客経験価値のための商品開発の全体設計と準備、事業企画開発フェーズ
4-1. 顧客経験価値のための商品開発の全体像とフェーズ
4-2. 準備フェーズ
4-2-1. 商品企画開発プロジェクトの背景、目的、目標・成果の設定
4-2-2. 商品企画開発プロジェクトの組織体制づくり
4-2-3. プロジェクトの実施スケジュールと予算
4-3. 事業企画開発仮説フェーズ
4-3-1. 事業企画開発仮説とは何か
4-3-2. 事業企画開発仮説の4つの視点の具体的な内容と発想
4-3-2-1. コアコンピタンスの視点での仮説
4-3-2-2. 市場イノベーションの視点での仮説
4-3-2-3. 顧客経験価値仮説の視点での仮説
4-3-2-4. 商品企画仮説の視点での仮説
4-3-3. 効果的な事業企画開発仮説のための3つの方法
5.商品企画開発仮説フェーズ
5-1. 機能とコスト中心の商品企画開発から脱却するために
5-2. 顧客経験価値を企画するための6つの手法
5-3. デザインシンキング
5-4. タウンウォッチング
5-5. 現場観察(エクスペリアンス調査)
5-6. 異業種アイデアソン
5-7. ペルソナデザイン
5-8. カスタマーエクスペリエンスマップ
5-9. 顧客経験価値の分析と仮説まとめ
5-10. 商品アイデア発想
6.仮説検証フェーズ
6-1. 2つの仮説検証方法
6-2. マーケティングリサーチ
6-2-1. 新たなマーケティングリサーチの目的とは
6-2-2. マクロトレンド
6-2-3. エコシステム(業界構造)分析
6-2-4. 有望市場分析
6-2-5. 有望市場とターゲット市場の関係
6-2-6. ターゲット市場分析
6-2-7. ターゲット市場での競合分析
6-3. PoC(実証実験:Proof of Concept)
6-3-1. PoC(Proof of Concept)の計画
6-3-2. 顧客経験価値重視の商品企画開発におけるPoCの位置づけ
6-3-3. PoCの企画方法
6-3-4. PoCの実施
6-3-5. PoC結果分析
7.事業戦略構想書作成フェーズ
7-1. 事業戦略構想とは
7-2. 事業のパーパス、ビジョン
7-3. 顧客経験価値、商品企画仮説、ビジネスモデル仮説
7-4. 仮説検証:マーケティングリサーチと実証実験(PoC)結果
7-5. SWOT分析と事業成功の要因
7-6. ターゲット顧客と顧客経験価値戦略
7-7. エコシステム・ビジネスモデル戦略
7-8. 顧客経験価値開発のためのマーケティング戦略
7-9. 商品開発計画
7-10. マーケティング開発計画
7-11. 技術開発計画
7-12. 事業開発ロードマップ
7-13. 事業計画とリスク分析、対応
7-14. 当面のアクションプラン
7-15. 実行組織体制
8.イノベーティブな商品企画開発実践するためのトレーニング
8-1. 個人の能力をアップさせる
8-1-1. 顧客経験価値を創造できる人=クリエターエコノミーの時代
8-1-2. 顧客経験価値=「意味」を創り出すこととは
8-1-3. 自分の生き方、価値観を明確に持ち、人からも学ぶ
8-1-4. Sense(知覚)、Feel(感情)、デザイン力を鍛える
8-1-5. 社外ネットワークを積極的につくり、活用する
8-1-6. 社会課題を考え、実際に行動する
8-1-7. ヒット商品、競合企業、製品のベンチマーキングを行う
8-1-8. プロセスを重視する
8-1-9. システムシンキング力を鍛える
8-1-10. 小さく始める、スタートアップを経験する
8-1-11. 「失敗」という概念をなくする
8-2. 組織能力をアップさせる
8-2-1. 商品開発の基本ツールを整備し、実践で使えるようにする
8-2-2. トレーニングも兼ねた実践商品開発研修を定期的に実践する
8-2-3. 誰もが挑戦できる自由な商品企画開発の場を設定する
8-2-4. 仕事の中で商品企画開発のために自由に使える時間を確保する(10%から15%)
【質疑応答】
セミナー講師
(株)ニューチャーネットワークス 代表取締役 高橋 透 氏
≪略歴≫
・1987年上智大学経済学部経営学科卒業
・同年旭硝子株式会社(現AGC)入社、セラミック事業マーケティング、消費財新事業開発、広告宣伝担当
・1993年大手コンサルティング会社入社
・1996年株式会社ニューチャーネットワークス設立 代表取締役就任
・2010年より上智大学非常勤講師(経済学部:コンセプトメイク、全学共通:グローバルベンチャー、理工学部:ものづくり講座)
・2016年ヘルスケアAIoTコンソーシアム 理事
≪主な訳書、著書≫
「顧客経験価創造のための商品開発入門」(著、中央経済社、2023年6月)「デジタル異業種連携戦略」 (著、中央経済社、2019年) 「技術マーケティング戦略」(著、中央経済社、2016年)「勝ち抜く戦略実践のための競合分析手法」 (著、中央経済社、2015年)「90日で絶対目標達成するリーダーになる方法」(著、 SBクリエイティブ、2014年) 「GE式ワークアウト」(デーブ・ウルリヒ他著、共訳、日経BP、2003年) 「ネットワークアライアンス戦略」(共著、日経BP、2011年) 「事業戦略計画のつくりかた」(著、PHP研究所、2006年 )、「図解でわかる・技術マーケティング」(共著、JMAM、2005年)、「研究開発テーマの評価と中止/撤退判断の仕方」 (共著、技術情報協会編、2021年)、「共同研究開発の進め方、契約のポイント」(共著、技術情報協会編、2020年)などがある。日本能率協会「JMA MANAGEMENT Vol.8 No.5」に『「デジタル異業種連携」を成功させるために』寄稿。技術情報協会「月刊 研究開発リーダー」など寄稿多数。
日経BP社プレミアムサイトに5年間、日経産業新聞WEB「企業マネジメント最新トレンド」へコラム執筆。弊社コラムサイト「グローバル・エイジ」にてコラム執筆多数。
セミナー受講料
49,500円(税込、資料付)
■ セミナー主催者からの会員登録をしていただいた場合、1名で申込の場合38,500円、
2名同時申込の場合計49,500円(2人目無料:1名あたり24,750円)で受講できます。
(セミナーのお申し込みと同時に会員登録をさせていただきますので、
今回の受講料から会員価格を適用いたします。)
※ 会員登録とは
ご登録いただきますと、セミナーや書籍などの商品をご案内させていただきます。
すべて無料で年会費・更新料・登録費は一切かかりません。
メールまたは郵送でのご案内となります。
郵送での案内をご希望の方は、備考欄に【郵送案内希望】とご記入ください。
受講について
Zoomを使ったWEB配信セミナー受講の手順
- Zoomを使用されたことがない方は、こちらからミーティング用Zoomクライアントをダウンロードしてください。ダウンロードできない方はブラウザ版でも受講可能です。
- セミナー前日までに必ず動作確認をお願いします。
- 開催日直前にWEBセミナーへの招待メールをお送りいたします。当日のセミナー開始10分前までに招待メールに記載されている視聴用URLよりWEB配信セミナーにご参加ください。
- セミナー資料は開催前日までにお送りいたします。
- 無断転載、二次利用や講義の録音、録画などの行為を固く禁じます。
受講料
49,500円(税込)/人