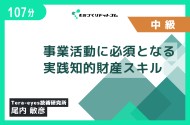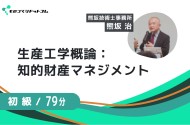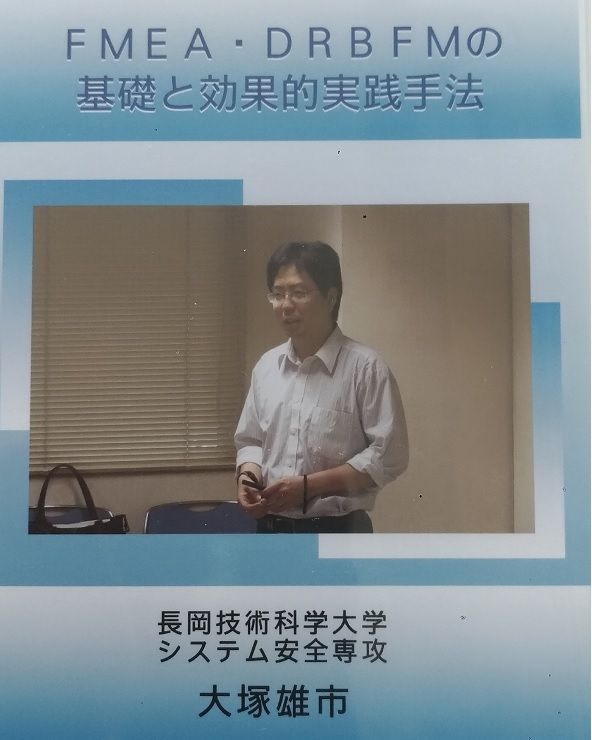![[入門者OK]<br/>この分野の初歩から説明します 初心者向けセミナーです](https://assets.monodukuri.com/img/beginner-mark.png?d=0x0) 特許の読み方、調査のコツと他社の特許網を回避した製品開発のポイント【Live配信セミナー】
特許の読み方、調査のコツと他社の特許網を回避した製品開発のポイント【Live配信セミナー】
研究者、技術者は最低限これだけは知っていてほしい!
効率的で効果的な知財実務のポイントをじっくり学びます!
日時
【第1講】2021年6月4日(金)13:00~16:00
【第2講】2021年6月8日(火)13:00~16:00
【第3講】2021年6月11日(金)13:00~16:00
【第4講】2021年6月18日(金)13:00~16:00
セミナープログラム
<6月4日(金)13:00〜16:00>
【第1講】 特許侵害の判断基準・対応方法と特許網を回避した製品開発のポイント
【講演趣旨】
他社の特許を侵害した場合には、差し止め請求や損害賠償請求などで訴えられ、事業に多大な支障が生じ、お客様に迷惑をかけ、多大な損害賠償を払わされるリスクがあります。 思いがけず、他社から特許侵害しているという話が来ることもあります。その場合には、本当に侵害しているかどうか(特許の請求の範囲と製品とを対比して技術的範囲に属するか否か)の調査・判断と当該特許が有効かどうか(当該特許に無効理由がないかどうか)の調査・判断が重要です。 また、侵害予防策として、他社特許侵害チェックを定常的に組織的に行う体制・運用が必要です。 本講座では、これらの侵害対応と侵害予防策について、具体的に何をしたらいいのか具体的に解説したうえで、これらの活動を通じて他社の特許網を回避してヒット商品を開発する方法についても解説します。
【講演項目】
- 特許権侵害が及ぼす自社事業へのリスク
- 直接的影響(差止、高額化する損害賠償、信用回復措置、不当利得返還など)
- 間接的影響(ガバナンス、ブランド信用棄損、世間の批判など)
- 特許権侵害の判断
- 特許の権利範囲の解釈
- 権利解釈の例
- 特許権侵害の判断に影響を与えるもの
- 例外的に特許権侵害となる場合
- 警告書が届いた場合の対応方法
- 特許権者と特許権の有効性の確認
- 特許権侵害の有無の確認
- 特許発明の実施が可能な権利の有無の確認
- 問題となっている特許の無効理由の有無の確認
- 自社事業への影響の検討(売上、損害額、事業計画への影響)
- 自社特許の検討(対抗できる特許があるか?)
- 警告書に対する対応方針の検討(回答、訴訟準備、無効審判・・・)
- 侵害論の検討方法
- 文言侵害の検討
- 侵害疑義製品(イ号)の特定
- 特許請求の範囲との対比
- 間接侵害の検討
- 均等侵害の検討
- 先使用権の検討
- 侵害を回避する仕様変更の検討
- 文言侵害の検討
- 無効論の検討方法
- 審査プロセス確認、審査官判断の妥当性検討
- 審査における先行技術調査の妥当性検討
- 外国出願のある場合は外国での審査状況検討
- 特許庁が行う通常の検索では調査しない範囲で調査を実施
- 非特許文献の探し方
- 特許庁が行う通常の検索では重視しない項目で調査を実施
- 周知・慣用技術、技術常識を調査(実物入手、専門家へのコンタクトなど)
- 記載要件違反の検討
- 数値限定発明への対応法
- 用途発明への対応法
- 侵害予防策としての他社特許侵害チェック体制・運用方法
- 競合他社動向の監視(技術動向、特許動向、障害特許の早期発見)
- 重要事業分野及び関連分野の特許監視(特許動向、障害特許の早期発見)
- 障害特許の早期発見の仕組みと運用
- 障害特許の社内周知化・対応策検討の仕組みと運用
- 外部専門家とのコネクション
- 他社の特許網を回避してヒット商品を開発する方法
- 事例紹介
- 他社特許網の正確な把握
- 他社特許網の穴の見つけ方
- 他社特許網の回避のコツ
- 先発メーカーの商品を凌ぐ商品を開発するコツ
【質疑応答】
<6月8日(火)13:00〜16:00>
【第2講】発明提案書の書き方と特許明細書チェックのコツ
【講演趣旨】
特許出願を契機に、自らの発明に気づき、発明を自らの手で育て上げることが、研究者・技術者自身の大きな財産となります。限られた時間で的を射た「発明提案書」や「特許明細書」を書くことは創造活動そのものとも言えます。
演者は長年にわたり、研究者および管理者として発明創出、出願、知財組織作りに従事してきました。その中での数多くの提案書や明細書の作成や添削チェックの経験と実績をベースに、「発明提案書」を書くのが"苦手・嫌い"という研究者・技術者が、苦手意識を払しょくし、「発明提案書」に取り組みやすくなり、短時間で且つ質の高い「発明提案書」を書けるようになるポイント、及び、事業に貢献するという視点での「発明提案書」の書き方を解説します。
また、研究者・技術者が、外部弁理士が書いた「特許明細書」を的確にチェック・評価し、広くて強い特許を取得することができるようになるための基礎知識とノウハウ(コツ)について解説します 。
【講演項目】
- 発明とは?
- 発明とは?
- 特許される発明とは?
- 質の高い発明とは?
- 良い発明とは?
- 権利取得には、発明の本質の把握が大切
- 権利取得には、先行技術との対比が大切
- 取得したい権利範囲と取得できると考える権利範囲
- 事業に貢献する発明提案書作成のポイント
- 発明(提案したい技術)の本質を把握し、取得したい権利範囲を想定していること
- 発明(提案したい技術)が従来知られていない技術で先行技術と構成の差があること
- 発明は「課題」「作用効果」「構成」がセット
- 先行技術と構成の(微)差があれば、「課題」「作用効果」の違いの説明の仕方が鍵
- 発明の名称、技術分野の考え方
- 発明の背景技術、従来技術、先行技術文献の説明の仕方
- 発明の概要の説明の仕方
- 発明のポイント、発明が解決しようとする課題、課題を解決するための手段、発明の効果の説明の仕方
- 発明を実施するための形態、実施例の説明の仕方
- 図面の説明の仕方
- 産業上の利用可能性の説明の仕方
- 会社の事業戦略上、R&D戦略上の位置付けの説明の仕方
- 知財部、外部弁理士への説明の仕方
- 広くて強い特許を取得するための特許明細書等のチェックポイント
- 特許請求の範囲(クレーム)のチェック
- 新規性
- 進歩性
- 侵害立証性
- 回避困難性
- 不要な限定の有無
- 発明のカテゴリーの妥当性
- 明細書のチェック
- 発明思想の説明の明確性、十分性
- 個々の構成要件の説明の十分性
- 課題、効果の関係性
- 用語・表現(定義、誤記、用語の段階的記載)
- 数値規定(数値範囲の段階的記載、数値範囲の上下、数値範囲の理由)
- 記載不備(36条関係:実施可能要件、サポート要件、明確性要件)
- 将来の補正を考慮した記載
- 実施例、比較例の整合性(クレームと実施例・比較例、課題・作用効果と実施例・比較例、ベストモードと実施例・比較例)
- 図面・表のチェック
- 知財部、外部弁理士とのコミュニケ—ションの取り方
- 特許請求の範囲(クレーム)のチェック
【質疑応答】
<6月11日(金)13:00〜16:00>
【第3講】 研究者・技術者のための特許の"効率的な"読み方
【講演趣旨】
特許の読み方は、特許を読む目的によって異なります。自社技術について権利化を考えているときと、自社ビジネスが他社特許権に侵害する可能性について判断しようとするときでは全く異なることは言うまでもありません。目的に応じて、効率よくかつ適切に特許を読めるようになることが重要です。また、特許を『効率的』に読むことが出来ると、調査も効率的にできるようになります。更に、他社特許の抜け道が見えてきて、新しいアイデア、発明に繋がっていきます。
また、『効率的』というのは、スピードが上がれば良いという意味でなく、発明のポイントを正しく、早く理解するということです。スピードが早くなっても、発明の本質を理解していないとせっかくの努力が無駄になってしまいます。 この目的に応じて効率よくかつ適切に特許を読める能力を身につけるには、本来はかなりの時間を要しますが、本講座では、短時間で習得できる読み方のコツを紹介します。
【講演項目】
- 効率的に特許を読むための基本
- 発明とは
- 特許要件(新規性 進歩性 記載要件等)
- 公報の種類(特許公開公報、特許公報等)
- 特許出願に必要な書類5種類(願書、特許請求の範囲、明細書、図面、要約書)
- 「発明の本質」を考える重要性
- 特許を読む
- 特にしっかりと読む必要がある部分(特許請求の範囲、課題、効果)
- 【特許請求の範囲】と【課題を解決するための手段】
- 【発明が解決しようとする課題】と【発明の効果】
- 【発明を実施するための形態】と【実施例】
- 【実施例】、【比較例】、【参考例】、【試験例】の違い
- 読み方を考える(速度を上げる、正しく読む)
- 特許を読む目的と目的に応じた効率的な特許の読み方
- 発明のヒントを見つける
- 自社技術を特許化し得るかを検討する(アイデアシート作成前の先行技術調査)
- 自社技術を特許化し得るかを検討する(出願前の先行技術調査)
- 自社技術を特許化し得るかを検討する(審査請求時の先行技術調査)
- 自社ビジネスが他社特許権を侵害しないか検討する
〜権利範囲の認定・解釈、侵害有無の判断〜 - 邪魔な他社特許が無効化できないか検討する
〜通常の先行技術調査では抽出できない先行技術の見つけ方〜 - 他社特許、特許網の弱点を見つける
- 他社特許出願を参考にした対抗出願を検討する
- 他社特許パテントポートフォリオを作成する
- IPランドスケープに利用する
【質疑応答】
<6月18日(金)13:00〜16:00>
【第4講】 効率的な特許調査(先行技術調査、侵害予防調査、無効資料調査)のコツ
【講演趣旨】
自らのアイデアや研究開発担当者のアイデアを、発明として特許出願すべきかを検討する際に発明の新規性・進歩性を調査すること(先行技術調査)が必要となります。 製品やサービスを製造販売する前には、他社特許の調査(侵害予防調査)が必須になります。邪魔な他社特許が見つかった場合には、邪魔な他社特許を無効化できないか検討する必要があります。 研究者・技術者が効率的な特許公報の調査法を身に付ければ、特許調査に費やす時間を短くすることができ、権利化が必要な発明か、事業化時に障害となる他社特許がないか、短時間で見極めることができ、邪魔な他社特許を効率的に無効化できる可能性が広がります。
本セミナーでは、先行技術調査、侵害予防調査、無効資料調査について、調査の手順やコツを、わかりやすく説明します。
【講演項目】
- 特許の基礎
- 特許とは
- 特許情報でわかること
- 特許調査の基礎
- 検索と調査
- 特許調査の目的、
- 技術動向調査
- 先行技術調査
- 侵害予防調査
- 無効資料調査
- 検索における「ノイズ」と「漏れ」
- 漏れが少なくノイズも少ない検索で、公報査読にかかる労力を圧縮
- 漏れが少なくノイズが多い検索で、公報査読の労力を人海戦術でカバー
- 漏れは多いがノイズは少ない検索でも大丈夫な場合
- 漏れが多くノイズ多い検索でも大丈夫な場合
- 技術者の特許調査
- 日常的な監視
- 技術開発のヒント探し
- 権利関係調査の予備調査
- 特許審査時に行われる先行技術調査
- 調査対象となる発明の認定
- 検索
- サーチの観点からの発明の特徴点の抽出
- サーチと特許要件判断の方針の決定
- サーチ範囲の決定
- 検索式の構築
- スクリーニングとサーチ方針の変更
- 引用例の認定
- 対比
- 判断
- 効率的な特許調査のコツ
- 目的別の調査方針
- 技術動向調査
- 先行技術調査
- 侵害予防調査
- 無効資料調査
- 具体的な調査の流れ
- 調査目的、目標の明確化、準備
- 予備検索(キーワード、出願人、テキスト検索、特許分類検索)
- 検索式の見直し
- 再検索、検索式の再修正の繰り返し
- 検索結果の読み込み、解析、調査とりまとめ
- 効率的な特許調査のコツ
- 共通する調査ノウハウ
- 先行技術調査のコツ
- 侵害予防調査のコツ
- 無効資料調査のコツ
- 目的別の調査方針
【質疑応答】
セミナー講師
よろず知財戦略コンサルティング 代表 萬 秀憲 氏
(元・大王製紙(株) 執行役員 知的財産部長)
セミナー受講料
1名につき68,200円(税込・資料付)
〔1社2名以上同時申込の場合1名につき62,700円(税込)〕
受講について
- 本講座はZoomを利用したLive配信セミナーです。セミナー会場での受講はできません。
- 下記リンクから視聴環境を確認の上、お申し込みください。
→ https://zoom.us/test - 開催日が近くなりましたら、視聴用のURLとパスワードをメールにてご連絡申し上げます。
セミナー開催日時に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。 - Zoomクライアントは最新版にアップデートして使用してください。
Webブラウザから視聴する場合は、Google Chrome、Firefox、Microsoft Edgeをご利用ください。 - パソコンの他にタブレット、スマートフォンでも視聴できます。
- セミナー資料はお申込み時にお知らせいただいた住所へお送りいたします。
お申込みが直前の場合には、開催日までに資料の到着が間に合わないことがあります。ご了承ください。 - 当日は講師への質問をすることができます。可能な範囲で個別質問にも対応いたします。
- 本講座で使用される資料や配信動画は著作物であり、
録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止いたします。 - 本講座はお申し込みいただいた方のみ受講いただけます。
複数端末から同時に視聴することや複数人での視聴は禁止いたします。 - Zoomのグループにパスワードを設定しています。
部外者の参加を防ぐため、パスワードを外部に漏洩しないでください。
万が一部外者が侵入した場合は管理者側で部外者の退出あるいはセミナーを終了いたします。
受講料
68,200円(税込)/人