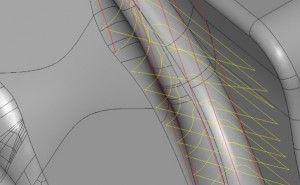人間とロボットが共存する未来社会は、もはや空想科学の世界にとどまりません。自動運転車、医療用ロボット、家庭用AIアシスタントなど、ロボット技術はすでに私たちの日常に浸透し始めています。しかし、こうした「知能をもった機械」が人間社会において安全かつ有益な存在であり続けるためには、技術そのものの進化だけではなく「倫理」や「制御」の枠組みが欠かせません。その重要な先駆けとして語られるのが、SF作家アイザック・アシモフが1942年に提示した『ロボット工学三原則』です。この三原則は、単なるフィクションの枠を越えて、現在に至るまでロボット倫理やAI開発における指標として多くの影響を与えてきました。今回は、ロボット工学三原則の内容と意義、現代のロボット開発との関連、そしてその限界や課題について詳しく見ていきます。
1. ロボット工学三原則の内容とその意図
アシモフの三原則は、彼の小説『Runaround(邦題:われはロボット)』にて初めて明示されました。その内容は次の通りです。
- 第1条:ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。
- 第2条:ロボットは人間に与えられた命令に従わなければならない。ただし、その命令が第1条に反する場合は、この限りではない。
- 第3条:ロボットは第1条および第2条に反しない限り、自己を守らなければならない。
この三原則は、単なるプログラムの命令体系ではなく、「機械に倫理を内在させる」ための枠組みとして設計されました。つまり、アシモフはロボットに自律性を持たせる一方で、それ...