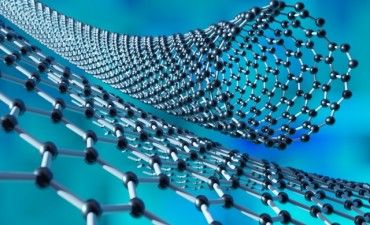においの原因物質特定方法や製品のにおい評価・改良方法等に
ついて、その具体的な手順を、事例をもとに解説します!
講師
(株)島津テクノリサーチ 試験解析事業部 営業部 グループ長 高野 岳 先生
受講料
1名46,440円(税込(消費税8%)、資料・昼食付)
*1社2名以上同時申込の場合 、1名につき35,640円
*学校法人割引 ;学生、教員のご参加は受講料50%割引
セミナーポイント
近年、芳香や消臭の機能を保有した商品の開発・販売が増加しており、幅広い分野への
展開がなされている。また、顧客・消費者からの、製品のにおいに関するクレーム・問い合わせも
増加してきている。
これらの状況を踏まえて、本セミナーでは、においの調査方法と分析方法・評価方法について
基礎的な内容から説明を行います。
ケーススタディとして数々の分析事例をもとに、そのアプローチの考え方やスキーム構築、
分析評価方法等、具体的なすすめ方を学びます。
○受講対象:
・食品・飲料、容器包装材、家電、工業製品、室内等の異臭等で困っている方
・消脱臭関連製品、臭気の低減化の担当者、体臭等のにおい分野の製品の開発担当者
○受講後、習得できること:
においの調査のスキームの構築方法、においの分析方法・評価方法の考え方の習得
セミナー内容
1.においとは
(1)人がにおいを感じる経路(嗅覚受容器の構造)
(2)におう化学物質とは
(3)においは複数の化学物質で構成
(4)におう化学物質は非常に低濃度
(5)臭気強度と物質濃度の関係、臭気強度の訓練方法
(6)快・不快度と物質濃度の関係
(7)ウェーバー・ファヒナーの法則(感覚の大きさが刺激強度の対数に比例する法則)
(8)臭質の捉え方(臭いの質の表現法)
(9)人の嗅力(ばらつき、年齢の影響、男女の差)
(10)順応(においの慣れ)、嗅覚疲労(嗅覚が働かなくなる)
2.においの調査・分析方法の例
(1)どこから始めたら良いのか?におい調査の考え方とその手順
(サンプル確保の留意点・従業員の訓練方法など)
(2)においの調査(原因物質の探索)のスキームと測定方法の例
(3)機器分析によるにおい成分の定性・定量の例
(4)代表的なにおいの採取方法
(5)悪臭防止法による特定悪臭物質の測定方法
(6)におい嗅ぎGCMSやGCMSによる試料の濃縮方法、測定方法
(7)におい識別装置による測定方法
(8)官能試験による測定方法
(9)再発防止(予防)策の例
3.においの原因物質特定における調査・測定評価事例
(1)食品異臭の例とにおい物質の物性(log pow、pKa、イオン解離性とpH)
(2)容器包装材の異臭・異味の例
4.製品のにおい改良に向けた調査・測定評価事例
〜においの全体像の把握・においの比較〜
(1)におい識別装置による測定の例
(センサ技術によるにおいの強さの違い、においの質の違いの評価)
(2)におい識別装置とGCを組み合わせた商品の評価の例
(3)工業原材料の改良の評価の例
(4)製品の消脱臭の評価の例
5.室内のにおいの調査及び分析・評価の具体例
(1)洗濯機の消臭の評価の例
(2)浴室の臭気の調査の例
(3)柔軟剤を使用した衣服を着用した時の調査の例
(4)喫煙後の呼気のにおいの調査の例
(5)キッチンの換気扇の油臭の測定の例
6.Indoor Air Qualityに関する試験
(1)室内で使用される製品からの化学物質の放散試験
*セミナーで紹介する各種においの調査及び分析評価の事例
事例1 倉庫保管時にダンボールに付着したかび様臭気の定性
事例2 カップ麺への防虫剤成分の移行
事例3 化粧品容器の異臭
事例4 ラミネートによる豆腐の異臭
事例5 におい識別装置による紅茶茶葉のにおいの比較
事例6 におい識別装置による食品油脂製品のにおいの比較
事例7 におい識別装置、GCによる納豆のにおいの比較
事例8 におい識別装置による市販ゴム手袋のにおいの比較
事例9 におい識別装置による樹脂の臭質の改善の評価
事例10 におい識別装置による電気製品のにおいの評価
事例11 におい嗅ぎGCMSによる洗濯機の洗濯槽の臭気
事例12 におい嗅ぎGCMSによる浴室の臭気
事例13 におい嗅ぎGCMSによる柔軟剤を使用したシャツの着用前後の臭気
事例14 GCMS、におい識別装置による喫煙後の呼気の臭気
事例15 におい嗅ぎGCMSによるキッチンの換気扇の油臭
<質疑応答>
※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です
開催日時
10:30 ~
受講料
46,440円(税込)/人
※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます
※銀行振込
※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です
開催日時
10:30 ~
受講料
46,440円(税込)/人
※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます
※銀行振込
類似セミナー
-
締切間近
 2026/01/20(火)
13:00 ~ 16:30
2026/01/20(火)
13:00 ~ 16:30<研究開発・製造販売等、専門外の方が知っておきたい>新規化学物質対応に必要となる化審法の申請手続と対応実務
 [東京・大井町]きゅりあん 5階第3講習室
[東京・大井町]きゅりあん 5階第3講習室
関連セミナー
もっと見る関連記事
もっと見る-
【真空不要】大気圧プラズマ(AP)とは?接着不良を解決しコストを激減させる「魔法の風」の仕組み
【目次】 製造業の現場では、製品の品質と耐久性を決定づける「表面処理」が極めて重要な工程です。これまで、高機能な表面処理を行うために... -
【液体を一瞬で粉末に】スプレードライ(噴霧乾燥)とは?原理・メリットから「粉ミルク」等の応用例まで
【目次】 現代の製造業、特に食品、医薬、化学の分野において、「乾燥」工程は最終製品の品質を決定する極めて重要なプロセスです。原料に含... -
驚異の多孔質構造が変える社会環境、MOF(金属有機構造体)の構造・機能、その市場とは
【目次】 現代社会は、地球温暖化対策のための二酸化炭素(CO₂)回収、クリーンエネルギーとしての水素貯蔵、医薬品の高効率な運搬、そして環... -
DEHPとは?危険性や健康への影響、身近な製品例と安全な代替品まで解説
【目次】 DEHP(フタル酸ジエチルヘキシル)、この耳慣れない化学物質が、私たちの日常生活に深く根ざしていることをご...