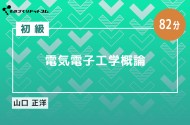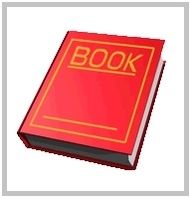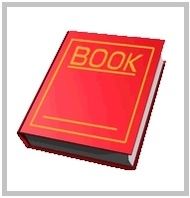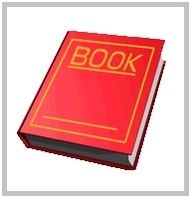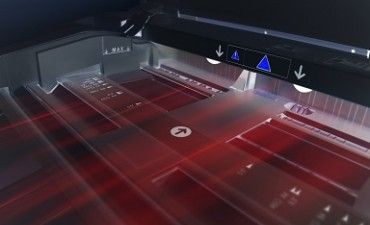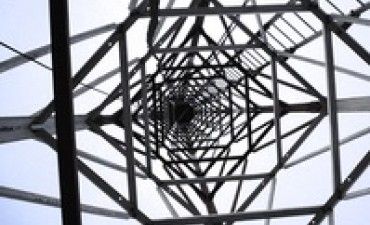★「苦手に思っている」「取っつきにくい」など難解と感じている方へ
基本知識、計算・解析方法、つまづきやすい点とその解消法までを学ぶ
日時
【Live配信】2025年11月10日(月) 10:30~16:30
【アーカイブ(録画)配信】 2025年11月19日まで受付(視聴期間:11月19日~11月29日まで)
セミナー趣旨
交流インピーダンスをツールとして利用しようとすると、「電気工学」「複素関数」「周波数分散」など、電気化学者にとって取っつきにくい概念が数多く生じる。特に、「電気伝導率測定・電気化学反応解析・界面挙動」は、「電解質・電極・二重層」を理解する上で欠かせない。これらの測定は電池・キャパシタ・電解質材料の性質を知る上でも重要な測定技術となる。講師はこれまで研究における学生の指導を通じて、インピーダンスに関する理解において、どこが引っかかるのかを感じてきた。このセミナーでは、
インピーダンスの定義と物理的な意味
インピーダンスに関する計算方法 (複素数がなぜ必要か?) と解析法
インピーダンスのデータで解ること・解らないことの区別
を中心に、さまざまな躓きやすい点を解消していきながら、実践的なインピーダンス測定の活用について解説する。
習得できる知識
・インピーダンスの定義と物理的な意味
・インピーダンスに関する計算方法 (複素数がなぜ必要か?) と解析法
・インピーダンスのデータで解ること・解らないことの区別
セミナープログラム
1.概要
1.1 インピーダンスと抵抗の違い
1.2 周波数と時定数
1.3 周波数分散(周波数を変えると何がわかるか?)
2.複素インピーダンス
2.1 インピーダンスになぜ複素数が関係するのか
2.2 ボード線図と時定数
2.3 ナイキストプロットと位相(電流・電圧のずれ)
2.4 等価回路は何のために必要か?
2.5 交流法におけるオームの法則
3.電気化学インピーダンス
3.1 「電位」と「印加電圧」は何が違うのか?
3.2 電気化学インピーダンスにおけるナイキストプロット
3.3 電気化学反応と時定数
4.実例をもとにした解説
4.1 電解質材料の電気伝導率測定
4.2 輸率測定(AC-DC法の意味)
4.3 リチウムイオン電池等の材料におけるインピーダンス
4.4 キャパシタ材料におけるインピーダンス
4.5 腐食・分極測定におけるインピーダンス
【質疑応答】
セミナー講師
神戸大学 大学院工学研究科 応用化学専攻 教授 博士(理学) 水畑 穣 氏
セミナー受講料
1名につき55,000円(消費税込・資料付き)
〔1社2名以上同時申込の場合1名につき49,500円(税込)〕
受講について
セミナーの接続確認・受講手順はこちらをご確認下さい。
受講料
55,000円(税込)/人
関連セミナー
もっと見る関連教材
もっと見る関連記事
もっと見る-
補償光学(AO)とは?レーザー加工の精度を限界突破させる次世代技術を徹底解説
【目次】 現代の製造業は、スマートフォンや半導体、医療機器などに代表されるように、ミクロンやナノメートルレベルの超精密加工を求められ... -
レアアースレス・モーターとは?レアアースフリーの衝撃、環境と経済を変えるモーターの進化論
【目次】 現代社会はモーターなしには成り立ちません。スマートフォンから電気自動車、産業用ロボットに至るまで、私たちの生活のあらゆる側... -
HVDC(高圧直流送電)とは?HVDCが描く未来、再エネ社会を繋ぐ革新送電
【目次】 現代社会において、電力は私たちの生活を支える不可欠なインフラです。しかし、その電力供給のあり方は、気候変動問題への対応やエ... -
エネルギーハーベスティングとは?自然の力がエネルギーの新しい形に、その現状と展望を解説
【目次】 エネルギーハーベスティングは、私たちの身の回りに存在する太陽光、熱、振動、電波といった微小なエネルギーを「収穫...