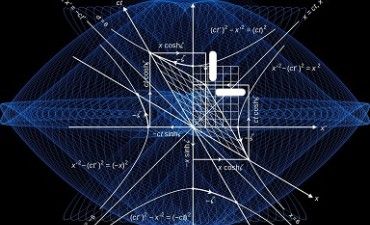★「モルフォ発色」のメカニズムと光ディフューザ等の最新動向を解説
セミナー趣旨
モルフォ蝶の青い輝きは、「生きた宝石」と呼ばれ、「生物の金属光沢」として著名である。その発色はしばしば「構造色の代表」と扱われるが、じつは物理学の観点では異常な発色である。それは、「干渉色なのに虹色でない」一種のミステリーである。その鍵は、鱗粉上の特異なナノ構造にあることを、我々は20年以上前に突き止めている。当初は純粋にその「謎解きと実証」で始まった研究は、その後、工学的にさまざまな利点が見いだされ(広角で明るく単色、無退色・省材料で低い環境負荷、など)、この10数年で多様な発展を遂げている。
一方、反射方向のみならず、この数年で透過方向にまったく異なる価値が見いだされ、従来なかった新しいタイプの光拡散板(光ディフューザ)が開発され始めた。一方向からの入射光を拡散し、明るく広角で一様かつ色変化のない光源を作る光ディフューザは、反射とはまた違った展開を見せ始めている。それら反射・透過の異なるアプローチを含めて、モルフォ発色の多様な展開について、今後の可能性も含めて紹介する。
同時に、ナノ構造を「作って・測って・予測する(設計)」すべてを実施する立場も参考になれば幸いである。加えて、「モルフォ蝶に学ぶ光特性」は、「構造色としては異端」だが「バイオミメティクスの中心」にあり、その縁で関わってきた国際標準化と国際動向についても一端を紹介する。
昨今深刻化する地球環境問題とのかかわりで、生物模倣の分野もこの10年ほどで大きく変貌しており、特に欧州の動向も含めて目が離せない状況にある。
セミナープログラム
1.モルフォ発色の基礎 〜構造色からの位置づけ
1-1 モルフォ発色の謎
1-2 モルフォ発色の原理: 乱雑ナノ構造
1-3 モルフォ発色の実証
2.反射型モルフォ光材料
2-1 モルフォ発色を設計する(計算)
2-2 モルフォ発色を作る(作製)
2-3 モルフォ発色を評価する(測定)
2-4 発展と必要な技術
3.透過型モルフォ光材料 (光拡散板)
3-1 反射から透過への転用
3-2 新たな光拡散板(ディフューザ)
3-3 発展と可能性
4.異なる方向性と新たな展開
4-1 モルフォ素子の発展形
4-2 ディフューザの発展形
5.バイオミメティクス国際標準化と世界情勢
6-1 国際標準化 TC266
6-2 世界情勢
6-3 フランスの特異な取り組み
【質疑応答】
セミナー講師
大阪大学 大学院工学研究科 物理学系専攻 准教授 博士(工学) 齋藤 彰 氏
セミナー受講料
1名につき55,000円(消費税込・資料付き)
〔1社2名以上同時申込の場合1名につき49,500円(税込)〕
受講について
セミナーの接続確認・受講手順はこちらをご確認下さい。
受講料
55,000円(税込)/人
前に見たセミナー
関連セミナー
もっと見る関連教材
もっと見る関連記事
もっと見る-
DEHPとは?危険性や健康への影響、身近な製品例と安全な代替品まで解説
【目次】 DEHP(フタル酸ジエチルヘキシル)、この耳慣れない化学物質が、私たちの日常生活に深く根ざしていることをご... -
測色とは?色を感じるプロセスと測色をわかりやすく解説
【目次】 色は私たちの生活に欠かせない要素であり、視覚的な体験を豊かにする重要な要素です。色を感じるプロセスは、私たちの感情や思考、... -
PFAS(ピーファス)を分かりやすく解説!有機フッ素化合物の基礎知識
【目次】 PFAS(ピーファス)という言葉を耳にしたことはありますか?PFASは「パーフルオロアルキル物質」の略で、主に有機フッ素化... -
プラスチック分解微生物とは?求められる背景や仕組みについて解説
プラスチックは私たちの生活に欠かせない素材ですが、その便利さの裏には深刻な環境問題が潜んでいます。毎年膨大な量のプラスチックが廃棄され、海洋や土壌に蓄...