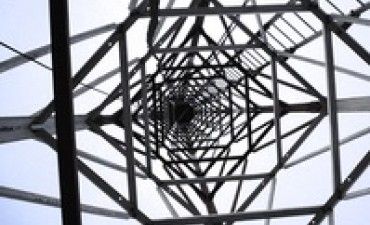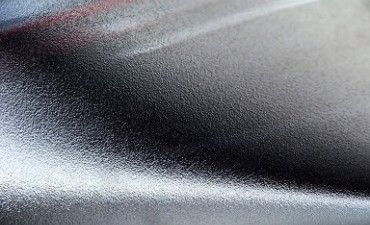類似セミナーへのお申込みはこちら
配線、接合材料として注目を集める
銅ナノ粒子の開発状況を詳解!
耐酸化性、分散安定化など課題解決へのヒントと導電回路の開発事例まで最新情報を報告
セミナープログラム
<10:00〜12:00>
1.銅ナノ粒子の分散安定化とインク・ペーストへの応用
北海道大学 米澤 徹 氏
1.金属微粒子の合成方法
1.1 化学的合成法
1.2 物理的合成法
1.3 大量合成法
2.銅微粒子・ナノ粒子の合成法
2.1 化学的合成法
2.2 原料の選択
2.3 還元手法
2.4 分散剤の選択
2.5 分析
2.5.1 構造
2.5.2 結晶構造
2.5.3 酸化状態
3.銅微粒子の分散手法
3.1 粉末からの分散
3.2 分散過程での処理法のノウハウ
3.3 単独粒子群の構築
3.4 保存
4.ペースト
4.1 分散剤の選択
4.2 溶剤の選択
5.低温焼結
5.1 低温焼結への最適化
5.2 添加剤
6.実際に焼結させる
7.まとめ
【質疑応答・個別質問・名刺交換】
<12:45〜14:15>
2.マイクロ流体デバイスを用いた銅ナノ粒子の合成と粒子径制御
関東学院大学 柳生 裕聖 氏
【講座概要】
マイクロ流体デバイスはガラスやシリコンに微細流路を加工し,マイクロスケールの流路内の空間で溶液を分子レベルで迅速に混合可能である。このことからデバイスを用いた化学合成では流量制御により微小時間だけ溶液を加熱反応させることも可能である。本講座ではマイクロ流体デバイスの原理やデバイスを用いた金,銅ナノ粒子の合成における粒子径の制御技術について説明する。
1.マイクロ流体デバイス
1.1 デバイス製造技術
1.2 マイクロスケールにおける混合
1.3 マイクロ流体デバイスの応用例
2.マイクロ流体デバイスを用いたナノ粒子の合成メカニズムの解析
2.1 液相還元法
2.2 ラメール図
2.3 最適混合時間の解析
3.マイクロ流体デバイスを用いた銅ナノ粒子の合成
3.1 アスコルビン酸を用いた銅ナノ粒子の合成
3.2 加熱温度と流量の影響
【質疑応答・個別質問・名刺交換】
<14:30〜16:30>
3.銅ナノインクを用いた導電パターンの形成と基材との密着性向上
石原ケミカル(株) 南原 聡 氏
【講座概要】
印刷法を用いて回路形成するプリンテッドエレクトロニクスが注目されている。本講演では、原料が安価でEM(エレクトロマイグレーション) 耐性のあるCuナノインクを用いて、印刷法により回路パターンを形成し、フラッシュランプを用いて、大気下、短時間でCu回路を形成する方法(フォトシンタリング)を紹介する。また、Cuナノインクの各種導体化法、有機フィルムやガラス基材上への微細配線形成プロセス、Cuナノインクを用いたSAP(Semi Additive Process)対応についても解説する。
1.プリンテッドエレクトロニクスとは
1.1 従来法と印刷法
1.2 適用分野
2.フォトシンタリング(光焼結)型Cuナノインクの紹介
2.1 導電性インクの比較
2.2 フォトシンタリングプロセスについて
2.3 フォトシンタリング前後のCu皮膜
3.フォトシンタリングのメカニズム
3.1 一般的な粒子の焼結
3.2 フォトシンタリングのメカニズム
4.ガラス基材上でのフォトシンタリング
4.1 ガラス基材上での照射エネルギー
4.2 ポリイミドとガラスの焼成皮膜の比較
4.3 熱伝導率とフォトシンタリング
5.導電パターン形成例
5.1 インクジェット印刷試作例
5.2 フレキソ印刷試作例
5.3 めっき増膜試作例
6.Cu皮膜とフィルム基材の密着機構
6.1 めっきCu皮膜の剥離試験
6.2 フィルム表面SEM像
6.3 めっきCu皮膜の断面SEM像
6.4 フォトシンタリング前後のフィルム表面SEM像
7.Cuメタルメッシュタッチパネルの作製
7.1 タッチパネル作製プロセス
7.2 グラビアオフセット印刷について
7.3 異なる線幅の同時印刷
7.4 各種基材上Cuメッシュパターン
7.5 センサーフィルム静電容量測定
8.導体化法・Cuインク・ペーストの紹介
8.1 各種導体化法
8.2 Cuインク・ペースト
9.薄膜印刷
9.1 付着力コントラスト印刷(薄膜印刷)
9.2 付着力コントラスト印刷例
9.3 Cuメタルメッシュ形成例
10.厚膜印刷
10.1 スクリーン印刷(厚膜印刷)
10.2 スクリーン印刷用ペースト
10.3 ギ酸雰囲気焼成による導体化
11.Cuナノインクを用いたSAP(Semi Additive Process)対応
11.1 片面FPC作製プロセス
11.2 高温負荷試験時の剥離強度
11.3 イオンマイグレーション試験
【質疑応答・個別質問・名刺交換】
セミナー講師
1.北海道大学 大学院工学研究院 材料科学部門/産学・地域協働推進機構 教授 博士(工学) 米澤 徹 氏
2.関東学院大学 理工学部 理工学科 機械学系 教授 博士(工学) 柳生 裕聖 氏
3.石原ケミカル(株) 第三研究部 開発課 主任 南原 聡 氏
セミナー受講料
1名につき55,000円(消費税抜き・昼食・資料付き)
〔1社2名以上同時申込の場合1名につき50,000円(税抜)〕
受講料
60,500円(税込)/人
類似セミナー
関連セミナー
もっと見る関連教材
もっと見る関連記事
もっと見る-
レアアースレス・モーターとは?レアアースフリーの衝撃、環境と経済を変えるモーターの進化論
【目次】 現代社会はモーターなしには成り立ちません。スマートフォンから電気自動車、産業用ロボットに至るまで、私たちの生活のあらゆる側... -
DEHPとは?危険性や健康への影響、身近な製品例と安全な代替品まで解説
【目次】 DEHP(フタル酸ジエチルヘキシル)、この耳慣れない化学物質が、私たちの日常生活に深く根ざしていることをご... -
HVDC(高圧直流送電)とは?HVDCが描く未来、再エネ社会を繋ぐ革新送電
【目次】 現代社会において、電力は私たちの生活を支える不可欠なインフラです。しかし、その電力供給のあり方は、気候変動問題への対応やエ... -
撓鉄(ぎょうてつ)とは?1200年の歴史が生んだ日本の鍛鉄技術、その美学と技能継承の課題を解説
【目次】 日本には、1200年以上の時を超えて受け継がれる「撓鉄(ぎょうてつ)」という独自の伝統技術が存在します。この技術は、熱した...