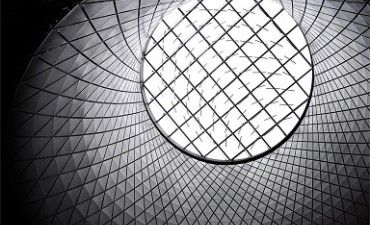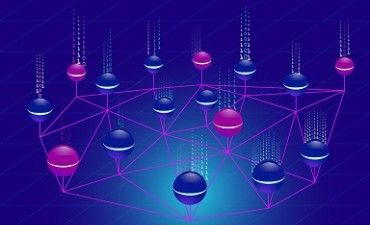類似セミナーへのお申込みはこちら
粉体を扱う技術者にとって欠かすことのできない
粒子径や粒度分布の測定・評価法を詳解!
粒子径・粒度分布測定の基礎を徹底的に解説します
セミナー趣旨
粉体・粒子を取り扱う業務では粒子径・粒子径分布の情報は欠かすことのできないものです。一方 、それゆえに 、対象となる粒子径範囲などに対応して10種類を超える異なる測定原理があったり 、また 、粒子径分布については統計的取り扱いが必要になったりするもので 、「基本的知識をひととおり」といえどもその系統だった学習はなかなかにハードルが高かったりします。ですので 、「粒子径・粒子径分布計測の基礎」の復習は 、粉体・粒子系技術者にとっての必修科目といって過言ではありません。
セミナープログラム
第1部 粒子径・粒子径分布計測の基礎
1.粒子径計測の目的
2.粒子径とはナニか
3.粒子径「分布」の取り扱い
4.ヒストグラムと分布密度と積算分布
5.粒子径分布の測定結果の表示法
6.個数基準の分布と質量基準の分布
7.代表径(各種の平均径・50%径)
8.各種測定原理概論
9.粒子径・粒子径分布計測の標準化活動(ISOとJIS)
□ 質疑応答 □
第2部 粒子径・粒度分布測定の実践テクニック
実用材料の分散性や分散安定性を評価する際、粒子径や粒子径分布測定は重要な位置を占める。実用材料では、粒子濃度が高いスラリーやペーストが多く使用されているが、本来、評価する目的に合わせて希釈操作も含めてサンプルの準備方法や評価方法を適宜選択する必要がある。本講では、実用材料を実際に評価する際のサンプル準備、目的ごとの測定手法の選択のポイント、得られた結果の解釈について実例を示しながら解説する予定である。
1.実用系ではどんな時に粒子径を測定するのか?
2.分散性と分散安定性評価と粒子径測定の関係
3.分散性評価のための粒子径測定
4.分散安定性評価のための粒子径測定-ゼータ電位測定との関係とは?-
5.濃厚系での評価事例紹介
□ 質疑応答 □
<受講によって得られる知識・ノウハウ>
・粒子径分布測定の注意点
・粒子径分布測定のための、サンプル準備法
・粒子濃度の高いサンプルの測定方法と注意点
・粒子濃度の高いサンプルの解析方法と注意点
セミナー講師
創価大学 理工学部 教授 松山 達 氏
第2部 粒子径・粒度分布測定の実践テクニック(仮) (14:30~16:30)
武田コロイドテクノ・コンサルティング(株) 代表取締役社長 武田 真一 氏
略歴
昭和63年より、超音波方式ゼータ電位測定装置の研究に従事、平成4年より米国Dispersion Technology社との共同研究として超音波方式粒度分布測定装置の開発に従事。平成16年からは、超音波法粒度分布測定法のISO化を目指し、ISO/SC4「超微粒子評価分野の国際規格適正化調査研究小委員会」委員および音響法ワーキンググループ(WG14)国際副委員長ならびに国内委員長として活動。
専門
コロイド科学、超音波減衰分光法
セミナー受講料
44,000円( S&T会員受講料41,800円 )
(まだS&T会員未登録の方は、申込みフォームの通信欄に「会員登録情報希望」と記入してください。
詳しい情報を送付します。ご登録いただくと、今回から会員受講料が適用可能です。)
S&T会員なら、2名同時申込みで1名分無料
2名で 44,000円 (2名ともS&T会員登録必須/1名あたり定価半額22,000円)
【1名分無料適用条件】
※2名様ともS&T会員登録が必須です。
※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。
※3名様以上のお申込みの場合、1名あたり定価半額で追加受講できます。
※受講券、請求書は、代表者に郵送いたします。
※請求書および領収証は1名様ごとに発行可能です。
(申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)
※他の割引は併用できません。
受講料
44,000円(税込)/人
類似セミナー
-
 2025/10/20(月)
10:30 ~ 16:30
2025/10/20(月)
10:30 ~ 16:30実務で扱うための「粉体工学」超入門-物性などの基本から測定・評価法、装置・操作機器設計の考え方まで-<会場受講>
 [東京・大井町]きゅりあん 4階研修室
[東京・大井町]きゅりあん 4階研修室
-
 2025/08/22(金)
10:30 ~ 17:00
2025/08/22(金)
10:30 ~ 17:00造粒技術の基礎・装置から前後処理などの実践ノウハウ、スケールアップ参考例まで~小型透明デモ機実験を通じて、粉体・粒子の挙動を体感的に理解する~
 [東京・大井町]きゅりあん 5階第3講習室
[東京・大井町]きゅりあん 5階第3講習室
-
 2025/10/21(火)
10:30 ~ 16:30
2025/10/21(火)
10:30 ~ 16:30<粉体の付着・凝集トラブルを解決するための>粉体の付着力・付着性の基礎・評価法から、効果的なハンドリング技術とその実例まで<会場受講>
 [東京・大井町]きゅりあん 4階研修室
[東京・大井町]きゅりあん 4階研修室
関連セミナー
もっと見る-
 2025/10/20(月)
10:30 ~ 16:30
2025/10/20(月)
10:30 ~ 16:30実務で扱うための「粉体工学」超入門-物性などの基本から測定・評価法、装置・操作機器設計の考え方まで-<会場受講>
 [東京・大井町]きゅりあん 4階研修室
[東京・大井町]きゅりあん 4階研修室
-
 2025/08/22(金)
10:30 ~ 17:00
2025/08/22(金)
10:30 ~ 17:00造粒技術の基礎・装置から前後処理などの実践ノウハウ、スケールアップ参考例まで~小型透明デモ機実験を通じて、粉体・粒子の挙動を体感的に理解する~
 [東京・大井町]きゅりあん 5階第3講習室
[東京・大井町]きゅりあん 5階第3講習室
-
 2025/10/21(火)
10:30 ~ 16:30
2025/10/21(火)
10:30 ~ 16:30<粉体の付着・凝集トラブルを解決するための>粉体の付着力・付着性の基礎・評価法から、効果的なハンドリング技術とその実例まで<会場受講>
 [東京・大井町]きゅりあん 4階研修室
[東京・大井町]きゅりあん 4階研修室
関連教材
もっと見る関連記事
もっと見る-
DEHPとは?危険性や健康への影響、身近な製品例と安全な代替品まで解説
【目次】 DEHP(フタル酸ジエチルヘキシル)、この耳慣れない化学物質が、私たちの日常生活に深く根ざしていることをご... -
ナノテクノロジーとは?基礎から最新応用、未来の課題まで徹底解説
【目次】 1ナノメートルは髪の毛の太さの約10万分の1。ナノテクノロジーとは、原子や分子といった極限の小ささの世界で物質を自在に設計... -
超流動とはどういう現象?仕組みや超伝導との違いなどを詳しく解説
【目次】 超流動とは、物質が極低温において示す特異な現象であり、流体が摩擦なしに流れる状態を指します。超流動の現象(特にヘリウム-4... -
フェルミ準位とは?半導体・金属での違いや応用例をわかりやすく解説
【目次】 フェルミ準位は、物理学や材料科学において非常に重要な概念です。特に半導体や金属の電子構造を理解する上で欠かせない要素となっ...


![[入門者OK]<br/>この分野の初歩から説明します 初心者向けセミナーです](https://assets.monodukuri.com/img/beginner-mark.png?d=0x0) 粉体技術者なら押さえておきたい粒子径・粒度分布測定の基礎知識
粉体技術者なら押さえておきたい粒子径・粒度分布測定の基礎知識