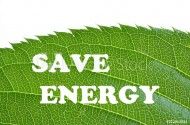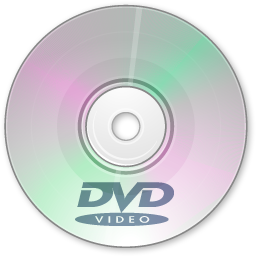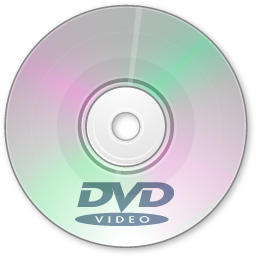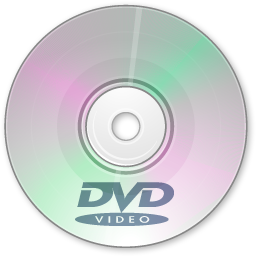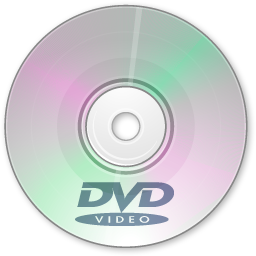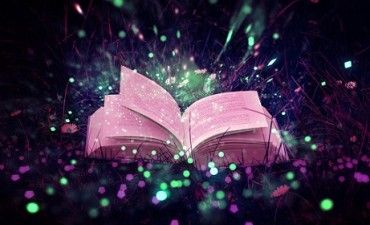類似セミナーへのお申込みはこちら
【エネルギーインフラのあるべき姿と、どこでお金が回るか】
-混乱が続く米国のエネルギー政策- -この法案の米国と世界と日本に与える影響-
■会場受講 ■ライブ配信
セミナー趣旨
現在の米国のエネルギー政策は、ウクライナ・ウイグル問題の長期化と混乱、ソーラーパネルのアンチダンピング調査のゴタゴタ、EPA(環境省)の温暖化ガス排出規制に関する連邦最高裁判決、民主党内の内輪揉め、旱魃とエネルギー価格の高騰等で迷走をつづけている。
この中で、米国連邦議会下院は、民主党単独で審議を進めてきた「インフレ削減法案(Inflation Reduction Act of 2022 (IRA))」を8月12日に220対207の賛成多数で可決した。上院では8月7日に51対50で可決済みで、米国のジョー・バイデン大統領が8月16日に署名し成立した。バイデン大統領が2021年に発表したビルド・バック・ベター(BBB)法案が事実上頓挫し、その他の内政・外交で八方塞がりに見えるバイデン政権にとって、久々のグッドニュースとなった。
上院民主党が公表している試算によると、同法は今後10年で、気候変動対策などに4,370億ドル(約57兆円)を歳出する一方、一部税制や薬価に関する改革などで7,370億ドル(約96兆円)の歳入を見込んでおり、差し引きで3,000億ドル(40兆円)以上の財政赤字の削減が実現できるとされている。
再エネ関連では、関連業界からの強い要望(ロビー活動)があった太陽光、風力、蓄電池、CCUSなどのカーボンニュートラルに必要な製品やサービスに対する税額控除が導入(延長/拡大)され、エネルギー安全保障と気候変動対策で、約3,690億ドル(約48兆円)が盛り込まれた。
日本では、この法案成立に対して好意的な報道が多く見受けられるが、米国では否定的な報道も多い。直接恩恵を受ける業界以外からの反対運動も激しい。「そもそも、インフレ削減には寄与しない」「生産は米国には回帰しない」「中国依存は変わらない(中国を利するだけ)」という意見も多い。11月の中間選挙の結果次第では揺れ戻しがくる可能性も否定できない。
米国(シリコンバレー)に37年居住し、エネルギー政策や再エネビジネスをつぶさに見てきた講師が、最新のアップデートを含めて、現在の米国の脱炭素や再エネビジネスの全体像を俯瞰すると同時に、今回成立したこの法案がどのような影響を及ぼすかを考え、エネルギーインフラのあるべき姿と、どこでお金が回るかについて、解説する。
セミナープログラム
1.米国のエネルギー政策の現状
(1)ボディーブローで響くウクライナ・ウイグル・アンチダンピング問題
(2)迷走するバイデン政権の脱炭素政策
(3)「温室効果ガス(GHG)排出に関するEPA規制は違法」との連邦最高裁判決
2.「インフレ削減法案(Inflation Reduction Act of 2022)」の詳細とその影響
(1)再生可能エネルギーの奨励と構築の加速
・ 投資税額控除(ITC)適格資産の定義を拡大
・ 生産税額控除(PTC)の延長と拡大
・ 炭素回収利用隔離(CCUS)関連税額控除(45Q)を延長・修正
(2)電気自動車(EV)技術の導入の加速
(3)建物とコミュニティのエネルギー効率の向上
3.この法律の影響は?
(1)中国や東南アジアへの依存度が高い製品の生産は米国に回帰するのか?
(2)そもそもインフレ緩和に役立つのか?
(3)温暖化ガス排出に、どれぐらい貢献するのか?
4.日本はこの流れの中で何をすべきか
5.質疑応答/名刺交換
※プログラムは最新状況に応じて変更する場合があります
セミナー講師
阪口 幸雄(さかぐち ゆきお) 氏 クリーンエネルギー研究所 代表
セミナー受講料
1名につき 40,000円(税込)
受講について
事前に、セミナー講師へのご期待、ご要望、ご質問をお受けしております。
可能な限り講義に盛り込んでいただきますので
お申込フォームの備考欄を是非ご活用ください。
■ライブ配信について
<1>Zoomにてライブ配信致します。
<2>お申込時にご登録いただいたメールアドレスへ視聴用URLとID・PASSを開催前日までに
お送り致しますので、開催日時にZoomへご参加ください。
受講料
40,000円(税込)/人
類似セミナー
関連セミナー
もっと見る関連教材
もっと見る関連記事
もっと見る-
サーキュラーエコノミーとは?循環型社会への挑戦とその可能性を解説
【目次】 現代社会は、大量生産・大量消費・大量廃棄を前提とした「リニアエコノミー(線形経済)」の中で発展してきました。しかし、この一... -
-
-
グリーントランスフォーメーション(GX)とは?脱炭素とカーボンニュートラルを超えた新たな挑戦
【目次】 「グリーントランスフォーメーション(GX)」という言葉は、近年ますます注目を集めています。GXは、脱炭素やカー...