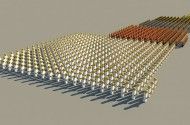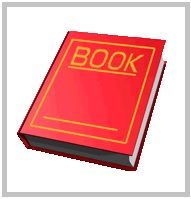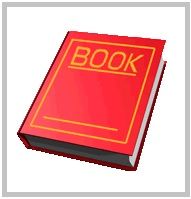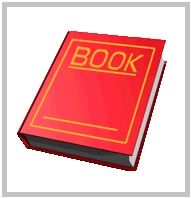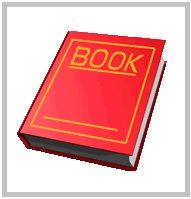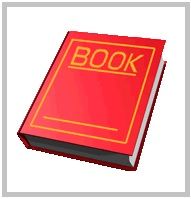![[入門者OK]<br/>この分野の初歩から説明します 初心者向けセミナーです](https://assets.monodukuri.com/img/beginner-mark.png?d=0x0) 医療機器滅菌と滅菌バリデーション、関連試験法の基礎、実務セミナー 滅菌関連法規から各滅菌バリデーションの基礎、滅菌関連試験の実務と問題解決(ISO1135:2014、ISO1137-1:2006Amd2:2018、ISO1137-2:2013、ISO11737-1:2018、ISO11737-2:2019、ISO10993-7:2008、Amd:2019対応)
医療機器滅菌と滅菌バリデーション、関連試験法の基礎、実務セミナー 滅菌関連法規から各滅菌バリデーションの基礎、滅菌関連試験の実務と問題解決(ISO1135:2014、ISO1137-1:2006Amd2:2018、ISO1137-2:2013、ISO11737-1:2018、ISO11737-2:2019、ISO10993-7:2008、Amd:2019対応)
滅菌保証における関連試験各工程のバリデーションを幅広く網羅!2021年3月公布の改正QMS省令も踏まえ、また要望の多かった実務事例も取り入れて3日間にわたって滅菌の基礎から解説します
日時
第1回 10月17日(月)13:00-16:30
医療機器におけるエチレンオキサイド滅菌とバリデーション(ISO1135:2014)
第2回 10月18日(火)13:00-16:30
医療機器における放射線滅菌とバリデーション(ISO1137-1:2006、Amd2 :2018、ISO1137-2:2013 )
第3回 10月19日(水)13:00-16:30
滅菌関連試験法の実務と規格要求 (ISO11737-1:2018、ISO11737-2:2019、ISO10993-7:2008、Amd:2019)
セミナー趣旨
医薬品医療機器法(薬機法)が施行され、滅菌バリデーション基準が改訂されるなど滅菌関連の規制が年々厳しくなっており、薬事規制を遵守し、規格基準を正しく解釈してシステムを構築、運用することが求められています。
また、規制要求であるバリデーションが強化されてます。
本セミナーは、医療機器にエチレンオキサイド滅菌、放射線滅菌を導入する場合の問題点及び法規制、また、工程設計、滅菌バリデーション、日常管理の事例を紹介し、実施する上の問題点と注意事項を解説します。さらに、関連試験として、バイオバーデン試験、無菌性の試験、EO残留物試験について、最新の規格要求および許容基準設定の考え方や正しく測定するための試験法バリデーション、試験実施上の問題点などについて説明します。また、滅菌を国内外の滅菌業者に委託する委託滅菌についての注意事項について考えていきたいと思います。
習得できる知識
・滅菌の基礎知識
・滅菌バリデーション、試験法バリデーションの知識
・滅菌関連試験を実施する上での注意点と関連情報
・ISO規格の動向
セミナープログラム
第1回 10月17日(月)13:00-16:30
医療機器におけるエチレンオキサイド滅菌とバリデーション
(ISO1135:2014)
■はじめに
本セミナーは、医療機器のエチレンオキサイド滅菌を導入する場合の問題点及び法規制、また、工程設計、滅菌バリデーション、日常管理の事例を紹介し実施する上の問題点と注意事項を解説します。また、滅菌バリデーション実施上の問題点を紹介し対応方法について考えていきたいと思います。
■受講後、習得できること
・滅菌の基礎知識
・滅菌バリデーション知識
・滅菌バリデーションレポートの作成とチェック方法
・ISO規格の動向
■講演項目
1. はじめに
2.EO滅菌の長所と短所
3. 滅菌法の選定
4.EO滅菌の法規制と安全性の確保
5. 滅菌剤の作用と毒性、環境/排出規制
6.EO滅菌の理論的考察と製品の無菌性保証
微生物の死滅と滅菌理論、製品の無菌性保証、微生物の滅菌抵抗性と作用機序、製品設計上の注意点
(ガス流路等による滅菌困難な事例と考え方)
7. 製品の定義と同等性および製品ファミリー、処理カテゴリー
製品、包装、積載の定義および製品ファミリー、処理カテゴリーの設定方法
8. プロセスおよび装置の特性、検証、校正
9. プロセスの定義と工程開発(滅菌条件設定)
プロセスパラメータと滅菌条件、日常管理の関係性、滅菌条件の設定
(オーバーキル法、BI/バイオバーデン法)
10. BIの管理とPCDの基本的要件
バイオバーデンの抵抗性とBIの抵抗性との比較、PCD使用要件
11. サンプルサイズと設定法
積載負荷(ダミーサンプル)、PCD、滅菌適格性試験
12. 滅菌バリデーション
IQ、OQ、PQ(PPQ、MPQ)と規格要求事項
13. 滅菌バリデーション計画書、報告書作成事例紹介
14. 滅菌適合性試験(標準条件)
15. BI無菌試験と無菌性の試験(ISO14161、ISO11737-2)
BIの無菌試験方法、部分サイクル法と無菌性の試験
16. 滅菌工程の日常監視と管理、滅菌委受託管理
製品のリリース判定基準、パラメトリックリリース、単一ロットリリース、滅菌委受託管理の責任と要件
17. 製品標準書と滅菌標準条件
18. プロセス有効性の維持
装置の保守、リクオリフィケーション(検証項目、実施頻度と設定根拠)
19. 変更管理
20. 滅菌工程の見直し(滅菌時間、コンディショニング方法、チャンバー温度、気化器温度)
21. 滅菌バリデーションにおける問題点と対策
製品温度分布改良(コンディショニング方法)、複数台の滅菌器の工程の同等性、
定期クオリフィーションの考え方、定期検証不適合時の対処方法
第2回 10月18日(火)13:00-16:30
医療機器における放射線滅菌とバリデーション
(ISO1137-1:2006、Amd2 :2018、ISO1137-2:2013 )
■はじめに
本セミナーは、放射線滅菌についてJIS、ISO規格の解説を中心に、自社滅菌および委託滅菌の管理と日常の運用について説明し、滅菌バリデーション計画書/報告書の形式で規格要求事項、資料のまとめ方を解説します。さらに、薬事承認申請添付資料の注意事項についても説明します。
また、滅菌条件の設定、検定線量照射、線量分布の統計処理や線量測定の不確かさなどについて実例で説明します。さらに、最近は放射線滅菌を海外で行うことが多く、その場合は海外のレポートを正しく評価し、また、QMS適合性調査を実施するためには規格要求事項を正しく理解する必要があります。査察を受ける際の注意点について解説します。
■受講後、習得できること
・滅菌の基礎知識
・放射線滅菌バリデーションの知識
・滅菌バリデーションレポートの作成とチェック方法
・ISO規格の動向
■講演項目
1. はじめに
2. 放射線滅菌法の長所と短所、滅菌法の選定
3. 放射線滅菌の法規制
QMS省令、滅菌バリデーション基準、JIST0806、ISO1137、PICS/GMP、EP、EMA
4. 放射線滅菌概略と滅菌装置、設備、線量計の校正
5. 放射線滅菌の理論的考察と製品の無菌性保証
微生物の死滅と放射線抵抗性、製品設計上の注意点
6. 製品の定義と製品ファミリー、処理カテゴリーの考え方
7. 工程の定義と工程開発(滅菌条件設定)
最大許容線量設定、滅菌条件の設定 と線量分布の関係性
8. 滅菌バリデーションと日常監視と管理
IQ、OQの要求事項と検証方法、PQ(線量分布)の要求と線量測定の不確かさ
9. プロセス有効性の維持
10. 変更管理と再検証の必要性
線源間の最大許容線量、検定線量、滅菌線量の移転
11. 滅菌バリデーション計画書/報告書作成事例紹介
12. バイオバーデン測定と管理のポイント
測定法の問題点と対処方法、低バイオバーデンの問題(過大/過小評価、検出限界)、
バイオバーデン基準外の処置、バイオバーデンスパイク、包装の汚染
13. 滅菌バリデーションにおける問題点と対策
低バイオバーデン、高抵抗性菌と検定線量照射試験失敗(損傷菌)、包装、
再検証不適合時の無菌性保証の考え方
14. 滅菌の委受託管理(国内、国外)
15. 放射線滅菌に係る承認申請資料作成上の問題点
滅菌線量設定の選定、最大許容線量(材質劣化試験)と安定性/耐久性の関係、
材質劣化の評価と加速試験
16. 放射線材質劣化対策と研究事例
・放射線による高分子材料劣化のメカニズム (分解、酸化、架橋反応)
・放射線のバイオマテリアル、医薬品成分に与える影響と対策
(高分子材料、高分子ゲル、生体由来材料、無機材料、注射剤)
・放射線劣化対策 (架橋法、添加法、低温照射法)
第3回 10月19日(水)13:00-16:30
滅菌関連試験法の実務と規格要求
(ISO11737-1:2018、ISO11737-2:2019、ISO10993-7:2008、Amd:2019)
■はじめに
本セミナーは、医療機器の滅菌関連の試験法として、バイオバーデン試験、無菌性の試験、EO残留物試験について、規格要求事項および問題点を説明します。また、試験結果を精度よく正しく出すために各規格で要求されている、試験法の選定、試験法バリデーション、試験精度の考え方について、実例を用いて注意点、問題点を解説します。また、査察指摘事項、トラブル事例についても解説します。
■受講後、習得できること
・滅菌関連試験実施上の情報、
・ISO規格の動向
・試験法バリデーションの規格要求事項と問題点の把握
■講演項目
1. バイオバーデン測定 ( ISO11737-1:2018、JIST11737-1:2013)
1.1 ISO11737-1:2018 変更の要点
1.2 バイオバーデン測定の目的とサンプリング法
グルーピングの考え方と要件、包装の考え方
1.3 バイオバーデン測定と測定法バリデーション
試験法適合性、取出法の妥当性、回収法選定要件と検証方法、培地性能試験
1.4 バイオバーデン菌種同定と簡易同定
1.5 バイオバーデン管理
管理基準値設定と基準逸脱処理、バイオバーデンスパイク、統計処理、変更管理
1.6 バイオバーデン測定上の問題点
未検出の取扱い、測定精度の向上、検出限界と改善法、測定部位、培養適正化
1.7 バイオバーデンの測定事例
(注射針、注射器、輸液セット、カテーテル、ダイアライザー、生検針、縫合糸、縫合器、血液回路、衛生材等)
1.8 低バイオバーデンの測定法 (培地浸漬法、MPN法、シェーカー法など)
1.9 低バイオバーデンの滅菌抵抗性によるトラブル事例
1.10 外部試験依頼の責任関係
1.11 QMS適合性調査不適合事例解説
2. 無菌性の試験( ISO11737-2:2019、JIST11737-2:2013)
2.1 無菌性の試験と除外規定
どのような評価に用いる試験か/無菌試験との違い
2.2 製品の選択(サンプルサイズ、グルーピング、SIP)
2.3 試験法バリデーション
(適合性試験、試験方法と判定評価方法(偽陰性、偽陽性)、培地培養条件、培地性能試験、無菌操作法、試験環境)
2.4 無菌性の試験評価方法、考慮すべき事項
試験の判定法、偽陰性、偽陽性の判定方法、製品の浮遊、損傷菌、無菌操作法
2.5 測定法の維持と変更管理
2.6 無菌性の試験のトラブル事例解説
2.7 外部依頼試験の責任関係
2.8 無菌性の試験のトラブル事例
3. EO残留物測定(ISO10993-7:2008,Amd:2019, JIST0993-7:2012)
3.1 各滅菌法比較とEO滅菌の歴史
EOの滅菌への応用、EO滅菌の優位性と必要性
3.2 EOの微生物への作用と滅菌抵抗性
3.3 EOの医用材料への作用(残留の機序)
浸透性(透過性)、吸着性、反応性
3.4 EOの毒性と滅菌法規制
3.5 医療機器のカテゴリー分類(患者の接触時間)
3.6 EO残留物許容限度と許容限度値の根拠(毒性データ)
許容限度値、小児使用について、EG許容値について、TCLの考え方
3.7 EO/ECH測定事例紹介(GC法)
・サンプリングと測定頻度、空試験
・抽出条件(サンプル比率、模擬抽出、徹底抽出、抽出温度/時間)
・測定法事例紹介
(使用カラム、充填材、標準品管理、GC設定条件、ヘッドスペース法、溶媒抽出法)
・残留量計算(未検出の考え方)
・試験法バリデーション
3.8 EO残留減衰曲線による製品出荷
3.9 EOの残留性と除去/低減対策
残留に影響する要因、残留EO除去方法、残留物低減対策
3.10 EO残留物管理における注意事項
再滅菌、材料との反応物、リスクアセスメント
セミナー講師
山口 透 先生 四季サイエンスラボラトリー
セミナー受講料
■税込(消費税10%)、資料付
*日程変更等ございました場合は、ご容赦下さい。
*全3回申込の方へ(不測の事態により、全回開催出来ない場合、以下規定に基づき、返金致します。)
全3回中、2回未満の実施の場合: 66%返金
全3回中、3回未満の実施の場合: 33%返金
| 参加形態 | 区分 | 見逃し配信なし価格(税込) (1社2名以上同時申込価格) |
見逃し配信あり価格(税込) (1社2名以上同時申込価格) |
|---|---|---|---|
| 1講座のみの参加 | 1回、2回、3回・・・ | 41,800円(30,800円) | 47,300円(36,300円) |
| 2講座の参加 | 1・2回、1・3回、2・3回、・・・ | 61,600円(50,600円) | 70,400円(59,400円) |
| 全講座(3講座)の参加 | 1・2・3・回・・・ | 75,900円(64,900円) | 86,900円(75,900円) |
※申込時に見逃し配信「なし」「あり」どちらかをお選び下さい。
参加形態(第○・○回参加)を申込備考欄に記載下さい。
※各回、別の方が受講いただくことも可能です。
※1社2名以上同時申込は、同時申込、同形態(講座数、参加日)でのお申込にのみ有効です
*学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引。
受講について
※本講座は、お手許のPCやタブレット等で受講できるオンラインセミナーです。
配布資料・講師への質問等について
- 配布資料は、印刷物を郵送で送付致します。
お申込の際はお受け取り可能な住所をご記入ください。
お申込みは4営業日前までを推奨します。
それ以降でもお申込みはお受けしておりますが(開催1営業日前の12:00まで)、
テキスト到着がセミナー後になる可能性がございます。 - 当日、可能な範囲で質疑応答も対応致します。
(全ての質問にお答えできない可能性もございますので、予めご容赦ください。) - 本講座で使用する資料や配信動画は著作物であり、
無断での録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止致します。
下記ご確認の上、お申込み下さい
- PCもしくはタブレット・スマートフォンとネットワーク環境をご準備下さい。
- ご受講にあたり、環境の確認をお願いしております(20Mbbs以上の回線をご用意下さい)。
各ご利用ツール別の動作確認の上、お申し込み下さい。 - 開催が近くなりましたら、当日の流れ及び視聴用のURL等をメールにてご連絡致します。
Zoomを使用したオンラインセミナーとなります
- ご受講にあたり、環境の確認をお願いしております。
お手数ですが下記公式サイトからZoomが問題なく使えるかどうか、ご確認下さい。
→ 確認はこちら
※Skype/Teams/LINEなど別のミーティングアプリが起動していると、Zoomでカメラ・マイクが使えない事があります。お手数ですがこれらのツールはいったん閉じてお試し下さい。 - Zoomアプリのインストール、Zoomへのサインアップをせずブラウザからの参加も可能です。
※一部のブラウザは音声(音声参加ができない)が聞こえない場合があります。
必ずテストサイトからチェック下さい。
対応ブラウザーについて(公式) ;
「コンピューターのオーディオに参加」に対応してないものは音声が聞こえません。
申込み時に(見逃し視聴有り)を選択された方は、見逃し視聴が可能です
- 開催5営業日以内に録画動画の配信を行います(一部、編集加工します)。
- 視聴可能期間は配信開始から1週間です。
セミナーを復習したい方、当日の受講が難しい方、期間内であれば動画を何度も視聴できます。
尚、閲覧用のURLはメールにてご連絡致します。
※万一、見逃し視聴の提供ができなくなった場合、
(見逃し視聴有り)の方の受講料は(見逃し視聴無し)の受講料に準じますので、ご了承下さい。
→こちらから問題なく視聴できるかご確認下さい(テスト視聴動画へ)パスワード「123456」
申込締日: 2022/10/18
受講料
75,900円(税込)/人