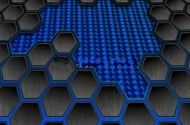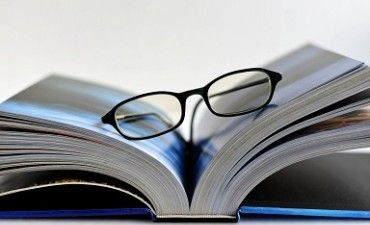類似セミナーへのお申込みはこちら
形状、流動性、乾燥度、造粒物の物性と
湿式造粒プロセスの関連性の把握、粘弾性制御のコツ
食品、化粧品、医薬品、コーティング、電子材料など
湿式造粒の各種用途展開
ムラ、粒子崩壊、閉塞などのトラブル例とその対策
講師
【第1部】 吉田技術士事務所 代表 技術士(機械部門) 吉田 照男 氏
【第2部】 大川原化工機(株) 開発部 部長 根本 源太郎 氏
受講料
1名につき50,000円(消費税抜,昼食・資料付)
〔1社2名以上同時申込の場合のみ1名につき45,000円〕
プログラム
【10:00〜15:00 ※ 昼食休憩挟む】
第1部 流動層造粒をはじめとした湿式造粒技術の基礎
● 講師 吉田技術士事務所 吉田 照男 氏
【講座の趣旨】
造粒方法には乾式もあるが運転条件や品質面で問題が多く実用例は極めて少ない。湿式造粒法の代表が押出造粒,流動造粒,攪拌造粒, 転動造粒,複合型流動造粒でこれらの特徴を解説する。
また流動造粒機の運転は粒子の成長に伴い風速を大きくする必要があるがその理解ができていない企業が多い。粒子の成長とともに風速を管理する線図を実際の生産プラントでの検証例も踏まえて解説する。
【セミナープログラム】
1.造粒の目的の考え方
食品,医薬品,飼料,肥料など業界別造粒の目的
2.造粒のメカニズム
2.1 造粒品はどのようにして作られるか
2.2 自足造粒機構と強制造粒機構
3.造粒機の特徴と運転管理およびトラブル事例と製品応用例
3.1 主な造粒機の使用状況と適正
3.2 押出造粒成形機:エクストルーダー,パスタ成形機
3.3 攪拌造粒機:回分式造粒機と連続式造粒機
3.4 流動造粒機:回分式造粒機と連続式造粒機
3.5 複合型流動造粒機:代表的な複合型流動造粒機
3.6 転動造粒機:回分式と連続式
3.7 噴霧乾燥造粒機:回転円盤式噴霧方法,流動層内蔵型(噴霧乾燥機で流動造粒)
3.8 解砕造粒機:真空乾燥品や真空凍結乾燥品を砕く方法
4.造粒プロセス関連技術
4.1 原料,製品の貯蔵:吸湿や粉体圧による固結トラブル事例
4.2 原料計量
4.3 空気輸送:配管閉塞や吸湿によるトラブル事例 4.4 原料粉砕:トラブル事例
4.5 原料混合・混練:成分偏析,嵩密度違いのトラブル
4.6 造粒品乾燥:流動不良トラブル
4.7 篩分工程:網の破損トラブル
4.8 解砕工程:解砕条件の決め方
5.造粒機のスケールアップ
5.1 スケールアップの考え方
5.2 スケールアップの実施例
6.造粒のバインダー
6.1 バインダーに要求される条件
6.2 バインダー選定の考え方
6.3 主なバインダー
7.造粒工程の環境管理
7.1 造粒プロセスの温度・湿度管理
7.2 造粒プロセスの空気清浄度・ゾーン管理
8.造粒プラントの粉体物性管理
8.1 粉体物性測定方法
8.2 原料,製品の流動性
8.3 製品顆粒の溶解性
8.4 製品顆粒の顆粒強度測定法
【質疑応答】
【15:15〜17:00】
第2部 流動造粒スプレードライヤの構成、運転と適用例
● 講師 大川原化工機(株) 根本 源太郎 氏
【セミナープログラム】
1.流動造粒スプレードライヤの基本構造
1.1 流動造粒スプレードライヤとは
1.2 流動造粒スプレードライヤの特徴
1.3 流動造粒スプレードライヤ製品について
2.流動造粒スプレードライヤの機器構成について
2.1 流動造粒スプレードライヤ本体について
2.2 微粒化装置
2.3 その他の機器
3.流動造粒スプレードライヤの運転操作と造粒形態
3.1 造粒の形態
3.2 製品水分について
4.流動造粒スプレードライヤの適用例
【質疑応答】
受講料
54,000円(税込)/人
類似セミナー
-
 2025/08/22(金)
10:30 ~ 17:00
2025/08/22(金)
10:30 ~ 17:00造粒技術の基礎・装置から前後処理などの実践ノウハウ、スケールアップ参考例まで~小型透明デモ機実験を通じて、粉体・粒子の挙動を体感的に理解する~
 [東京・大井町]きゅりあん 5階第3講習室
[東京・大井町]きゅりあん 5階第3講習室
-
 2025/08/21(木)
10:30 ~ 16:30
2025/08/21(木)
10:30 ~ 16:30基礎から学ぶ発酵技術~発酵微生物の育種、発酵プロセスの設計、管理とスケールアップ等~<会場受講>
 [東京・大井町]きゅりあん 4階第1特別講習室
[東京・大井町]きゅりあん 4階第1特別講習室
関連セミナー
もっと見る-
 2025/08/22(金)
10:30 ~ 17:00
2025/08/22(金)
10:30 ~ 17:00造粒技術の基礎・装置から前後処理などの実践ノウハウ、スケールアップ参考例まで~小型透明デモ機実験を通じて、粉体・粒子の挙動を体感的に理解する~
 [東京・大井町]きゅりあん 5階第3講習室
[東京・大井町]きゅりあん 5階第3講習室
-
 2025/08/21(木)
10:30 ~ 16:30
2025/08/21(木)
10:30 ~ 16:30基礎から学ぶ発酵技術~発酵微生物の育種、発酵プロセスの設計、管理とスケールアップ等~<会場受講>
 [東京・大井町]きゅりあん 4階第1特別講習室
[東京・大井町]きゅりあん 4階第1特別講習室
関連教材
もっと見る関連記事
もっと見る-
-
専門家がみる食用油脂の素顔:食用油脂の知識(その14)
【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「食品技術」に関するセミナーはこちら! ▼さらに幅広く学ぶなら!「分野別のカリキュラム」に関するオ... -
脂質酸化酵素リポキシゲナーゼ:食用油脂の知識(その13)
▼さらに深く学ぶなら!「食品技術」に関するセミナーはこちら! ▼さらに幅広く学ぶなら!「分野別のカリキュラム」に関するオンデマンドセミナーはこちら!... -