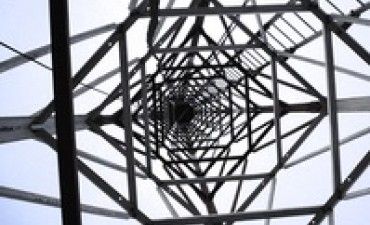類似セミナーへのお申込みはこちら
デンドライトはどのようなメカニズムで発生し、
リチウムイオン電池に様々な問題を引き起こすのか?
電極内を可視化し、観察するには?
デンドライトの析出、成長過程を徹底解説!
講師
1.バッテリーコンシェルジュ 代表 佐野 茂 氏
2.群馬大学 理工学部 環境創生理工学科 教授 工学博士 鳶島 真一 氏
3.(株)エマオス京都 代表取締役 石塚 紀生 氏
4.(株)住化分析センター マテリアル事業部 木村 宏 氏
5.岡山大学 大学院自然科学研究科 准教授 博士(理学) 後藤 和馬 氏
受講料
1名につき60,000円(消費税抜き・昼食・資料付き)
〔1社2名以上同時申込の場合のみ1名につき55,000円(税抜)〕
プログラム
【10:00〜11:15】
1.現行カーボン電極でのリチウム金属生成・成長機構およびそれに起因する問題
バッテリーコンシェルジュ 佐野 茂 氏
【講座概要】
自動車電動化の大きな流れの中で、リチウムイオン2次電池には膨大な市場が予測されています。パソコン・携帯電話のような民生用途及びハイブリッドカー用としては十分実績が積まれましたが、電気自動車用ははるかに高度な性能が要求されています。特に、エネルギー密度、寿命、安全性は大きなテーマです。安全性については、民生用で時々発火事故が起きたように、高エネルギー密度化のための詰込み過ぎによるデンドライトショートの発生による発火事故が懸念されます。
本セミナーではデンドライトショート発生機構を解り易く図説しますので、設計上の理解不足によるデンドライト発生、発火事故を事前に防止することができるようになります。電池技術者特に電気自動車用リチウムイオン2次電池の開発者にとって非常に有意義なセミナーです。
1.リチウムイオン2次電池の致命的欠陥
1-1 SEI(固体電解質界面)頼り
1-2 SEI 形成〜修復
1-3 電解液劣化
2.発火事故例と原因
2-1 発火事故例・社説
2-2 ボーイング火災事故・原因調査結果
2-3 ノートパソコン用バッテリーパックのリコール
2-4 発火原因:異物混入による内部短絡説
2-5 正極分解・熱暴走
3.デンドライトショート
3-1 デンドライトショートの図解
3-2 充電制御の盲点
3-3 デンドライトショートの初歩
3-4 劣化によるデンドライト発生
3-5 電気化学的考察
3-6 デンドライトショートと突然死の予測
3-7 全固体電池/次世代電池におけるデンドライトショート
【質疑応答】
【11:25〜12:40】
2.リチウムデンドライトの生成、成長機構とそれに起因する問題
群馬大学 鳶島 真一 氏
【講演概要】
リチウムデンドライトはリチウム金属電池のみならずリチウムイオン電池でも電池の性能劣化と安全性に影響する解決すべき課題である。本講演ではデンドライトの基礎と対策の検討例について議論し高性能リチウム電池開発の助としたい。
1.リチウムイオン電池実用化の歴史的経緯
2.デンドライトとは?
3.電気めっきとデンドライト
4.デンドライト発生メカニズム
4-1 物理的条件の影響
4-2 化学的条件の影響
5.リチウム電池におけるデンドライト発生と電池性能および安全性との関係
6.デンドライト抑制対策
6-1 負極、
6-2 電解液
6-3 セパレータ
6-4 電池構成
6-5 充電制御
7.市販リチウムイオン電池のデンドライトによる市場トラブル例
8.リチウムイオン電池の今後の展開とデンドライト
【質疑応答】
【13:25〜14:40】
3.「ポリマーモノリス」を用いたセパレータの安全性、耐熱性向上とデンドライトの抑制効果
(株)エマオス京都 石塚 紀生 氏
【講演概要】
モノリスは、マイクロメートル領域の貫通型細孔と骨格が絡み合った共連続構造を有する新規な多孔質体である。 本講座では、モノリスの作製と特長および用途開発について説明し、リチウムイオン電池のセパレータへの適用の可能性や取り組みについて紹介する。
1.はじめに〜モノリスとは?〜
2.モノリスの種類と作製
3.モノリスの用途開発
4.ポリマーモノリスのリチウムイオン電池用セパレータへの適用
4-1 モノリス膜の作製
4-2 モノリス膜の特性
5.モノリス複合膜
6.モノリス膜の今後と課題
【質疑応答】
【14:50〜16:05】
4.リチウムデンドライト観察をはじめとしたin situ分析及び電極合剤の分散性評価
(株)住化分析センター 木村 宏 氏
【講演概要】
車載用へのLiイオン電池(LIB)の展開において、負極でのデンドライト発生は、電池内の短絡発生につながるため抑制する必要がある。そのためには、電池内で過充電箇所が発生しないよう、電極における反応分布の均一性が重要である。
本講座では、負極における反応分布を観測する手法として、カラー共焦点顕微鏡によるin situ顕微鏡観察を紹介する。本手法における、充放電における反応分布、Liデンドライトの発生過程、低温における電解液凝固を説明する。また、反応分布に関連する合剤電極の分散性評価についても紹介する。導電助剤、バインダーの分散性等が、実際の電池特性にどのように寄与するのかを説明する。これらの手法は、電極の製造法の最適化や品質管理の分野において、分析支援できるものと考えられる。
1.はじめに
2.充放電作動条件における反応分布評価(in situ分析)
2-1 白色光共焦点顕微鏡によるin situ分析
2-2 負極黒鉛における反応分布の可視化
2-3 リチウムデンドライト発生過程の観察
2-4 低温充放電による電解液の凝固観察
3.合剤分散性による電池性能への寄与
3-1 導電助剤、バインダーの分散性評価―ラマンマッピング法、EPMA分析法
3-2 電極製造条件による分散性及び電池特性の関連性
3-3 電極内の活物質導通の可視化―SPM法
3-4 導通活物質割合と電池特性の関連性
【質疑応答】
【16:15〜17:00】
5.二次電池負極上のデンドライトの析出過程の観測
岡山大学 後藤 和馬 氏
【講座概要】
リチウムイオン電池の需要拡大に伴い、安全性に関する要求も高まってきている。電池が過充電されると負極活物質上にデンドライト状リチウムが析出し、セパレータを破って短絡の原因になるため、デンドライトの析出状況を的確に観測することが求められる。
本講演では、核磁気共鳴法(NMR)を用いたリチウムイオン電池やその他二次電池の負極上のデンドライト析出過程の精密観測について、その場観測(オペランド解析)を用いた最新の研究成果を紹介する。
固体NMRによる二次電池の解析方法についての一般的な内容との解説と、トピックスとしての最新の研究成果の紹介が本講演のメインになります。直接観測では難しい、デンドライトの析出開始タイミングの精密な見積が可能な技術を紹介します。
1.核磁気共鳴の原理
1-1 NMRとは
1-2 NMR測定の長所と短所
1-3 溶液NMRと固体NMR
1-4 オペランド解析
2.炭素負極,その他電池材料のNMR観測
2-1 リチウムイオン電池負極上のデンドライト生成過程および時間経過による変化過程の観測
2-2 ナトリウムイオン電池電極内ナトリウムの状態分析
【質疑応答】
受講料
64,800円(税込)/人
類似セミナー
関連セミナー
もっと見る関連教材
もっと見る関連記事
もっと見る-
レアアースレス・モーターとは?レアアースフリーの衝撃、環境と経済を変えるモーターの進化論
【目次】 現代社会はモーターなしには成り立ちません。スマートフォンから電気自動車、産業用ロボットに至るまで、私たちの生活のあらゆる側... -
DEHPとは?危険性や健康への影響、身近な製品例と安全な代替品まで解説
【目次】 DEHP(フタル酸ジエチルヘキシル)、この耳慣れない化学物質が、私たちの日常生活に深く根ざしていることをご... -
HVDC(高圧直流送電)とは?HVDCが描く未来、再エネ社会を繋ぐ革新送電
【目次】 現代社会において、電力は私たちの生活を支える不可欠なインフラです。しかし、その電力供給のあり方は、気候変動問題への対応やエ... -
エネルギーハーベスティングとは?自然の力がエネルギーの新しい形に、その現状と展望を解説
【目次】 エネルギーハーベスティングは、私たちの身の回りに存在する太陽光、熱、振動、電波といった微小なエネルギーを「収穫...