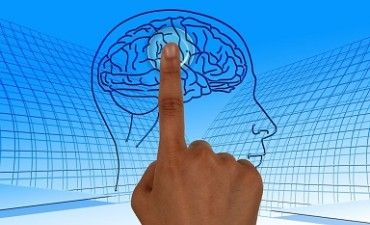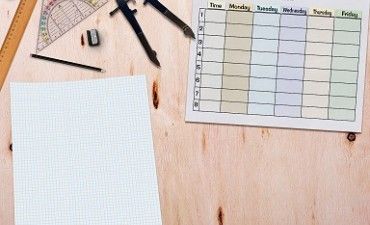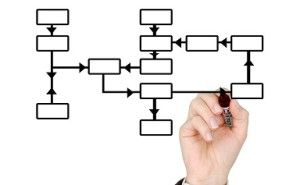系統図法(ツリーダイヤグラム)とは、キーワードからわかりやすく解説
1. 系統図法(ツリーダイヤグラム)とは
系統図法(ツリーダイヤグラム)とは、ものごとを考える過程で、ある項目と因果関係のある複数の項目を順次ツリー状に結び付けてゆくことで系統的に整理する方法です。 目的を実現する方策・手段を展開してゆく「方策展開型」と、組織図などのように業務や機能の構成要素を系統的に整理する「構成要素展開型」に大別できます。 前者は信頼性向上手法である「FTA(Fault Tree Analysis)」後者は設計の準備段階で使われる「機能展開」がその範疇に含まれると考えられ、いずれも思考パターンを見える化した「マインドマップ」とも通じるものがあり、ものごとを整理する時に自然に取られる思考法と言えそうです。
2. 2種類の系統図法とは
系統図法とは、目的・目標を達成するために必要な手段・方策を、系統的に展開した“系統図”を作成することによって、問題(事象)の全貌に一覧性を与えて、問題の重点を明確にしたり、目的・目標を達成するための最適手段・方策を追求して行く手法です。
系統図法で用いる系統図は、大きく分けて、対象を構成している要素を目的-手段の関係に展開する「構成要素展開型」と、問題を解決したり、目的・目標を果すための手段・方策に展開していく「方策展開型」の2種類があります。
3. 問題の要因を掘り下げる系統図法
例えば、親和図法で問題の洗い出しを行った後や、管理図法などでモニタリングをした結果、出てきた問題(例:昨年に比べ売上悪化)に対し、その問題の要因(原因)を探る時に使います。
4. 解決策を具体化する系統図法
「解決策を具体化する系統図法」というものがあります。問題の要因を掘り下げた後、その要因に対しその解決策を案出するのに使ったりします。具体的なアクションが見えるまで、掘り下げます。
5. 方策展開型系統図の具体的な活用
系統図法、特に方策展開型の活用は、単なるアイデア出しに留まらず、戦略的な計画立案においてその真価を発揮します。売上悪化などの問題の要因が特定された後、その要因を解消するための具体的な方策(手段)をブレイクダウンしていく過程です。例えば、「顧客満足度の向上」という上位の方策に対し、「アフターサービスの質改善」「製品レビューの収集と反映」「顧客サポートの迅速化」といった中位の方策を展開し、さらにそれぞれを下位の具体的なアクション、例えば「サポート部門の24時間体制の試験導入」「製品FAQの拡充とAIチャットボットの導入」といったレベルまで掘り下げます。この展開は、実行可能な最小単位のタスクにまで落とし込むことが目標です。このプロセスを経ることで、抽象的な目標が具体的な行動計画へと変換され、誰が、何を、いつまでに行うべきかが明確になります。
6. 系統図法と他のQC七つ道具との連携
系統図法は、単独で完結する手法ではなく、他の品質管理(QC)のツールと連携することで、より強力な問題解決のフレームワークとなります。
まず、問題の混沌とした情報を整理する親和図法や、問題の要因を網羅的に洗い出す特性要因図(フィッシュボーン図)で得られた要素を、より論理的かつ階層的に構造化する際に系統図法が役立ちます。親和図でグルーピングされた「テーマ」を系統図の起点とし、そのテーマを実現するための具体的な手段を深掘りしていくのです。
また、抽出された方策の優先順位を決定する際には、マトリックス図法やアローダイアグラムが連携します。系統図で展開された多数の手段の中から、コスト、効果、実現可能性などの複数の視点から最適なものを選択するためにマトリックス図法を用います。そして、その選ばれた手段群の実行スケジュールや工程管理を行うためにアローダイアグラムへと移行することで、計画の実行段階まで一貫した管理が可能になります。系統図法は、これらのツールの間を繋ぐ「思考の架け橋」として機能し、問題解決の一連の流れに構造と論理性を与えます。
7. 系統図作成のポイントと留意点
系統図法を効果的に活用するためには、いくつかのポイントがあります。
第一に、展開のレベル感を揃えることです。一つの階層で並列に展開される要素は、論理的な粒度が同等であることが望ましいです。粒度が異なると、展開の途中で論理の飛躍が生じ、抜けや漏れが発生しやすくなります。
第二に、「なぜ」または「どのように」という問いかけを繰り返すことです。上位の項目に対し「これを実現するためには、どのようにするのか?」と問いかけ、下位の手段を展開していきます。問題の要因を探る際は、「この事象はなぜ起こるのか?」と問いかけて原因を深掘りします。このシンプルな問いかけが、系統図の論理的な繋がりを担保します。
また、作成後の検証も重要です。展開された最下位の手段(方策)をすべて実行した場合に、本当に最上位の目的が達成できるのか、という論理的な妥当性をチェックする必要があります。この時、もし達成できないようであれば、どこかの展開に抜けや漏れ、あるいは誤りがあったことになります。
系統図法は、一見すると手間のかかる作業に見えますが、複雑な問題や大規模なプロジェクトにおいて、関係者全員の認識統一を図り、無駄のない効率的な実行を可能にするための不可欠なツールです。思考を可視化し、それを論理的な構造に落とし込む力は、現代のビジネスにおける意思決定の質を高める上で極めて重要と言えるでしょう。