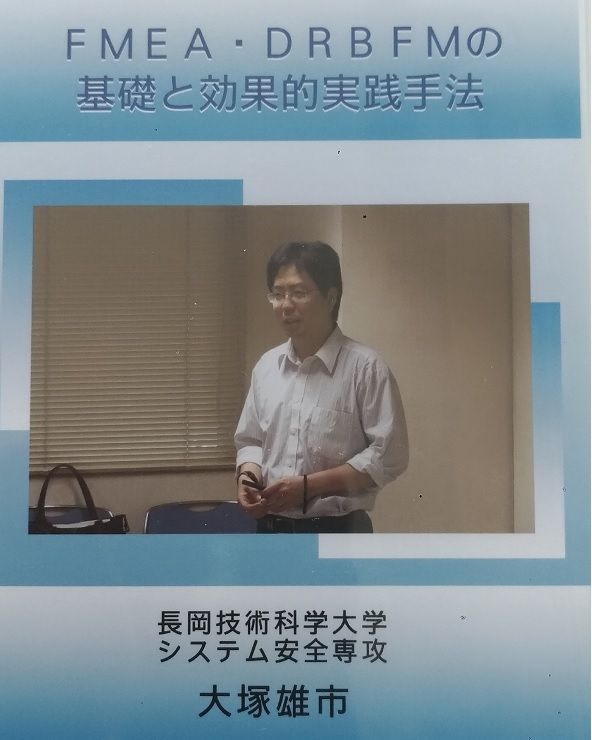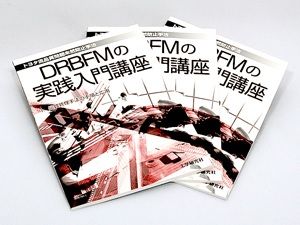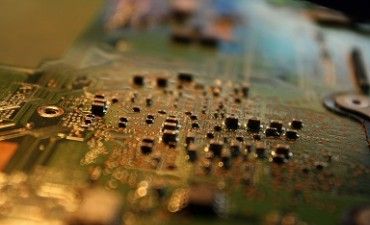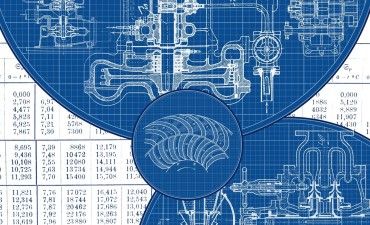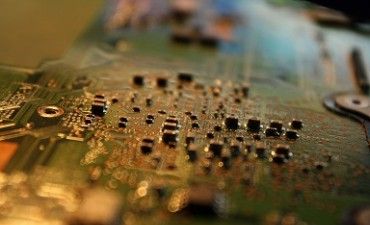図面情報を有効活用した設計FMEA/工程FMEAの具体的な進め方~図面から故障原因の特定から故障の影響の判定・評価点の算出まで~【会場/WEB選択可】WEB受講の場合のみ,ライブ配信/アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可)
FMEAを形だけで終わらせない… 図面情報を活用し、形状や寸法・公差から潜在的な故障モードを的確に抽出し、原因と影響を評価点に落とし込む手法を解説します。事例と演習を通じ、設計FMEA・工程FMEAを実務で活かすための具体的な進め方を習得できます!!
【会場/WEB選択可】WEB受講の場合のみ:ライブ配信/アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可)
セミナー趣旨
図面は、製品と工程を理解し、潜在的な故障モード、その原因および影響を具体的に特定するための不可欠な情報源です。特に設計FMEAでは、図面上の形状および寸法・公差が有する機能に着目することで、見逃しがちな故障モードと故障原因を網羅的に洗い出すことができます。また、図面上の各寸法および公差で表現された機能に着目することで、これらを変更した際の製品機能および工程の変化や発生するリスク、すなわち故障モードを的確に導き出すことができます。
過去の事故例や故障例は「寸法不適」が故障モードの大半を占めるとされており、本講座では図面情報を有効活用した設計FMEA/工程FMEAの具体的な進め方を解説します。
故障モードの抽出や故障モードおよび原因に対する評価点(発生度・致命度・検出度)の付け方など、対象となる部品の形状や構造が考慮しながらの実施方法を紹介。事例と演習を通じて、製品機能の低下やリスクにつながる故障を予測し、信頼性と安全性を向上させる手法と、製品を部品や工程に展開し、各部品・各工程に対して項目を推定・検証する手法を習得いただきます。
さらには、皆さんがFMEAで悩みがちな評価点の付け方および評価方法を、具体的な数値と根拠ともに解説します。試験結果や設計標準、管理方法などをもとに評価点をつける手法が掴め、評価の妥当性を格段に向上できます。
受講対象・レベル
製品設計や開発の実務を行っている初心者から中堅の技術者。
必要な予備知識
機械工学の基礎があれば理解が進みます。
習得できる知識
1)設計FMEAと工程FMEAに関する基礎知識
2)実施手順
3)各段階・項目の評価法
4)故障モードを予測するコツ
5)設計FMEAと工程FMEAの具体的な作り方
セミナープログラム
1.FMEAの目的と構成
1-1 FMAEの目的と構成
①FMEAの構成と検討項目
②FMEAのフォーマット(設計FMEA/工程FMEA)
③故障・故障モード・故障の影響
1-2 FMEAの変遷
①MIL-STD-1629Aの制定
②QS-9000発表とPotential FMEA要求拡大
③TS 16949実践ガイド制定
④IEC 60812 第2版制定
1-3 FMEAの分類
機能FMEA/プロセスFMEA/構想FMEA/システムFMEA/設計FMEA/工程FMEA/使用FMEAなど各種目的に応じた実施方法
2.FMEAの実施手順と各段階・項目の評価法
2-1 FMEAの実施準備
①チーム編成
②必要情報(過去のトラブル事例、他社のトラブル事例、過去のFMEA実施資料、故障モード分類、ストレス―故障モード表、製造作業エラーモードなど)
2-2 設計FMEAの実施手順
2-3 工程FMEAの実施手順
2-4 故障モード抽出のコツ
①機能の細分化<設計FMEA>
②工程の細分化<工程FMEA>
③図面寸法機能からの導出(寸法変化に伴う機能損失)<設計FMEA>
④キーワードからの類推(キーワード+機能、HAZOP誘導語、製造エラーモード)
⑤過去の知見や経験則(生成AIを活用してみる)
⑥故障モードの分類(故障の性質/発生部位/発生状況)
2-5 故障の原因分析と故障の影響の評価
①FTA:ツリー構造での原因探索<設計FMEA>
②動作分析<工程FMEA>
③信頼性ブロック図の利用
2-6 評価点の考え方とつけ方(ISO/TS 16949、QS 9000)
①発生度・致命度・検出度の具体的な算出・判定方法・算出例
②重要度PRNの見積もり
2-7 評価点改善結果のフィードバック
3.図面情報から故障モードを予測するコツ
3-1 各寸法の機能を明確にする
・直径・長さ・板厚・面取りなど機能を理解
3-2 寸法変化による機能損失(機能損失が故障モードに)
・経年変化などによる寸法の変更
3-3 故障リスクの特定による設計変更
4.設計FMEAの演習
・部品名展開・部品の機能・故障モードの抽出・故障の原因抽出・故障の影響抽出・評価点記入の一覧の流れを体得します。
・発生度(Occurrence)、致命度(Severity)、検出度(Detection)の各評価点について、それぞれのランク(10段階)に対する具体的な基準を、設計FMEAと工程FMEAそれぞれについて理解します。危険優先数(RPN)算出例への理解を深めます。
5.質疑応答・まとめ
セミナー講師
ほうきたコンサルタント 代表 伯耆田 淳 先生
1984年3月茨城大学工学研究科(修士課程)卒業
1984年4月(株)日立製作所入社
1984年4月~1987年1月
(株)日立製作所自動車機器事業部佐和工場開発部でターボチャージャの開発を推進しました。世界耐久レースに参加したマツダとマーチのレーシングカーに搭載のターボチャージャを開発しました。
1987年2月~1988年6月
(株)日立製作所自動車機器事業部佐和工場エンジン機器設計部でGM向け熱線流量計付きスロットルボディの開発を推進し、原価を37%低減しました。
1988年9月~1993年8月
日立オートモーティブプロダクツ(アメリカ)Inc.に駐在、設計部として、生産立ち上げ、部品の現地調達、品質問題解決、収支改善、プロジェクトマネージメント、現地における開発、試作、市場クレーム対応、顧客との製品開発、現地サプライヤとの技術および値段の交渉を推進しました。
1993年9月~1995年8月
(株)日立製作所自動車機器事業部佐和工場エンジン機器設計部の技師としてGMとフィアットのスロットルボディの開発を推進しました。1994年の4月から9月は日立オートモーティブプロダクツ(アメリカ)Inc.の開発問題解決のため現地で活動を推進しました。
1995年9月~1996年6月
日立オートモーティブプロダクツ(アメリカ)Inc.に駐在、設計部のシニアエンジニアとして、設計と購買の強化を実施しました。また、現地サプライヤとの関係を良好なものにして、原価低減と値段低減を推進しました。
1996年7月~2001年9月
日本側で発生したターボチャージャの開発問題解決のためアメリカから日本に戻り(株)日立製作所自動車機器事業部佐和工場エンジン機器設計部主任技師(1997年から)としてスズキ、いすゞのターボチャージャの開発を推進しました。また、フィアットのターボチャージャ受注活動で、競合他社と性能競争を行い、パラメータ設計で性能が1位となりました。
2001年10月~2006年1月
(株)日立製作所とボルグワーナーターボシステムズ(株)のジョイントベンチャーである日立ワーナーターボシステムズ(株)に出向して戦略購買課長としてグローバル原価低減を推進、さらに設計部主任技師としてターボチャージャの開発設計を推進しました。2003年~2005年にはボルグワーナー社との関係修復のため、ドイツでボルグワーナー社と活動を行いました。
2006年2月~2013年6月
日立オートモーティブシステムズ(株)EMS設計部の主任技師として、燃料系システム部品の開発を推進しました。また、日本に開発拠点を置くインジェクタとポンプの開発を推進しました。
2006年6月~2013年3月
日立オートモーティブプロダクツ(アメリカ)Inc.に駐在、設計部のダイレクターとしてアメリカでの高圧燃料供給システムのGMとの開発とその生産立ち上げを推進しました。エンジン騒音を低減するため、世界発となるインジェクタ吊り下げ式ラバーアイソレータシステムを開発し、300億円/年の売り上げを実現しました。また、高圧ポンプは現地生産を行いグローバル収支の改善を実施しました。
2013年4月~2017年6月
日立オートモーティブシステムズ(株)EMS設計部の担当部長として、燃料系システム部品の開発と日本、北米、欧州、中国の生産拠点の収支改善プロジェクト活動を推進しました。
2017年7月~2023年3月
日立オートモーティブプロダクツ(アメリカ)Inc.に駐在、設計部のシニアダイレクターとしてアメリカでの設計力強化、顧客とのモータ、インバータの製品開発、サプライヤとの部品現地調達、生産立ち上げを推進しました
2023年4月~2024年4月
日立Astemo株式会社の人材統括部総務部教育課に異動し、技術研修の開発や業務委託契約のシステムを完備したり、新規研修をホンダどのと協力して立ち上げ、さらに約30の研修を実施しました。
2024年5月から現在
ほうきたコンサルタントを立ち上げ、技術と英語の支援を推進中。
所属学会
日本機械学会に所属していましたが海外駐在のため退会
セミナー受講料
(消費税率10%込)1名:49,500円 同一セミナー同一企業同時複数人数申込みの場合 1名:44,000円
※WEB受講の場合、別途テキストの送付先1件につき、配送料1,210円(内税)を頂戴します。
テキスト:製本資料(受講料に含む)
受講料
49,500円(税込)/人