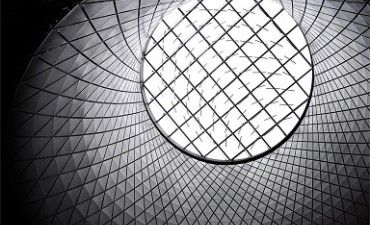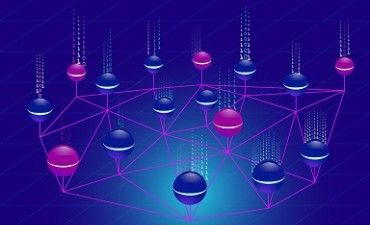・静電気放電と発火リスクの関係、保守・管理の注意点等、基礎から解説
・工程内の静電気リスクを見つける眼を養う
セミナー趣旨
国内での事業所火災件数は年々減少している一方、静電気による火災件数は横ばいが続いています。静電気は目に見えないため、対策が取りづらいことが原因と考えられます。
本セミナーでは、静電気の基礎知識を学んだうえで、過去の災害事例の分析、静電気放電と発火リスクの関係や放電防止対策、保守・管理の注意点など、静電気事故の防止に役立つ基本的な知識の習得を目指します。
受講対象・レベル
・工場の管理責任者
・製造・生産にかかわる作業者・技術者・現場リーダー
・労働安全衛生法に基づく静電気対策を講じたい方
など
習得できる知識
・静電気の基礎知識
・静電気事故を防ぐための基本的な考え方
・静電気対策機器の情報と使い方
・工程内の静電気リスクを見つける眼
セミナープログラム
1. 静電気と災害
1.1 静電気火災の発生状況
1.2 着火の3要素
1.3 災害事例
2. 静電気の基礎知識
2.1 帯電
2.1.1 帯電とは
2.1.2 帯電列
2.1.3 強く帯電する要因
2.2 誘導帯電
2.3 電荷・静電容量・電圧
2.4 接地
2.4.1 接地の意味
2.4.2 人体の接地
2.4.3 導体の接地
2.4.4 不導体について
3. 接地の注意点
3.1 浮遊導体について
3.2 不導体について
4. 人体の接地
4.1 基本は靴と床
4.2 リストストラップ
4.3 その他の対策
5. 設備の接地
5.1 同電位化の徹底
5.2 接地方法とNG例
6. 不導体の静電気対策
6.1 工程でよく使われる不導体材料
6.2 基本は導電性付与
6.3 イオナイザ
6.4 その他の手段
7. 放電
7.1 絶縁破壊
7.2 最小着火エネルギー
7.3 放電の種類
8. 静電気対策
8.1 導体の同電位化
8.2 不導体の除去・除電
8.3 対策への現場理解と徹底(教育・コミュニケーション)
9. 気体・液体・粉体特有の静電気対策
10. 静電気対策の代表的な注意箇所
11. 災害事例の分析
12. 測定・評価方法
12.1 測定機器
12.2 評価方法
12.3 管理方法
13. 教育・組織・体制
13.1 教育の必要性
13.2 トラブル事例
13.3 定期検査
13.4 リスク評価・原因分析
14. まとめ
<質疑応答>
*途中、小休憩を挟みます。
セミナー講師
長岡産業(株) 研究開発室 博士(農学) 小原 有策 氏
■ご略歴
10年間にわたり静電気対策フィルム『スタクリア』の開発・上市に携わりつつ、
2020年以降は静電気情報サイト『静電気制御コム』を立ち上げ、より広範な静電気対策サービスに取り組んでいる。
これまで化学・半導体・繊維・光学・メディカル分野など、多岐にわたり静電気問題のサポートを実施している。
≪学位・資格≫
博士(農学)/一般社団法人静電気学会会員(賛助会員)/
一般財団法人日本電子部品信頼性センター ESDコーディネーター/サイエンスコミュニケーター
セミナー受講料
【オンライン受講(見逃し視聴なし)】:1名 45,100円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき34,100円
【オンライン受講(見逃し視聴あり)】:1名 50,600円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき39,600円
*学校法人割引:学生、教員のご参加は受講料50%割引。
受講について
- 配布資料はPDF等のデータで送付予定です。受取方法はメールでご案内致します。
(開催1週前~前日までには送付致します)
※準備の都合上、開催1営業日前の12:00までにお申し込みをお願い致します。
(土、日、祝日は営業日としてカウント致しません。) - 受講にあたってこちらをご確認の上、お申し込みください。
- Zoomを使用したオンラインセミナーです
→環境の確認についてこちらからご確認ください - 申込み時に(見逃し視聴有り)を選択された方は、見逃し視聴が可能です
→こちらをご確認ください
受講料
45,100円(税込)/人
関連セミナー
もっと見る関連教材
もっと見る関連記事
もっと見る-
DEHPとは?危険性や健康への影響、身近な製品例と安全な代替品まで解説
【目次】 DEHP(フタル酸ジエチルヘキシル)、この耳慣れない化学物質が、私たちの日常生活に深く根ざしていることをご... -
ナノテクノロジーとは?基礎から最新応用、未来の課題まで徹底解説
【目次】 1ナノメートルは髪の毛の太さの約10万分の1。ナノテクノロジーとは、原子や分子といった極限の小ささの世界で物質を自在に設計... -
超流動とはどういう現象?仕組みや超伝導との違いなどを詳しく解説
【目次】 超流動とは、物質が極低温において示す特異な現象であり、流体が摩擦なしに流れる状態を指します。超流動の現象(特にヘリウム-4... -
フェルミ準位とは?半導体・金属での違いや応用例をわかりやすく解説
【目次】 フェルミ準位は、物理学や材料科学において非常に重要な概念です。特に半導体や金属の電子構造を理解する上で欠かせない要素となっ...