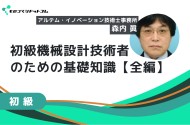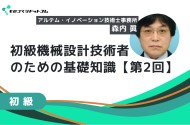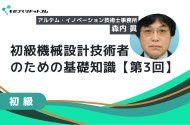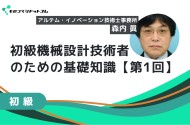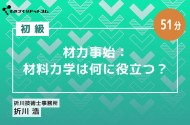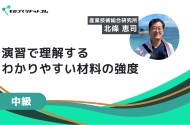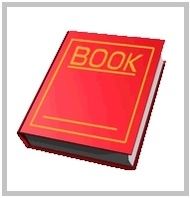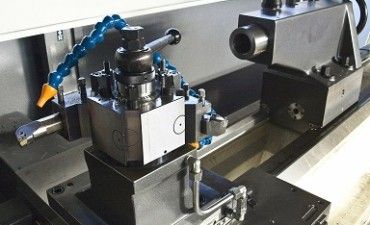実務で明日から活用する
実務で強度計算をするための材料力学,引張・曲げなどの強度計算,金属材料・プラスチックに関する材料特性,両者の違いなどについて,複数の例題を交え,強度設計の全体像を分かりやすく解説する特別セミナー
【WEB受講(Zoomセミナー)】ライブ配信(アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可)付き)
セミナー趣旨
近年、製品が安全であることや不具合が少ないことは、付加価値ではなく当たり前のことだと認識されるようになってきました。もし、消費者の期待を裏切るような低い品質の場合、ネットショップの製品レビューやSNSなどによって瞬く間に拡散してしまいます。品質を確保する取組みが、かつてないほど重要になっているといえます。特に強度に関わる不具合は安全面の問題に直結し、リコールにつながることもあります。強度設計に関するスキルは、設計者が学ぶべきことの中で最も優先順位が高いテーマの一つだといってよいでしょう。
一方、強度設計のスキルを身につけようとすると、材料力学や材料学、信頼性工学など非常に多くのことを学ぶ必要があることに気づきます。多忙な業務の中、とてもハードルが高いと感じる技術者が多いのではないでしょうか。
本セミナーは、このような技術者向けに、強度設計の全体像を効率的に理解できるように構成しています。式の導出などは最低限に抑え、実務での強度設計ができるようになることを目指します。前半は強度設計に必要な材料力学の基礎、後半は材料特性やばらつきへの対応手法、デジタルツールの活用方法などを解説しています。実務で課題となりやすい金属材料とプラスチックの違いにも言及した上で、多くの例題を使いながらわかりやすく解説します。
<進呈>
講師著書:「図解! わかりやすーい強度設計実務入門 基礎から学べる機械設計の材料強度と強度計算」(日刊工業新聞社)を進呈致します。
受講者の声
- 強度計算、強度設計に関する知識を感覚的に捉えることができ実務にすぐ活かすことができそうです。ありがとうございました。
- 参考になりました。各ページにて著書のどこを見ればいいかなどが書いてあり、分かりやすかったです。
- 仕事で必要な知識を学べたのでとても良かったです。 非常に分かりやすくためになりました。
- 有意義に学べました。ありがとうございました。講師の話は非常に分かりやすくよかった。
受講対象・レベル
設計・開発部門/品質部門/生産技術部門などの若手技術者、
経験5~6年までの技術者
必要な予備知識
特に必要ありません
習得できる知識
1)材料力学の基礎がわかる
2)機械特性と基準強度の考え方がわかる
3)材料強度のばらつきへの対応方法がわかる
セミナープログラム
1. 強度設計に必要な材料力学の基本はたったこれだけ
1-1 単位
1-2 力
1-3 モーメント
1-4 支持条件
1-5 荷重/応力/ひずみ
1-6 フックの法則
※例題を解きながら理解を深めていきます。
2. 基本的な強度計算の方法(1)
2-1 引張荷重/圧縮荷重
2-2 曲げ荷重
2-2-1 はりの強度計算の進め方
2-2-2 はりの種類
2-2-3 曲げモーメント
2-2-4 断面係数とはりに発生する応力
2-2-5 断面二次モーメントとはりのたわみ
※例題を解きながら理解を深めていきます。
3. 基本的な強度計算の方法(2)
3-1 せん断荷重
3-2 ねじり荷重
3-3 座屈
3-4 応力集中
※例題を解きながら理解を深めていきます。
4. 材料強度と強度設計
4-1 材料の基準強度
4-2 静的強度
4-2-1 応力-ひずみ曲線
4-2-2 金属材料の強度
4-2-3 プラスチックの強度
4-2-4 静的強度における基準強度の考え方
4-3 動的強度
4-3-1 疲労
4-3-2 衝撃
4-4 環境的影響
5. ばらつきへの対応とデジタルツールの活用
5-1 ストレンス-ストレングスモデル
5-2 材料強度のばらつき
5-3 許容応力と安全率
5-4 CAE
5-5 生成AIの活用
セミナー講師
田口技術士事務所 代表 田口 宏之 先生
技術士(機械部門)、博士(情報工学)
元 TOTO(株
九州大学大学院修士課程修了後、東陶機器㈱(現、TOTO㈱)に入社。
12年間の在職中、ユニットバス、洗面化粧台、電気温水器等の水回り製品の設計・開発業務に従事。金属、プラスチック、ゴム、木質材料など様々な材料を使った製品設計を経験。
また、商品企画から3DCAD、CAE、製品評価、設計部門改革に至るまで、設計業務に関するあらゆることを自らの手を動かして実践。それらの経験をベースとした講演、コンサルティングには定評がある。
独立後、九州工業大学の博士課程で3Dプリンタ部品の特性や機械学習を使った設計支援方法の研究に従事。
2024年に博士(情報工学)を取得。
セミナー受講料
(消費税率10%込)1名:49,500円 同一セミナー同一企業同時複数人数申込みの場合 1名:44,000円
※別途テキストの送付先1件につき、配送料1,210円(内税)を頂戴します。
テキスト:製本資料(受講料に含む)
受講料
49,500円(税込)/人
類似セミナー
関連セミナー
もっと見る関連教材
もっと見る関連記事
もっと見る-
工作機械とは?種類と役割、加工技術と未来の可能性をわかりやすく解説
【目次】 工作機械は、現代の製造業において欠かせない存在です。これらの機械は、金属やプラスチックなどの材料を加工し、さま... -
弾性限界とは?定義や求め方を応力ひずみ曲線を用いて解説!
【目次】 弾性限界(弾性限度とも呼ばれる)は、材料が外部からの力に対してどのように反応するかを理解する上で重要な概念です。特に応力ひ... -
ロボット工学とは何か?構成技術、学習方法、応用分野、AIとの相乗効果も!
ロボットといえば大昔はSF小説や漫画・アニメ・特撮の世界のものでしたが、現代では社会のさまざまな分野に浸透し、その姿や機能も多種多様なものとなっていま... -
ポアソン比とはどういう意味?求め方やヤング率との関係、活用例を解説
機械装置や構造物などの設計で、構造計算や材料の強度計算をする際に登場する数値のひとつに「ポアソン比」があります。よく使う数値で言葉には馴染みがあり、意...