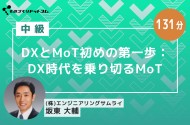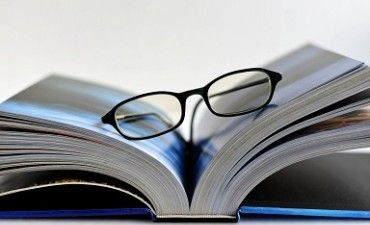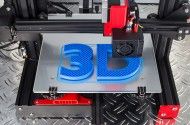
未来の食を変える! 3Dプリンターとフードテックの革新と挑戦【LIVE配信・WEBセミナー】
AIによる新サービスモデル、社会実装と他分野との連携・応用事例と今後の課題、食品のDXのための新技術について解説!
■本講座の注目ポイント
「フードテック」の中でも、今後の大きな成長が期待されているのが「3Dフードプリンター」です。
これは単に「美的に優れた食材」を生産するだけでなく、IT技術やデータ管理を駆使し、「健康管理システム(ヘルステック)」と連携することによって、個々のニーズに最適化された食品を提供する新しいサービスの展開へとつながります。
COOLD FOODの開発や低温凍結技術、細胞性食肉の創製に関連する3Dバイオプリンターの役割に注目し、これらの技術がどのように持続可能な社会に貢献できるか、その可能性や将来性、さらには現時点における課題、そして食品のDXのための新技術〜食べられるデータ、透過撮影技術〜についても具体的な事例を交えながら解説します。
セミナープログラム
【第1講】 未来の食を変える:3Dプリンターとフードテックの革新と挑戦
【時間】 13:00-13:45
【講師】山形大学工学部 機械システム工学科 材料・構造・デザイン領域/教授 古川 英光 氏
【講演主旨】
本講座では、3Dプリンター技術の基礎から食品分野における最新の応用例までを学びます。特に、COOLD FOODの開発や低温凍結技術、細胞性食肉の創製に関連する3Dバイオプリンターの役割に注目し、これらの技術がどのように持続可能な社会に貢献できるかを理解します。受講者は、最新のフードテックと3Dプリンターの可能性を学び、今後の研究や開発の方向性について具体的な示唆を得ることができます。
【プログラム】
・3Dプリンター技術の概要と食品分野での応用事例
・クールドな凍結食材「COOLD FOOD」の開発事例紹介
・低温凍結粉砕含水ゲル粉末を使った長期保存技術
・3Dフードプリンターの社会実装に向けた課題と展望
・テーラーメイド細胞性食肉の創製における3Dバイオプリンターの役割 未来のフードテックと3Dプリンターの可能性
【キーワード】
3Dプリンター, フードテック, 持続可能な技術, クールドフード, バイオプリンター
【講演の最大のPRポイント】
持続可能な未来を切り拓くための最先端の3D/4Dプリンティング技術の社会実装について知る機会。食品分野での応用や社会に与えるインパクトを具体的に理解できます。
【習得できる知識】
・3D/4Dプリンティング技術の基礎
・フードテックの最新応用事例
・持続可能な食品保存技術
・社会実装に向けた課題と展望
【第2講】 3Dフードプリンターとロボット・AIによる新サービスモデル~社会実装と他分野との連携・応用事例と今後の課題~
【時間】 14:00-15:00
【講師】ミツイワ株式会社 デジタルイノベーション推進本部ファクトリーイノベーション推進部テクノロジー推進課 シニアマネージャー 本多 隆史 氏
【講演主旨】
近年、特にここ2~3年にわたり注目を集めている「フードテック」は、多様な分野において新たな商品やサービスが次々と創出されています。その中でも、今後の大きな成長が期待されているのが「3Dフードプリンター」です。これは単に「美的に優れた食材」を生産するだけでなく、IT技術やデータ管理を駆使し、「健康管理システム(ヘルステック)」と連携することによって、個々のニーズに最適化された食品を提供する新しいサービスの展開へとつながります。このように、3Dフードプリンターは未来の食事体験において不可欠な要素であると考えています。今回の講演では、その可能性や将来性、さらには現時点における課題について、具体的な事例を交えながら考察いたします。
【プログラム】
1.3Dフードプリンターの歴史(ミツイワ紹介含)
・工業用3Dプリンターの遷移、及びそこから派生した3Dフードプリンターの遷移
2.3Dフードプリンターの仕組
・「エアー式」「機械式」「その他」方式の違いと機能差
3.3Dフードプリンターのメリット
・デザイン面、データ管理の面からの産み出されるメリット
4.3Dフードプリンターのデメリット・注意点(及び 現時点での対応策)
・現時点におけるデメリットについて(AIやロボットでの解決策)
5.近未来における3Dフードプリンターの社会実装案
6.3Dフードプリンターの将来性と課題
7.おわりに
【キーワード】
3Dフードプリンター、マスカスマイゼーション、パーソナライズ、ミツイワ、フードテック、ヘルステックと食事、フードロス
【講演の最大のPRポイント】
近年、注目を集めているものの、その具体的な活用事例や将来性については十分に理解が浸透していない。本稿では、これまでに蓄積した知識や経験、ならびにお客様からのフィードバックを基に、その潜在的な可能性や、社会実装への取組みを推進している状況について述べる。
【習得できる知識】
・「3Dフードプリンター」の基礎知識
・「3Dフードプリンター」の現在地
・「3Dフードプリンター」の課題と将来性
【第3講】 食品のDXのための新技術 〜食べられるデータ、透過撮影技術〜
【時間】 15:15-16:30
【講師】国立大学法人埼玉大学 理工学研究科/准教授 プンポンサノン パリンヤ 氏
【講演主旨】
本講座では、ヒューマンコンピューターインタラクション(HCI)分野向けて、食品デジタルファブリケーション(食品3Dプリント技術、レーザーカッティング技術等)を使用して食品に情報を書き込み手法に着目して解説します。 また、透過撮影や画像処理技術を使用して食品から書き込んだデータを読み込み手法も紹介します。 最後に、実用化へ向けた課題や議論している、ロボットを使用して食品処理や人間と食品インタラクションと繋がる研究、および潜在的な産業用途における将来の使用についてご紹介します。
【プログラム】
1 人間と食品の相互作用に関する最近技術
2 食品デジタルファブリケーション
3 食品に情報を書き込み手法
3.1 食品3Dプリントの例
3.2 レーザーカッティングの例
4 食品からデータを読み込み手法
5 実用化へ向けた課題や議論など
6 質疑応答
【キーワード】
ヒューマンコンピューターインタラクション(HCI)、デジタルファブリケーション、3Dプリント技術、データ書き込み、画像処理
【講演の最大のPRポイント】
デジタルファブリケーション技術は, 食とそのインタラクションをデジタル領域と空間的に連動させることで, 食とダイニングのかつてない変革を約束する技術である.本講演では, 食品3Dプリンターを設備として活用し, 食品とその食品情報を局所的に制御し, 食品に新たな創造性を持たせ、作成方法、実用化に向けた課題や今後の展望についても述べる。
【習得できる知識】
・食品デジタルファブリケーション技術の基礎知識
・食べられるデータの作製方法
・食べられるデータの今後の展開と課題
セミナー講師
第1部 山形大学工学部 機械システム工学科 材料・構造・デザイン領域/教授 古川 英光 氏
第2部 ミツイワ株式会社 デジタルイノベーション推進本部
ファクトリーイノベーション推進部テクノロジー推進課 シニアマネージャー 本多 隆史 氏
第3部 国立大学法人埼玉大学 理工学研究科/准教授 プンポンサノン パリンヤ 氏
セミナー受講料
【1名の場合】49,500円(税込、テキスト費用を含む)
2名以上は一人につき、16,500円が加算されます。
主催者
開催場所
全国