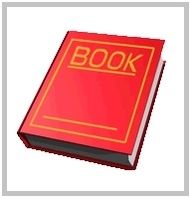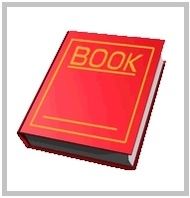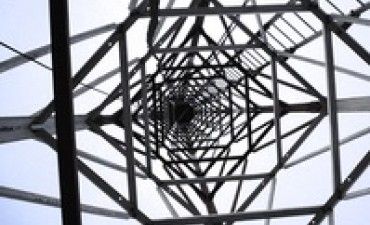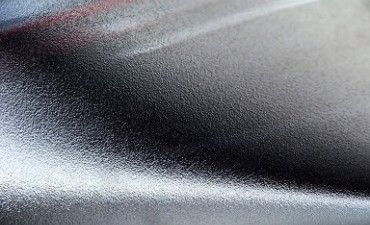半導体/プリント基板へのめっきの基礎と最新技術動向【LIVE配信・WEBセミナー】
★2024年4月25日WEBでオンライン開講。第一人者の関東学院大学 理工学部 表面工学学系 教授 小岩 一郎 先生が高密度実装技術、高機能化・小型化を支えるめっき技術にはじまり、半導体を活かすめっき技術、環境とめっき技術、非水溶媒を用いた新しいめっき技術にまで触れるまたとない講座です。
■注目ポイント
★5G用ポリマーへの湿式処理と紫外線処理の知識、5G時代に必要不可欠な低粗度での高密着力創生方法の知識が身につく!
★高密度実装でのウエハレベルチップサイズパッケージ、部品内蔵基板技術でも重要なキーテクノロジーであるめっきを学ぶことが出来る
セミナー趣旨
1970年代にスパッタリング法が活発に実用化され、「めっき技術」の研究が軽視されていったが、1980年代に磁気ヘッドや1997年に半導体の銅配線にめっきが使用され、めっき技術への社会的なニーズが高まった。さらに、ウエハ上の薄膜形成に、上述のIBMによる銅めっき(ダマシン法)により、電気めっきが使用されたことにより、後工程のウエハレベルチップサイズパッケージにも使用されるようになった。異方性導電性テープ中の導電粒子にも、貫通電極にも、部品内蔵基板にもめっき法が使用されている。さらに、厚さが必要な高密度実装でのウエハレベルチップサイズパッケージや部品内蔵基板技術でも、めっき技術が重要なキーテクノロジーとなっている。さらに、有機溶媒からのアルミニウムのめっきなども活発に研究されている。その他の新しいめっき技術の紹介も行う。また、米国や欧州などの産業創生方法についても解説する
【キーワード】
高密度実装技術、高機能化・小型化を支えるめっき技術、半導体を活かすめっき技術、環境とめっき技術、非水溶媒を用いた新しいめっき技術
【講演のポイント】
大学時代に、卒業論文、修士論文、博士論文を「めっき技術」で終了し、その後、沖電気工業株式会社で17年間、研究開発に従事したのちに、関東学院大学でめっきの研究を行っているので、「学」だけでなく、「産」も経験している。
習得できる知識
・5G用ポリマーへの湿式処理と紫外線処理の知識
・5G時代に必要不可欠な低粗度での高密着力創生方法の知識
・半導体関連へのめっき技術の知識
・無電解ニッケルーリンめっきの知識
・無電解銅めっきの知識
・非水溶媒を用いたあたらしいめっき技術の知識
セミナープログラム
1. 今、めっき法はエレクトロニクスデバイスでの重要度が高まっているのか?
1-1 小型化・多機能化の進展を支える技術
1-2 実装技術の必要性
1-3 エネルギー分野やヘルスケア分野への応用
2. めっき法の躍進
2-1 今までのめっき技術
2-2 スパッタリング法との比較
2-3 エレクトロニクスにめっきが使用されるようになる2つの要素
2-4 現在のエレクトロニクス分野へのめっき法の適用
2-5 エレクトロニクス分野へめっき法を使用する利点
2-6 エレクトロニクス分野へめっき法を利用する際の注意点
3. エレクトロニクスデバイスを進化させるめっき技術
3-1 めっき法とは
3-2 プリント基板の微細化(配線形成技術、基板の平坦化)
3-3 プリント基板の積層化(ビア技術)
3-4 積層チップの貫通電極
3-5 異方性導電粒子の作製法
3-6 ウエハにめっきするバンプ形成技術
3-7 フレキシブル配線板とITOの接合
3-8 ワイヤーボンディング用金めっきの薄膜化
3-9 コネクタのめっき
3-10 チップ部品のめっき
3-11 大型デバイスのめっき
3-12 めっき法によるガラスマスクの作製
3-13 医療分野へのめっき技術の展開
3-14 粒子を用いた反応性分散めっき
3-15 非懸濁液からの分散めっき膜の作製(Zn₋Al2O3、Zn-TiO2)
3-16 その他(放熱材料としてのCu-Mo合金など)
4. 非水溶媒を用いた新しいめっき技術
4-1 非水溶媒(有機溶媒とイオン液体)とは
4-2 溶媒をめっき法に用いる利点
4-3 非水溶媒をもちいためっき法の例(AlおよびAl合金を中心に説明)
5. 環境に対する注意点
5-1 シアンを含まないめっき浴からのシアンの検出
5-2 めっき法による環境問題の過去の知見
5-3 めっき法を用いる時の環境に対して新たに必要となる知見
6. その他の新しいめっき技術
【質疑応答】
セミナー講師
関東学院大学 理工学部 表面工学学系 教授 小岩 一郎 氏
セミナー受講料
【1名の場合】45,100円(税込、資料作成費用を含む)
2名以上は一人につき、16,500円が加算されます。
受講料
45,100円(税込)/人