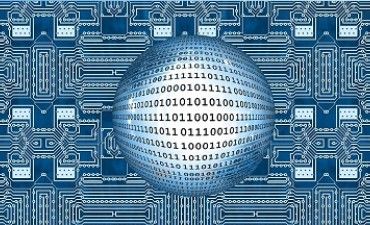以下の類似セミナーへのお申込みをご検討ください。
基礎から構造・物性、応用まで丁寧に解説します!
エポキシ樹脂の重要なポイントをしっかり習得できるセミナーです!
セミナー趣旨
基礎編ではエポキシ樹脂の製造方法からその不純物などエポキシ樹脂の基礎から時間をかけて丁寧に解説します。
構造・物性編では主にエポキシ樹脂の分子骨格と物理性状値(軟化点や粘度)、硬化性,耐熱性の関係を,データをもとに解説し,引き続き電気電子材用向けエポキシ樹脂が必要とされる機能を紹介します。
設計・応用編では耐熱性と相反する諸特性を基礎物性理論と硬化物データを関連付けながら解説し,それぞれ相反関係にある機能を両立する分子デザインとその合成技術について紹介します。また最近のトピックスとして低誘電率化の手段として注目されている活性エステル型硬化剤について解説を行います。主に電気電子材料用向けエポキシ樹脂に焦点を当てたセミナーです。
習得できる知識
硬化物の耐熱性向上機構のみならず、課題との関連性が理解できます。資料もイラストを多用し分かりやすく解説します。
セミナープログラム
第1部 基礎編 エポキシ樹脂とは
1.熱硬化反応の概念
2.エポキシ樹脂と他の熱硬化性樹脂の比較
3.代表的なエポキシ樹脂の紹介
4.エポキシ樹脂の分類
4-1. 官能基数
4-2. 基本骨格
4-3. 製造方法
5.エポキシ樹脂の製造方法
6.エポキシ樹脂の不純物の紹介
7.エポキシ樹脂硬化物の作成方法
8.代表的な硬化剤の紹介(特徴や反応機構など)
8-1. ポリアミン型硬化剤
8-2. 酸無水物型硬化剤
8-3. ポリフェノール型硬化剤
8-4. 触媒硬化
第2部 構造・物性編
1.エポキシ樹脂の分子構造と性状値(粘度および軟化点)の関係
1-1.粘度および軟化点の理想設計
1-2.分子量と性状値の関係
1-3.骨格の剛直性と性状値の関係
1-4.水素結合の影響
2.エポキシ樹脂の分子構造と硬化性の関係
2-1.立体障害の影響
2-2.官能基濃度の影響
2-3.官能基数の影響
2-4.水酸基濃度の影響
2-5.末端不純物濃度の影響
3.エポキシ樹脂の一般的な耐熱性向上技術の紹介
3-1.官能基濃度の影響
3-2.官能基数の影響
3-3.骨格の剛直性の影響
3-4.硬化速度の影響
4.各種電気電子材料の技術動向
4-1.半導体パッケージ
4-2.高周波基板
4-3.パワー半導体デバイス
第3部 設計・応用編
1.耐熱性と相反する重要特性に関する解説
2.耐熱性と相反する諸特性を両立する分子デザインとその合成技術
2-1.耐熱性×流動性
2-2.耐熱性×吸湿性
2-3.耐熱性×誘電特性(活性エステル型硬化剤の解説)
2-4.耐熱性×難燃性
2-5.熱劣化と構造の関係
3.耐熱性と相反する諸特性を両立する分子デザインを応用した
最新の特殊エポキシ樹脂・エポキシ樹脂硬化剤の紹介
<質疑応答>
セミナー講師
DIC株式会社 総合研究所 コア機能開発センター サイエンティスト 博士(工学) 有田 和郎 先生
セミナー受講料
1名47,300円(税込(消費税10%)、資料・昼食付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき36,300円
*学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引。
受講料
47,300円(税込)/人
関連セミナー
もっと見る関連教材
もっと見る関連記事
もっと見る-
RO膜(逆浸透膜)とは?RO膜による水処理の仕組み、メリット・デメリットをわかりやすく解説
【目次】 水は私たちの生活に欠かせない資源であり、その水質は健康や環境に大きな影響を与えます。近年、世界中で水資源の不足... -
IGBTとは?原理と仕組み、その利用法をわかりやすく解説
【目次】 IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)は、現代の電力エレクトロニクスにおいて非常に重要な役割を果たしています。特に、... -
熱雑音とは?知っておくべき基礎知識と対策法をわかりやすく解説
【目次】 電子機器や通信システムにおいて、熱雑音は避けて通れない問題です。特に、精密な測定や高性能なデバイスを求める現代においてその... -
SiC MOSFETとは?仕組みや利用における利点と欠点について解説
【目次】 シリコンカーバイド(SiC)金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)は、次世代のパワーエレクト...










![[入門者OK]<br/>この分野の初歩から説明します 初心者向けセミナーです](https://assets.monodukuri.com/img/beginner-mark.png?d=0x0) エポキシ樹脂の基礎と高機能化技術〜硬化反応の基礎から構造・物性の理解、耐熱性と諸特性の両立のための設計・応用技術まで〜
エポキシ樹脂の基礎と高機能化技術〜硬化反応の基礎から構造・物性の理解、耐熱性と諸特性の両立のための設計・応用技術まで〜